擬態
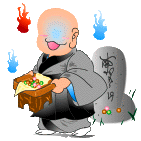
- 藤原晴彦:「似せてだます擬態の不思議な世界」、化学同人、'07を読む。私の擬態との出会いは中学生2年生になった頃だった。生物班という虫屋のグループに籍を置き、蝶の蒐集に夢中であった。コノハチョウという、名前の通りに、翅裏面が枯れ葉そっくりの蝶を標本箱の中に見つけたときである。もう半世紀以上60年近い昔になる。この蝶にかぎらずタテハチョウ科には、翅を閉じると、樹木の景色に溶け込んで見分けにくくなる蝶が多い。でもタテハチョウ科の蝶は一般に停まっているとき常に裏面を見せるのではなく、時折翅を開閉するのでほんとに擬態なのか疑問である。
- 歯切れが悪いのは、私はコノハチョウを自然界の生きた姿で見たことがないからだ。印旛沼ほとりの「くさぶえの丘」の飼育室で見たことはある。本HPの「金よりも金色」にちょっとだけ触れている。コノハチョウ生息地の南西諸島には何度か立ち寄ったが、今もって現地ではお目にかかれない幻の蝶である。擬態の知識は最近になって急速に拡大した。NHK「ダーウィンが来た!」に代表されるTV自然探訪シリーズが、世界中の珍しい生物を紹介してくれる。著者は分子生物学の立場を強調している。直感的にはちょっとそれはまだ無理なのではないかと思う、でも読んでみよう。
- タテハチョウ科には、クジャクチョウという文字通り孔雀の羽毛のような艶やかな翅をした蝶がいる。前翅にも後翅にも目玉を思わせる模様が付いている。残念ながらこの蝶にも飛翔する姿でお目に掛かったことがない。目玉模様を殆どの種が持っているのがジャノメ科の蝶だ。彼等は大きな擬態の目玉で捕食者を脅しているのだ。もっと手が込んだ脅し擬態はシロオビアゲハ(メス)だという。毒蝶のベニモンアゲハのそっくりさんに化けて、オレを食べると腹痛を起こすぞと悠々と大空に舞う。赤斑点の多い大層派手な模様だからむしろ存在を誇示している。南西諸島で何度かお目に掛かった。
- 私ども人間はヘビ嫌いが多い。むかし恐竜時代に、哺乳類が痛めつけられた苦悩が、遺伝子に刷り込まれているからだと聞いたことがある。同じように毒々しい色というのがあって、色を視覚による食の一次選別手段として有効に利用している。例えば毒茸。でも敵も然る者だから、しょっちゅう騙されて、中毒騒ぎになる。書いてはないが、捕食者一般にこの原理が成り立つのであれば、ドきつい赤を黒などで囲ってなお一層に目立たせた模様は、広い意味での擬態である。アゲハに比較的多く見られる。上に引用した「金よりも金色」は飼育室のオオゴマダラの蛹を指している。私はきんきらきんに輝く蛹など鳥は餌と思わないだろうと書いた。本書は究極のカモフラージュと書いている。
- タテハやジャノメの目玉模様の輪郭線を描く遺伝子は、分子生物学的成果の一つだそうだ。模様のグランドデザインを決める最上位遺伝子が、ショウジョウバエに見付かった、脚の大枠構造を決める遺伝子と共通するという。奇妙に思えるが、ハエの脚は円錐形で、頂点から見れば円錐は同心円の集合だから、脈絡が繋がっているという。形態形成物質が中心から半径方向に拡散する。その中心点を途中で焼き切ると文様の成長は止まる。でもその模様を何色のクレヨンで色分けするかについては何ら説明が出来ない。輪郭線は、出発物質のチロシンが、酵素を介して黒色のメラミン色素に変化することで描かれる。他の色に比べればはるかに単純だ。それでも酵素が細胞内に出来たり出来なかったりする機構は皆目分からないと云う。分子生物学が、ここ20年の間に、画期的な進歩を遂げたと云ってもこの程度である。
- カイコは完璧に家畜化された動物である。自然の桑の木に載せてやっても一度地面に落ちると、もう元の位置に戻れずアリの餌食になってしまう。成虫の蛾は飛ぶことが出来ない。大量飼育可能になったために、貴重な昆虫資料にされてしまう。性フェロモンでノーベル化学賞を取ったブーテナント教授の実験材料は、日本から送られた大量のカイコであった(石井象二郎他:「新ファーブル昆虫記」、日本化学会編、大日本図書、'91)。このHPの「蚕糸王国・岡谷」に60年ぶりかに見たお蚕さまの生きた姿を書いている。彼等は緑の葉の中で白い身体をくねらせつつ、メタボリックシンドロームが心配になるほど食いに食い、大きな繭を作るのに専心する。身体は白い方が管理し易い。でも品種改良以前の原生種には飛べる翅もあるし、外敵から身を守る擬態も使う。カイコに表れる紋様はその名残だ。紋様遺伝子研究は後一息までに進んでいるそうだ。カイコを材料に選んだ理由はブーテナント教授と同じだろう。
- お蚕さまの成虫の正確な姿は記憶にない。が、ガであることは間違いない。蛾眉山月半輪秋・・という李白の七言絶句が頭に浮かんだ。NHK中国大紀行で蛾眉山紹介が出たばかりだったからだ。昔はチョウ目(鱗翅目)はチョウ亜目とガ亜目に分かれていた。今はその区別はない。生物学的に無意味だからと云う。蛾の触角のような眉とは唐時代の美人に対する褒め言葉だが、今の中国でもそうなのだろうか。旅人の関口知宏はそんな質問をしてくれなかった。余談はさておき、チョウ目の幼虫はまことに無防備である。成虫はまだジグザグ飛翔により鳥の攻撃から逃れられるが、幼虫は発見されればそれまでだ。だからあまり知られていないが、手の込んだ迷彩服を着る。
- ナミアゲハは、家紋(揚羽蝶・・平家の流れ、織田家もこれ)になって出てくるほどに、日本人にはお馴染みの蝶である。幼虫は4回脱皮する。第4齢までは鳥の糞の擬態だが、第5齢になるともうウンコより大きくなってしまうからであろう、緑の自衛隊まがいの服装になる。キアゲハはナミアゲハとは交雑できるほどに種が近いが、幼虫の迷彩服は全く別のものを着る。食草が前者がミカン科植物なのに対し、後者がセリ科で全く違う。昆虫の世界は本当に不思議だ。でもこの食草は人間にとって研究材料とするのに好適だ。迷彩服の分子生物学、生化学的研究が進んでいるという。ファーブル先生の研究を思い起こさせるが、ホルモンの時期を調節して、鳥の糞模様の第5齢幼虫を作り出すことが出来たとある。成虫で忘れてはならない擬態に春型と夏型の変化がある。一般に夏型の方が黒っぽい。殆ど触れられていないが、幼虫は気候の先読みをするのか、それとも黒人と白人のような分離をしているのか興味がある。
- 聴覚利用の擬態として取り上げられた事例では、カッコウの幼鳥が育ての親ヨシキリの巣で、ヨシキリの幼鳥の声を物まねする話が面白かった。托卵ではホトトギスが有名であるが、ウグイスの巣で同じことが行われるのであろうか。臭覚による擬態としてはフェロモン利用の化学擬態がある。アリと同じ仲間認識フェロモンを体表から出して巣に居着いてしまうコオロギがあるそうだ。ゴイシシジミは幼虫時代をアリと共生して過ごすことで有名だが、幼虫の密腺にあると理由付けられてきた。この幼虫は肉食でアリの卵を食って生活するとんでもないやつだ。密だけでアリを騙しているのかフェロモンもあるのか触れられていない。
- 微生物が宿主を騙す行為を擬態と言っていいのか疑問である。この本にはそれも含めている。私はエイズ・ウィルス問題が噴出したときにたまたま教職にあったから、つけやきば的に勉強して、学生に概要を話したことがある。ウィルスでもやるぐらいだから、アメーバが騙しのテクニックを使っても驚くことはない。マラリアというアメーバがそうだという。世界で年に3億人が罹り、100万人以上が死ぬという。治療の難しさはマラリアを特徴付けるタンパクがどんどん変化するためだ。エイズがレトロ・ウィルスで、忍者ウィルスと呼ばれるほどに変化が激しいために、容易にワクチンなど作れないと言う話と符合する。
- あとがきを読むと、本書がヒトの擬態とムシの擬態を対比させて読本にしようとしたことが解る。結構人間社会の詐欺事件などが織り込まれていてそれなりに面白いが、最高等動物にムシを対比させる試みは所詮無理な話であることも分かった。
('07/05/06)
