武士の一分
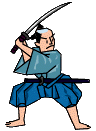
- 山田洋次監督映画「武士の一分」を見た。その前日であったか、本年の日本映画界の総括が新聞に出た。最盛期には邦画が映画市場総売上の78%を占めたが、昨今の低迷期には20%台に落ちていた。今日本映画は復活期にあり、本年は50%を超した。評判を取った映画の一例にこの「武士の一分」が上がっていた。私は山田監督の時代劇に注目しているから、こんな論評が無くても出掛けたであろう。封切り直後は人で溢れかえるので、何週間か過ぎてから見に行くことにしている。今回の館内は1/3ほどの入りで、日に5回の上映となっていた。
- まず映画の音響効果を褒めておこう。映画館の京成ローザ10がフィルム(?)の録音を満足すべき状態に再生している点の評価もしておこう。にわかめくらの剣士・三村新之丞が頼る感覚の中で聴覚の占めるウェイトは大きい。カメラの視野には入らない位置から発せられる音が、思わず顔をそちらに向けたくなるような立体効果を与えられている。妻や仲間の声であったり、虫の音であったり、鳥かごの中からであったり、おとないの声であったり、風の音であったりする。道場に稽古に来た新之丞に師が茶碗を落として注意力を逸らさせる場面、決闘の場で一際風が強く吹いて、新之丞の剣感覚を狂わすときの誇張した風音など音の設計にプロを感じる。盲目に気付き将来に絶望したときの新之丞の苛立ちや不安が、言葉の陰欝な抑揚だけで見事に表現されている。表情は能面のように変わらず、見えぬ目の視点が不気味にあらぬ方向に向いている。私の持っている武士のイメージにピッタリだ。木村拓哉はなかなかの俳優である。
- 殿様の台所組織を映像で見るのは初めてであった。狭い調理場に10人ほどの侍が料理を作っている。隣の小部屋に毒味役5人が控えており、それぞれが異なる椀を毒味する。藩侯毒殺防止制度だ。パスしたら台所頭(広式番)に率いられて藩侯座敷に運ばれる。受け取った配膳給仕役が並べて藩侯の着席を待つ。映像は昼の膳であった。藩侯一人に頭以下20人からの侍がかかりきりである。藤沢周平原作だから、出てこなかったがどうせ東北裏日本側に仮想された海坂藩七万石にまつわるお話である。前日にCh 4で三部作の一つ「たそがれ清兵衛」を見た。あそこに使われた方言がそのままこの映画にも使われている。毒味役が侍であることは知っていたが、給仕人には女性が出てくる映像の方が普通だ。海坂藩は一際古風な藩であったのか。不幸は貝料理がもたらす。
- 貝毒が含まれていたのである。映画ではある時期に貝が毒性を持つことがあると言っていた。いま流行のノロウィルスは牡蠣を媒介する場合があるというが、あれに体内繁殖されても健康体の人なら下痢程度で済む。新之丞は剣で鍛えた強健な身体であったが、死を免れたものの失明した。そんな強烈な貝毒を私は知らない。フグ毒並みだ。フグは養殖物では毒性が全くない場合もあるそうで、理由は寄生プランクトンに原因があるからだそうだ。二枚貝の毒性も、ノロは別だが、たいていはプランクトンに起因するという。さて、藩主毒殺未遂事件かと思われたが、食材選定の問題に帰すことが出来、藩は安堵する。だが、台所頭は責任を取らされる。彼は自宅に係累が隣室に控え焼香する中で、位牌の並ぶ仏前に読経したあと切腹する。切腹は死ぬまでに時間がかかる。刀を腹に立てたあとの苦悶の声が隣室に響く。武士の責任の取り方をリアルに描いて素晴らしい。
- 三部作の何れに対しても云えるのだが、立ち回りが素晴らしい。真に迫っている。私は真剣勝負など見たことがないから、真に迫ると言っても、シチュエーションから想定される真の姿と言うことだ。でもそこが大切なのである。今回はNHK大河ドラマ「功名が辻」の光秀を演じた坂東三津五郎との対戦であった。勝新太郎・座頭市の立ち回りもなかなか見せたが、綺麗すぎて何か現実味が薄かった。この映画ではめくらの弱点を十分に見せながら、なおかつ相手を倒す。左腕の付け根あたりに深手を負わせ、「武士の一分」が立ったあとはとどめを控える。三津五郎の方は対戦相手を最後まで明かさずに翌日残りの手で切腹する。私闘は御法度で、表に出れば相手もただでは済まない。だが、相手を司法の手で切るのはいいが、理由が理由だけに家にとっては末代までの恥と感じたのであろう。ベネディクトは「菊と刀」に日本文化を「恥の文化」と言ったが、その面目躍如たるものがある。
- 笹野高史は私のお気に入りのバイプレイヤーである。その名を覚えたのは村上弘明・沢口靖子主演「新・御宿かわせみ」の番頭役だった。その後も映画やTVドラマの中で幅広く彼を見かけた。喜劇「釣りバカ日記」には社長の運転手で毎回出てくる。昨夜の「男はつらいよ(44)寅次郎の告白」にもちょい役の釣り人で出ていた。寅さんシリーズでも結構活躍しているらしい。今回もはまり役だった。それにしてもたった30石の下級武士に過ぎぬ三村家にも仲間がいるとは驚きだ。亡父の代からの忠義ものである。通いらしい。仲間とは公的私的関係無しの便利屋である。薪割り、雑巾掛け、庭掃除、女房が居なくなると炊事洗濯まで、家事一切を引き受けている。主人の役所出仕の時は供を仰せつかり、果たし合いの文使い、介添え役何でもこなす。彼は家僕としての立場を越えて、時には事情を飲み込んだ家族のように振る舞わねばならぬ。離婚された妻・加世を「飯炊き女」と偽って家に引き入れる。加世は孤児で離婚されても戻る家がないという伏線が有効である。主役よりも難しい役柄ではないかと思うときもある。
- 加世役の壇れいには初めてお目にかかった。武士の女房とはこんなであったかと思わせる好演ぶりだ。山田監督の演技指導が良かったからかもしれない。あるいはそれだけの演技力を監督が見抜いて主役に抜擢したのかも知れない。たそがれ清兵衛の宮沢りえについても、似たような感想をこのHPに載せたように思う。30石の家にしては女房殿の衣服も髪も整いすぎている欠点は感じる。新之丞の父母に引き取られて育ったという前歴から、お家大事という考えが殆ど本能に近く身に付いてしまっていたのであろう。新之丞の失明につけ込んだ上役の餌食になる。夫のお手討ち覚悟の上であった。武士には、なんとしても家禄を守ろうという志向が強いことは、ことに藤沢周平の作品に強く表れる。基本的には武士の大半は無用の長物であった平和な時代が百年二百年と続いた、ということは自由市場ではなかったが、雇用者側の極端な買い手市場だったから、こんな今ならとんでもない異常な感覚が妻女にまで浸透していたのであろう。
- 失明した新之丞は、順当ならば、禄を召し上げられ捨て扶持で飼い殺しになる。家は返上せねばならない。事実、家老は後日の新之丞の処分を、殿に、捨て扶持20俵と上申する。三村家をどうするかは親族の大問題だ。兄をヘッドとする親族会議が行われる。たいていこんな会議では何も決まらず、迷惑の押し付け合いで紛糾しただけの結果になるが、大家族主義の下では、親族一同の責任で面倒を見なければならぬと言う鉄則の確認にはなっている。決定には当事者は従わなければならぬ。その決定は、加世が、以前から色目を使っていた上役を訪問し懇願するというもので、事件の火種になってしまう。親族一同は殿の判断を待つべきであった。殿は、身代わりになった功労者として、30石のまま保養に努めさせると言う決定をした。戦国時代から侍は怪我と弁当は自分持ちだった。毒に当たっても自分持ちとして何ら不思議に思わなかったのであろう。その点海坂藩藩主は開明君主であった。決定は先例となってその後の藩の政治に影響することとなるだろうから、時代の進歩に一石を投じたことになった。
('06/12/24)
