与謝野源氏
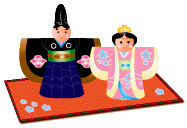
- 与謝野晶子訳:「全訳 源氏物語(上)(中)(下)」、角川文庫、'71を読む。この年になって今更源氏でもないと思うが、近頃の本屋には平積みにいい本が並ばないので、いつかは読もうと買ったまま積読10年を超したこの本をとうとう手に取ることにした。源氏物語はもう2回は読んでいる。原文はとても歯が立たないから、現代語訳でである。一つは円地文子、もう一つは田辺聖子が翻訳者であった。後者は宇治十帖を省き、登場人物に大阪弁を使う姫君をもうけたりして、かなり意訳的であった。与謝野晶子訳と並び戦前から著名であった現代訳に谷崎潤一郎の訳がある。最近では瀬戸内寂聴訳が有名だ。村山りゅうの朗読もあった。文学者は一度は我が口であるいは我が手で、この小説を今の言葉で語り、書き残してみたい誘惑に取り憑かれるものらしい。
- 更級日記は高校国語の教材であった。少女の頃の著者・菅原孝標女が、源氏物語50何帖をおばから贈られ読みふけり、「后の位も何にかはせむ」と、夢中の心境を書き留めていた。中流貴族の姫にとって后の位とは、望んでも手の届かぬ、しかし仄かに実態の分かる憧れの地位であったのだろう。それよりも源氏の方がいいと言い切っている。この一言は50何年間を経た今日まで私の脳裏から離れなかった。原文のままで口に出せる唯一の文言である。今頃になってまだ読む気にさせられる大きな理由になっている。
- 孝標の娘が何に夢中になったかには興味がある。彼女は多分中学生ぐらいの年齢だ。あの時代は早婚だったがまだちょっと間があるはずだ。それに肉体的には現代の方がずっと早熟の傾向にあると思うから、彼女は身体の方は今の小学生高学年ぐらいだっただろう。夢多い思春期の入口にあって、源氏に描かれた濃密な大人の恋は、おそらくは理解できなかったであろう。それよりも、大人の世界への想像を掻き立てる見事な文章に、引きずり込まれていったというのが本当のところであろう。文章はおそらくは当時の話し言葉に準じた文体であろう。現代の文語と口語ぐらいの開きがあったなら、いくら菅原が学者の家系でも、読んで面白いと感じるであろうか。
- 現代訳だけだがもう何回か読んだので、好きな巻を摘み食いにする。まず空蝉。中流貴族の奥様が仕掛けられる浮気話。彼女は賢明な身の処置で家庭の破綻を防ぐ。以前は昼ドラで遠慮気味だったが、今は市民権を得たように、昼夜区別無しにやっている不倫ドラマの主人公たちに見習ってほしい進退だ。私は現役を日本總中産階級時代に終えた。格差が目立たずワーキングプアなどという言葉もなかった比較的健康な社会を生きたから、こんなタイプのお話を好むのであろうか。でも空蝉は前巻・帚木の続きだから、そこも読まねばならぬ。この帚木は苦手である。苦手と言えば贈答歌がある。歌人の晶子には理解容易だったのか、歌に解釈も訳もつけてない。素養のない私には源氏に出てくる歌はまず20%ほどしか分からない。
- 帝のご謹慎日の宿直をする4人の、それぞれ自信のある青年貴族が男女論を闘わす。謹慎とは物忌みの訳だ。晶子は平易に平易にと心掛けて翻訳しているから、現在の若人でも十分読める文章になっている。それでも原文に忠実に、いつピリウドが来るか分からぬ長い長い文章が挟まる。我らのような論文書きは要点を簡明にと毎度努力する。それと正反対の行き方だ。あっちを立てればこっちが立たずの議論には向いているのかも知れない。さて中身。男から見た恋人論は、本質は変わらぬまでも時代環境がすっかり変わった今日ではあまり通用しない。男の身勝手はこんなものと思って読むなら解らぬでもない。夫婦論は今でも応用が利く内容だ。紫式部は確かに結婚していたと分かる。ちょっと雨夜の女の品定めを引用してみよう。孝標の姫御はきっと帚木は飛ばして読んだのだろう。
- [妻に必要な資格は家庭を預かることですから・・・、ただ物質的な世話だけを一生懸命にやいてくれる、そんなのではね。・・階級も何も言いません。容貌もどうでもいいとします。片よった性質でさえなければ、まじめで素直な人を妻にすべきだと思います。(家出や出家の反抗に対して)一度そんなことがあったあとでは真実の夫婦愛がかえってこないものです。・・何人かの女からよいところを取って、悪いところの省かれたような、そんな女はどこにもあるものですか。・・(菊の宴に作詩に懸命の時菊の歌を贈られたとしたら)知っていることでも知らぬ顔をして、言いたいことがあっても機会を一、二度ははずして、そのあとで言えばよいだろうと思いますね。]。
- 私はこのHPの「紅花」に次のように書いている。[ベニバナは末摘花とも云った。源氏物語第6帖の題はこの「末摘花」である。延喜式には宮中の御服や調度品の紅染法と紅花貢納の規定があるそうだから、平安時代既に貴族階級にもよく知られた花であったらしい。常陸の宮の姫君が孤児になって寂しく暮らしておられる。その彼女に源氏が言い寄るが、雪明かりに顔を見てビックリ。鼻が象鼻でしかも先端が赤い。だから「末摘花」。源氏ほどの男が摘むべき花ではなかった。しかし源氏は最後は自身の邸宅東の院に彼女を引き取り安楽な終生を約束する。源氏物語には色んな恋の冒険が語られるが、空蝉と末摘花はとりわけ人間味豊かな語り口で好きだ。]。左様、この姫君も私の好みである。ことに異性に対しては判官贔屓になるものらしい。源氏物語絵巻・蓬生には彼女の荒れ果てた屋敷に源氏と従者が佇む姿が趣深く描かれている。
- 野の宮神社は嵯峨野にある。天竜寺の近く、竹林の脇で風情のある中規模のお宮だ。丸太黒木の鳥居で有名だったが、私が訪れたころは、鳥居は黒色のコンクリート造りだった。今はどうなっているのだろうか。源氏物語で重要な役割を担う建造物で現に実在するものといえば、このお宮と伊勢神宮である。そして双方とも六条御息所と関係している。私の推挙する第三の女性である。彼女は東宮未亡人というやんごとなきお立場を高く矜持され、自由な感情表現ましてや行動を謹んでおられる。しかし光源氏に対する溢れる情念は疎遠になると共に抑え切れぬものとなり、光源氏の女たちに物の怪となって災難をもたらす。平和な源氏物語にあって強烈なアクセントとなり、小説の名声を不動のものにした立役者だ。野の宮神社で禊ぎする彼女を訪れる光源氏の場面は榊(賢木)の巻の冒頭だが、そこは名文中の名文なんだそうだ。今は観光客が溢れていようが、平安朝時代は、嵯峨野が化野で、遺骸を捨てるそれは淋しい場所であったと理解すれば、なお名文が身に迫ってこようというものだ。しかも秋も深まったころである。
- 光源氏の女の論評はこれぐらいにして、巻末の池田亀鑑先生の解説から、我が国の戦中戦前の軍国政権の対応ぶりを引用しよう。[源氏物語の影響は、・・、広く日本文化の全面にわたり、生活の諸方面に及んだ。・・(それを軟弱文化と苦々しく思う彼等側からは)・・不倫の恋愛を取り扱っているとか、皇室の尊厳を傷つけるとか、さまざまな低劣な議論があらわれ、・・、ついに焚書の論さえも一部の過激派の間には叫ばれるに至った。この狂騒は今日から考えると愚にもつかぬことながら、その当時としては真剣な問題であった。この古典を護り続けることは容易ならぬ、命がけの仕事であった。]。私は戦中を小学校生徒で過ごした。だから雰囲気が分かる。命がけという表現を大げさなと笑う気にはなれない。現在の中国もこれに近い雰囲気があるのではないか。主義主張がどんなに立派でも、独裁形態をとらざるを得ない国は所詮そんなものである。
('06/12/21)
