迷走する帝国Ⅱ
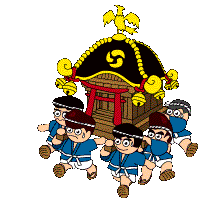
- 塩野七生:「ローマ人の物語ⅩⅡ~迷走する帝国~」、新潮社、'03を読む。本題の迷走する帝国Ⅱは「第2部 ローマ帝国・三世紀後半」を扱う。このシリーズを読みながらいつも思うのは、同時期の日本がまだ弥生時代だったと言うことだ。卑弥呼の記事が魏志倭人伝に表れるのが三世紀前半だ。遺跡、遺物に見る文明レベルの高さもさることながら、私は、主権在民の多民族多文化法治国家という今の世界国家の理想の原型が、そのとき既に実際に存在し、1200年に亘って機能し続けたことに感嘆せざるを得ない。
- 70才の皇帝ヴァレリアヌスが1万の軍兵と共にペルシャ王の捕囚になった。彼らは結果としてはローマに見捨てられ、ペルシャで死ぬ。ゲルマン民族の侵入はますます激しくなる。ローマは四面楚歌になった。東方ではパルミア王国が建ち、こともあろうにローマ皇帝私領のエジプトまでその支配下とした。パルミアとはシリア砂漠にある中継貿易で栄えた都市で、遺跡が今にその繁栄を伝える。パクス・ロマーナあってのパルミアだったが、そこの武将がパクスを守ったのである。西方にはガリア帝国が建った。息子の新皇帝ガリエヌスは最も激しいドナウ河防衛線の対ゴート民族戦闘に掛かりきりで、帝国三分にも打つ手がなかった。興隆期には蛮族を対岸で邀撃する攻めの守りだったが、三世紀後半にはいると防衛線はずたずたになり、多くの砦や軍団基地が放棄され、住民は居住地に高い防壁を築いて侵略から自衛せねばならなくなった。平地は無住化し、耕地は荒れ果て、それを当てにしている兵站基地に支障をきたし、軍団を弱体化させる悪循環が始まった。
- ガリエヌスが手をこまねいていたわけではない。機動部隊を騎兵中心で固めた。蛮族が騎馬軍団であったのに合わせたのである。元老院と軍隊を完全分離した。おそらく差し迫ったニーズから、即戦力登用に道をつけたかったのであろう。しかしこの法律はローマをローマたらしめた、軍事+政治の人材プールとしての元老院をより形骸化する結果となり、非ローマ化の重要要因とされるようになる。戦争に継ぐ戦争は国庫に破綻をもたらす。デナリウス銀貨に取って代わったアントニヌス銀貨の銀含有量が僅かに5%で、銅貨に銀メッキという品物になり、銅貨は鋳造されなくなった。過去の良貨はタンス預金されたことが現存する2千年前の銀貨の多さから証明されると云う。ガリエヌス帝は騎兵隊長に殺された。蛮族に押されっぱなしの戦線情況の責任を取らされた格好だった。
- 皇帝クラウディウス・ゴティクスは謀殺者ではないが騎兵隊長である。彼は対ゴート戦に数々の実績を上げ、ついにはドナウ河下流防衛線内に彼らの一部を導き、定着させることに成功した。ローマにとって不幸だったのは新皇帝が疫病で早々に死去したことである。度重なる戦役による難民の増加と都市流入、経済状態の悪化、食糧難などのマイナス要因の増加で、風呂好きで今流には保健衛生感覚に優れたローマ市民も疫病流行頻度の増加を防げなくなっていた。将兵は有能な武将アウレリウスを皇帝に据えた。彼もドナウ河下流域に定着したローマ化した蛮族の出身であった。
- 大陸に繁栄を謳歌した都市は堅固な城壁で囲まれているのが普通であった。NHK夏の特集番組「世界遺産 フランス縦断の旅」でプロヴァンを映し出していた。今でも2kmにわたって12世紀の城壁が残っている。中世の交易都市である。古代の地中海都市も城壁都市だった。だが、ローマはカエサル時代に町の拡張のためにこの城壁が取り去られた。パクス・ロマーナが外敵を防衛線の外に釘付け出来たからであった。その300年を経てアウレリウス帝はローマ城壁(周囲19km、高さ平均6m、施工期間6年)の建設を決定した。即位の年にヴァンダル族が中部イタリアまで侵入した事件がきっかけであった。元老院はアウレリウスがヴァンダルを完膚に打ちのめすと、それまでの恐怖を忘れ、侵略を許した傭兵隊長上がりの皇帝を批判した。軍事を分離され口出しできなくなった翼賛議会の恨み言と解釈されている。元老院は皇帝から銅貨発行権をも取り上げられいよいよ有名無実化されて行く。
- 皇帝は今のルーマニアであるダキアを放棄する。ゲルマン民族活性化後はもうダキア維持は重荷であった。だが165年の統治は見事な同化策の証拠を残した。現代のイタリア人は半分ぐらいルーマニア語を理解できるという。パルミラ王国の女王ゼノビアは皇帝の軍を見くびり合戦を挑んだが最後は捕囚の身となり、のちの凱旋式を飾る身の上となった。全身に所有の宝飾品をつけさせられ、極上の見せ物であったという。ガリア帝国皇帝は闘わずして軍門に下り、自らは元老院議員の議席を回復した。皇帝は最後の仕上げであるペルシャ遠征に赴く途中、些細な誤解から小心の配下に殺される。4年と9ヶ月の治世であった。
- 皇帝が次々に代わってのち6年治めることが出来たのはプロブスであった。彼はライン河をドナウ河を乗り越えてくる蛮族との合戦に明け暮れた。そしてまたもや謀殺される。貴種不要の実力主義が横行するこの時代に首謀者の位も下がり、今回の謀殺は兵士階級だった。荒廃した農地の回復事業に彼らを使おうとしたことに不満が募ったという。元老院はもう帝位には無関係となり、近衛軍団の長官カルスが軍に推薦された。彼はペルシャに進軍した。弱体化していたササン朝ペルシャには邀撃力がなく連戦連敗で首都まで明け渡す始末であった。だが悲劇が起きた。砂漠の落雷で彼は即死した。ローマ軍は引き上げ、共同皇帝の2人の息子は日を待たずして殺された。次の皇帝は遠征軍から立った。ディオクレティアヌスである。やはりドナウ河下流域出身であった。彼の在位は21年とそれまでの皇帝22人に比して非常に長い。ローマはそれまでとは違う時代に入った。
- 迷走する帝国には政局不安定にいよいよもう一つの危機材料・キリスト教の台頭が加わる。最終章はローマ帝国とキリスト教という題になっている。次のローマ人の物語ⅩⅢはキリスト教の国教化を扱う。その序曲である。帝国からローマの神髄を食い荒らして潰してしまうのがキリスト教だから、一番注目してよい巻になる。今日に照らしてまことに示唆的なのである。バーミアンの大仏が爆破されたとき、イスラムの多神教神像忌避の姿勢に改めて瞠目させられた。だが同じことを乗っ取り成功後のキリスト教徒はローマの神に対して行っている。皇帝は元老院によって神格化されると最も神々しい姿、即ち裸体の彫像となって神殿に祭られた。無数と言ってよいほどにあったはずの皇帝像は徹底して破壊された。この度量の狭さは、単純明快に人生を社会を解釈して見せようとする宗教や社会科学に対して、まずは心に留めておかなければならぬ用心帳第一条である。
- キリスト死後300年になって教徒の数は、今や属州のみならず本国さらに首都においてすら、無視できない集団になった。ユダヤ教の一分派であったキリスト教もその頃では独立の一神教である。教団の増勢についてこの章は理由を追及する。ギボン:「ローマ帝国衰亡史」、1776~88とドッズ:「不安の時代の異教徒とキリスト教徒」、1965がそのテキストだ。主因に彼らは合計7つの理由をあげている。詳細は本書さらには原文献に任せるとして、私が思うのは創価学会との類似性である。このHPに「創価学会」という書評を書いたのは一昨年であった。帰依が現実の生活に利益をもたらす。教団は信徒の不幸救済にあらゆる手を打った。寡婦、孤児、老人に失業者、病人、死人の葬式。冠婚葬祭全部という学会に何とよく似ていることか。指導者の高潔で禁欲的な生き方。学会はヒエラルキー頂上の名誉会長個人に発展の原動力を感じている。
- ディオクレティアヌス帝はローマ軍からキリスト教徒を追放する。教徒の数は、ついにキリスト教を公認する次のコンスタンティヌス帝の時代でも、最も多かったシリアの大都市アンティオキアでも住民の20人に1人ほどだったという。ちょっと意外だった。だが、数よりもキリスト教徒の団結力と相対的な非キリスト教徒の「末世」感覚というかアイデンティティ・クライシスが問題だ。キリスト教の勝利は、実はただ単に、ローマ側の弱体化と疲弊化に要因があったという。殉教司祭の手紙の一節は印象的である。「ローマはもはや老いた、・・。今では・・、自分自身の身体の重みをささえきれないでいる。」
('06/08/26)
