ローマ帝国の危機と克服[上]
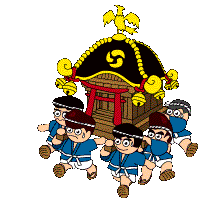
- 塩野七生:「ローマ人の物語21−危機と克服[上]−」、新潮文庫、'05を読む。BC 753年に建国したローマは例を見ない長寿命の国家であった。西ローマ帝国滅亡がAD 476年、東ローマ帝国は1453年まで存続している。ローマ市民はこの間に幾度も存亡の危機を迎えている。彼らはそのたび毎に賢明に対応した。ローマ帝国の最盛期はネルヴァ、トライアヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウス、マルクス・アウレリウスの五賢帝時代(96-180)だとしたら、この「危機と克服」の巻が取り扱う歴史は繁栄絶頂期の産みの苦しみを味わう時期になる。市民が直面したのは並みの危機ではなかった。同じ年に3人もの皇帝が殺害されたり、自死に追い込まれたことがあった。帝国が消滅してもおかしくない事件だったのに、なぜ不死身鳥のように甦り、更なる発展に結びつけたのか興味は尽きないではないか。
- 分冊「上」はその3人−ガルバ、オトー、ヴィテリウス−を記述する。皇室典範改正で我が国でもお血筋問題がクローズアップされている。順位はだいぶ後の方だが、継承権のある宮様のお一人が、男系をDNA問題から主張されたりして賑やかである。私は天皇家は今では宮中伝統文化の継承のためにあると思う。もはや天皇親政の時代ではないのだから、周囲が喧しく騒ぎ立てる必要はなく、天皇家内部でお決めになればいいと思う。ローマ帝国では、神君カエサルのお血筋と言うことがローマ市民や元老院の皇帝資格の判断基準の重要な一つであった。だが暴君ネロが支持を失い倒れると、選択肢はユリウス・クラウディウス家から名門貴族全般に広がり、さらにその枠が元老院議員ならと云うことになって行く。最後のヴィテリウスは父の代からの元老院議員であった。次の分冊の最初の皇帝ヴェスパニアヌスは、父の職も不確かな軍団のたたき上げということで、帝国でありながら、お血筋無縁の実力頭領型皇帝を戴く時代となって行く。
- 問題は実力とは何かであろう。元老院は、この時代になると、反中央の属州総督が戦に勝ち次代皇帝を名乗ると、唯々諾々と追認するという塩梅で、共和制時代の覇気も見識も指導力も失い、元老院属州の利権維持に汲々としているという有様であった。気分は武家政治が確立した鎌倉時代頃の日本の公家階級と似たような状態だったと思う。だがローマ帝国のシステムは日本とは全く違っていた。総督は皇帝の推薦通りだったとしても元老院の議決を必要とし、元老院議員で執政官出身でなければならなかったし、直接の実行力である軍団の兵士はローマ市民権所有者であった。軍団はイタリア本国に近衛軍団一つを残して全部を帝国の辺境に配備していた。地方の軍団の統率権は総督が握っている。次々擁立される皇帝はすべてこの辺境の軍団の支持の賜である。
- この頃になると植民二世三世とか、補助兵軍団長期勤務によりローマ市民権を得たものとかの、本国を知らない土着民や準土着民が軍団で幅を利かすようになる。オトーとヴィテリウスの交代期さらに次の交代期におけるライン軍団対ドナウ軍団の、従来に見なかった同胞間の血なまぐさい闘争は、こんな背景を持っていた。そうしておいおいと皇帝位をめぐる紛争が、上層部の権力争いから、階段に手が届くのを知った兵士階級の野試合的様相を見せるようになる。補助兵軍団は、ローマ市民権を持たない属州民の兵で構成されている。彼らの内乱戦闘参加はローマに対する侮りとなり、補助兵はその気分を属州に伝える媒体になった。今までは治まっていた属州民の反乱が勃発する。軍団を覇権確立のためにイタリアに転進させると武力の空白地帯が生じる。そこには蛮族が入り込んでくる。
- ヴィテリウスの最後は激しい市街戦を伴った。ローマ市内に兵を引き込むことは、何百年に亘って禁じられていたのに、ヴィテリウスは敢えて兵士を駐留させていた。ローマの守護神を祭る神殿が放火され炎上した。建国から数えて822年目の初めての出来事であった。もっとも激しい戦闘はヴィテリウスのライン軍団の精鋭が守る近衛兵兵舎で、彼が即位と共にクビにした旧近衛兵組織との間で起こったという。では市民はどうしていたか。歴史家タキトゥスの記述がある。著者の訳をそのまま引用する。「首都の民衆は、この日の市内での戦闘を、競技場で闘われる剣闘士試合でも見物しているように観戦した。敢闘する者には拍手と歓声を浴びせ、苦戦する者にはもっと気を入れて闘えとヤジをとばしながら。劣勢に陥った側が店や家の中に逃げ込もうものなら、引き出して殺せと要求するのは民衆のほうだった。・・」どこまで本当か知らないがひどい話である。市民は公衆浴場や、居酒屋や、娼家で日常通りの生活をしていた。民衆は内乱の行方などに関心がなかった。市街戦という見せ物に関心があっただけだという。彼らには皇帝のクビのすげ替えなどどうでもよい無関心事であった。
- ここまで聞くともうローマはお終いだと思ってしまう。しかし著者は最初の「カバーの銀貨について」の説明に、こんな内乱にもかかわらず「現実の帝国の方は充分に機能していた・・。・・通貨鋳造所では、金や銀をちょろまかす所員もなく、・・良質な通貨が造られ、途中で奪われることもなく、広大な帝国の各地に運ばれていたのである。・・」と書いている。本書の随所で感じるのだが、人間性をがっちり把握した融通性のある聡明なシステムは、機能すると皇帝交替など茶番劇にしてしまうほどの威力が出るものだと言うことである。なぜこの分冊の皇帝たちは光秀の三日天下で終わったかについては、人を治める立場の人には誠に耳の痛い言葉の数々で要約してある。一番気に入った言葉は、ガルバ殺害の節に出てくる。「平凡な資質の持ち主は、本能的に、自分より優れた資質の持ち主を避ける。」次のヴェスパニアヌスは強力な助っ人を2人用意していた。彼は内乱の究極の勝利者になると共に、押し込まれた内患外憂の帝国を除々に回復する。
- ヴェスパニアヌスはユダヤ戦役の司令官であった。反乱を起こしたユダヤ王国はその頃イェルサレム市街を残して孤立していた。だが、彼はその戦役に留まった。同盟者たちが将来の皇帝に手を汚させたくなかったからだと書いてある。同胞間戦争はローマ市民内に恨みを残すから。なかなかの遠謀深謀である。イタリア本国に進攻したのはシリア属州総督のムキアヌスで、先発のドナウ軍団を追うように入った。エジプト皇帝直轄領長官のアレクサンドロスが遊軍の形で待機するという重厚な構えであった。
- 想定される外敵とは、留守中を思って、今までの相互不可侵条約の確認を行っている。ローマの伝統戦略が載っている。協定は信頼するが、それとて信頼できるところまでである。信頼できるところまでの基準は、自分たちの側の軍事上の防衛力である。平和条約を交わした相手との国境にも、以前と変わらない規模の軍事力を配置し続けるのだ。ムキアヌスは将来のための備えを残して出発する。ライン軍団を根こそぎ持ち出して空白を作ったヴィテリウスとはだいぶ出来が違う。帝国の安全を盤石にしたこの抑止力構想を現代日本人はよく理解せねばならない。下手に自衛隊など持つとそれを理由に侵略されるから、日本は丸裸のスッポンポンがよいと言う、何とも馬鹿げた議論を大真面目でやる政治家がおり、それを大きな活字で大真面目で取り上げる新聞があった。それも過去の話となったと思っていたら、「社民党自衛隊違憲説に復帰」の記事を目にした。安全音痴国と嘲られぬようにしたいものだ。
('06/02/09)
