放浪記
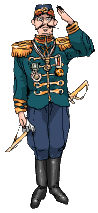
- NHK BS11に「放浪記」の放映があった。原作:林芙美子、監督:成瀬巳喜男、主演:高峰秀子、制作年:昭和37年(1962)の白黒映画である。私は以前このHPに林芙美子を書いている。原作も読んだ、評伝も見た、もう一つの映画「うず潮」も見た、尾道や桜島も訪れた、などなどけっこう私には縁のある作品である。高峰秀子がおふみ、田中絹代は母、宝田明が同棲の売れない文士と一応の対応はつくが、加東大介に相当する人物を原作に思い浮かべることは出来ない。これでもかこれでもかと続く苦痛の物語に、一陣の涼風を送り込まんがため、脚本家が書き加えた人物なのであろう。商業映画として仕方がなかったのだろう。
- 同時代の人物で、林芙美子ほどに魅力に富んだ生き方をした女性は見当たらない。彼女は、母親が桜島を20歳も年下の父と駆け落ちしたときに伴われた連れ子で、そのとき8歳であった、私生児だったという。父母は行商で主に西国を転々としながら糊口を凌いでいた。彼女はアルバイトで尾道の女学校を卒業した。それは前代未聞の出来事であった。女学校出は当時ではインテリに属していた。しかし上京した彼女にはまともな就職口はなく、カフェや牛飯屋の女給が精一杯の働き口ある。そのカフェも遊廓の近くで、遊び帰りの男が、一杯引っかけるために立ち寄るような場末であった。男たちは、からかい半分に、女給に50銭とか35銭とかの値を付ける。淫売行為1回に対する対価である。不景気な時代らしかった。当時は女学校卒事務員の月給が30円。妾の手当は80円で、こちらは帝大出の初任給と変わらない報酬のようであった。芙美子は5ヶ年のアナーキスト的生活の後、大正15年末に画家と結婚し、作家として成功、47歳で死ぬまで共に暮らす。それまでの廃退的刹那的生活を微塵も感じさせない、大変身の20年あまりであったようだ。
- 高峰秀子がこの映画に出演したときはもう37になっていた筈だ。母と共に上京した21歳の頃から、超流行作家になり机に寄りかかってうたた寝をする、おそらく死期に近い頃までを自在奔放に演じ分ける。おふみが赤貧状態から頂点に這い上がる20数年は、映画の中のセリフにもあるように、ゴミ箱をひっくり返したような臭気ふんぷんの人生だが、そこを明るく嫌みのない表現に仕上げたのは女優としての実力であろう。共演の草笛光子の解説では、成瀬監督は、めずらしくも高峰秀子の演技に、ほとんど文句を付けなかったという。
- いろんなメークで出てきて、見るものを愉しませる。同棲者の新しい恋人が、厚かましくも住まいに現れたときに見せる、所帯やつれの顔など見事だ。彼女は子役の頃から安定した演技力と、多分極端に走らぬ世渡りのうまさで息の長い女優生活を続けた。文才もあって何冊かの随筆をものにしている。その1冊「おいしい人間」を読むと、家庭的にはそう恵まれた方ではなかったらしいと思われる。忍耐が自然に環境から身に付いたのであろう。共演の顔ぶれは豪華である。既出出演者の他に飯田蝶子、小林桂樹、伊藤雄之助、加東武、名古屋章、林美智子、橋爪功等々多彩だ。のちの映画、TV-ドラマで主役、準主役あるいは名脇役として鳴らした俳優が並んでいる。まさしく日本映画黄金期の配役である。
- 字幕で詩が出てくる。男に心を奪われた女の切なさを歌った無題の詩である。外見には荒れた恋愛関係だが、おふみは瞬間瞬間に心を時めかせている。
私はお釈迦様に恋をしました
仄かに冷たい唇に接吻すれば
おおもったいない程の
痺れ心になりまする
もったいなさに
なだらかな血潮が
逆流しまする
- 原詩はもっと長いのだが、引用はここまでだった。詩人としても林芙美子は抜群の才能を持っていた。放浪記第二部の終わりにある自由律は放浪生活から足を洗う直前の歌で、いい詩である。そのさわりを以下に書き写す。やっぱり題名がない。映画には出てこない。
ああ二十五の女心の痛みかな
遠く海の色透きて見ゆる
黍畑に立ちたり二十五の女は
玉蜀黍よ、玉蜀黍
かくばかり胸の痛むかな
二十五の女は海を眺めてただ呆然となり果てぬ
一ツ二ツ三ツ四ツ
玉蜀黍の粒々は、二十五の女の侘びしくも物ほしげなる片言なり
蒼い海風も
黄いろなる黍畑の風も
黒い土の吐息も
二十五の女心を濡らすかな
- 同棲者は、いけ面だが生活力がない、そのくせプライドが高く、女給をして食わせてくれるおふみに「養ってやっていると鼻に掛けている」と言って暴力を振るう。その頃の女二十五歳は年増に属する。おふみはもう落ち着きたいと願っている。だが最後には家出をし、夜は木賃宿に雑魚寝をしながら、ミカン箱とローソクの灯りで放浪記を書き続ける。彼女はもう物書きとの同棲はこりごりだという。映画の場面と重ねるとそんな時期の詩である。
- 小説「放浪記」には随所に映画に出てきたエピソードが描かれている。カフェでウィスキーを10杯飲んで客から10円をせしめるシーン、ただ原文では酒の代金として店の収入になるのだが、映画ではチップとなっている。母と娘が夏の暑い盛りに大きな荷物を担いで行商をしている、「クレップのシャツと、すててこはいりませんか、お安くしておきますけどね」と声を掛ける。口上まで同じである。母が上京してくる、娘に弁当の残りを大事そうに手渡す、これもあった。義父が行商で売ったインチキ化粧品が腐っていたと訴えられ、警察でタコ釣られるシーンは「うず潮」にも出てくる名場面である。ただこれは「風琴と魚の町」に描かれている。おもちゃ製造の工場で働く場面、そこの雇い主がいつも30分時間を誤魔化して余計に働かせる話も「風琴と魚の町」に出ていたように思う。
- 映画の最後に放浪記出版記念パーティ出席者の私語が出てくる。あまりにも赤裸々に貧乏生活をぶちまける姿勢に批判的な意見が相次ぐ。最後に身勝手な元同棲者として敵役にされた男が登場して、憎しみをもって読んだが、見事な作品だと評価して去る。明治以来の封建的な厳しい道徳律を保持していた当時から見れば、確かに破天荒な小説であった。
('05/09/13)
