ユリウス・カエサル・ルビコン以後(上)
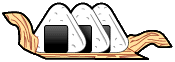
- 塩野七生:「ローマ人の物語〜ユリウス・カエサル ルビコン以後(上)〜」、新潮文庫、'04を読む。私はこの延々と続く物語にそろそろ飽き始めている。でもなぜか最近になって、TVでローマの遺跡や歴史の解説を見る機会が多くなり、その後押しを感じながら、興味よりも勉強するつもりで読んでいる。この分冊は共和国から帝国に変貌する直前の歴史である。民主主義体制だって、いつ独裁体制に変わるか知れたものではないと言うことだ。古代史の中では現世に最も役に立つ歴史である。それがdriving forceになっているようだ。ルビコン河を渡ったカエサルが、いよいよ元老院派の名将ポンペイウスに戦いを挑む。
- ローマの最高決定権は市民集会にある。その常設議会が元老院である。市民集会は常にローマの町中で開かれるし、元老院もローマにある。私は、カエサルの接近により元老院議員側が簡単に首都ローマを放棄し、イタリアからも撤退した理由がよく呑み込めなかった。対ガリア戦で鍛えられたカエサルの軍隊は確かに強力で脅威だったろう。しかし各地にローマ軍を派遣していても、イタリアが全くの空き巣であったわけでもないし、昔からの強い地盤を元老院各議員もポンペイウスも持っていたのにと思う。カエサルは北イタリアとフランスを支配するだけで、あとの地中海を取り巻く広大なローマ領は、イタリアの長靴地帯も含めてまだ体制側の支配下にあった。ローマを占拠すれば、相応しい官職を手に入れるのはそう困難ではない。つまり賊軍から官軍に変身できる。我が国でも天子と京都を掌中にしたものが終局の勝利者になった。
- ポンペイウスは持久戦を選んだ。確かに兵力、補給力、財力いずれも数字の上ではポンペイウス側に歩があった。制海権すらポンペイウスのものであった。一進一退の後に両雄対決の戦機がギリシャに訪れる。カエサル軍はポンペイウス軍のアドリア海沿岸主陣地を取り囲み陣地構築をする。しかし、少人数で大人数を取り囲むのは基本的には無理であった。対ガリア戦では成功したが、土木技術や戦略的兵器に格差があったからこそであった。ポンペイウスに弱点を突かれて、カエサルは一敗地にまみれ遁走する。だが平地での大会戦に勝利した。勝因は騎兵であった。1000の騎兵と2000の歴戦の重装歩兵によって、ポンペイウスの7000の騎兵を追い散らし、余勢を駆って倍以上の敵歩兵軍団を粉砕した。戦前からすでに戦勝気分で、戦後処理の議論に夢中であった元老院派の野望は敢えなく潰えた。ポンペイウスは海路をエジプトに逃げたが、エジプト王朝権力者のだまし討ちに合い、あっけない最期を遂げる。遺骨はローマの未亡人に届けられた。その墓は現存するという。ポンペイウス派は、逃避行の間に立ち寄ろうとした、それまでは自派の小アジア諸都市からも、冷たく門前払いを食わされている。武田勝頼が長篠の合戦に敗れて後、天目山で自刃するまでの経過と何か似ている。軍の組織力とかカリスマ性に足らない面があったのだろう。
- 一進一退と云った。カエサル側の一進はスペイン戦役である。大事な緒戦であった。勝敗とは別に、私は、長い間ポンペイウス側にあったスペインの実体について興味を感じる。この地の原住民は、ローマ時代からガリア人とは意識されていなかったらしい。現在カスティリャ人、アンダルシア人、バスク人、カタルニャ人、ガリシア人などと分類される人々は歴史民族学的にはどんな分類に入るのだろうか。バスク人が言語学的に独高の位置にあることぐらいは知っているが、さてそれがローマ時代さらにはそれ以前にはどうだったのだろう。一退は北アフリカ、今のチュニジアあたりでの対ヌミディア戦で起こった。ポンペイウス側に付いていたヌミディア王国軍の騎兵と象隊に、完膚なまでに打ちのめされたのである。ポエニ戦役で、カルタゴのハンニバルに従ったヌメディア騎兵は、アルプス越えをしたイタリアで優れた実力を示したし、逆にローマのスキピオに率いられたヌメディア騎兵は、ハンニバル軍をアフリカのザマで打ち破っている。このヌメディア王国に対する配慮を欠いたために、カエサル軍の兵士は、降伏者も含めて一兵残らず殺される羽目になった。
- いよいよ絶世の美女クレオパトラの登場になる。カエサル52才、クレオパトラ21才。この著者は君主論のマキュアヴェッリをしばしば引用する。君主論は、どうせローマ史を縦横無尽に活用し政治術のエッセンスを抽出した結果だろうから、塩野さんが引用するのはまことに当を得ている。今回は「民主的な討議でことを決する習慣をもたない民族に、それを移植しようと努めても無駄である。」という言葉を引用した。なんだかブッシュ大統領のイラク対策アフガン対策を冷やかしているように聞こえるから面白い。エジプトがローマの属州にならず、独立王国として残り得た理由の一つにこの言葉を当てている。独立王国と言っても、実質はローマの安全保障下にある属国同然の国であった。当時の王朝はアレキサンダー大王配下が築いたギリシャ系王朝であった。独立を保てた最大の理由は、今の日米関係のように、エジプトが徹頭徹尾親ローマ同盟国であったからである。だがもう一つの理由はエジプト文明にある。ピラミッドに象徴されるこの文明は、神政とも云えるほどの独裁政治を奉信する文明であった。ローマは人政だから、不必要な文明の衝突を避けたのである。その説明にマキュアヴェッリが引用された。
- カエサルはクレオパトラを女王の地位に引き戻す。それまでエジプトを牛耳っていた弟王を、アレクサンドリア戦役で打ち破った。超大国ローマに対して、当時のエジプトが中小国の一つでしかないことは、冷静な宮廷人なら理解できたはずだ。著者は「過去の大国はしばしばこの種の過りを犯す」と書く。当時のエジプトは3000年のエジプト文明と、アレキサンダー大王以来の300年のギリシャ文明という二重の輝かしい過去を誇っていた。カエサルは「内乱記」に「見たいと欲する現実しか見ない人は怖ろしい。」と記しているそうだ。これも真理である。古代に止まらず現代にももちろん当てはまる。どこかの将軍様は早く本当の現実に目覚めてほしいものだ。
- カエサルが危機に瀕した2局面が描かれている。1つはスペイン戦役を勝利してイタリアに引き返すとき、最も信頼していた軍団兵士にストライキを起こされた時である。カエサルは指示を受ける者(兵士)には義務があると言って、要求を拒否した上、全員に十分の一刑を言い渡した。十分の一刑とは抽選で十分の一の人数を選び、それを残りの十分の九が棒で殴り殺す刑である。幕僚の取りなしで刑の執行は延期になり、結局うやむやに終わった。指揮者の断固たる姿勢が、その後に及ぼした影響は計り知れなかったであろう。もう1つは、ポンペイウスとの直接対決第1回戦で敗れたときの演説である。彼は、この敗戦は、あらゆる配慮を怠らなかった指揮者の責任ではなく、兵士諸君の間違いの結果だと云った。安易に自分の責任だと言わなかった。彼は兵士の気概を呼び覚まし、第2回戦に勝ったのであった。NHKプロジェクトXでは、しばしば冷や飯を食わされている連中が、逆転の救世主になっている。私も部下を甘やかすばかりが能でないことは解っていたが、さて現実にはどうであったか。今となっては後悔先に立たずの局面ばかりを思い出す。
('05/02/04)
