古都
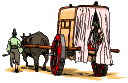
- 川端康成の「古都」を読む。書店の重版のコーナーでたまたま見つけた文庫本である。岩下志麻が主演した映画の「古都」は繰り返し見たが、原作を手に取るのは初めてである。康成にしては珍しい中編小説である。ちょうど映画化に適当な長さであったらしく、志麻の「古都」には、「伊豆の踊子」のような、追加の挿話など無かったように記憶する。純粋に京都だけが舞台の小説であるのも珍しい。京都の観光案内小説にもなっている。映画でははっきりしなかったが、小説には昭和36年と日時を特定できる部分がある。府立植物園の再開が書き入れられているからである。
- 作者は小説を新聞に一旦発表した後、単行本化のときに京都弁を全面的に校正したそうだ。記憶では、私の周囲は小説よりももう少し、特に男性は、標準語に近かったように思う。私は京都育ちといっても御土居のちょっと外に住まいした。主人公たちのように、御土居の中の本当の京都に住む人たちは、まだ小説のような会話をしていたのかもしれない。私はもう関東在住期間の方が長くなって、京都弁を忘れがちである。いくつも思い出させてくれたという意味でも読んだ価値があった。はじめの章「春の花」から気まぐれに選んでみる。みっともないやないの?(気恥ずかしいと思いませんか?)、行(イと発音)かはるわ(行かれますね)、うち(私)、おつむ(頭)、いとおすか(痛みますか)、しとうみやす(やってごらんなさい):文字ではなく音で記憶している言葉であるから、ラジオかテレビの朗読の時間にでも京都人に読んで欲しい本である。
- 相手を思いやり気遣う文化が穏やかに漂ってくる。私は、少し前に京都を離れていたが、昭和36年当時主人公とそう違わない年齢であった。小説の描く主人公たちの感性に共鳴できる素地は十分ある。親の世代には確かに色濃く、我々年代では幾分色あせた雰囲気で継承していた文化である。その理解がないと古都はつまらぬ過去の小説になってしまう。一卵性双生児の一方・千重子は捨て子になる。私は、双子の一方を捨てる習慣はさすがに話だけでしか知らなかった。二十歳の今は千重子が呉服問屋の嫡女、もう一方の苗子は親に死なれて杉丸太作りの作業員である。二人は祇園会の宵山の夕方に御旅所で再会する。事情を知る苗子が探していた。苗子が小雪が舞う師走の夜に、贈られた着物と帯で千重子をそっと訪れ、一夜を過ごし、早朝に去ってゆく。苗子が見送る千重子を振り返らないのは、「身分ちがい」が千重子の将来に触ってはいけないと思っているからである。気遣い文化の華のような結末である。
- 無いようで有る微妙な「身分ちがい」を、そのほか問屋と織屋の関係、大問屋と傾いた問屋の関係などで、さりげない会話の中に滲ませている。まだ親が結婚に責任を持つ時代であった。親子の会話にも自然と親の位置、子の位置が分かるような内容になっている。身分に対する絶妙の配慮がなされておりながら、それでいて現代の小説である点が康成の真骨頂なのであろう。NHK大河ドラマ「新選組!」は幕末の時代劇である。「古都」風の文化は、江戸においても、小説の昭和36年よりはもっと純粋に強く、生活の一部として人々に溶け込んでいたと思うが、ドラマはそれを微塵も感じさせぬ現代活劇風に進行している。このちぐはぐは決して視聴率を上げる方向に働かないであろう。
- 冒頭の平安神宮神苑の紅しだれ桜はもう盛りを過ぎたであろうか。あれは季節を合わせて訪れるとまことに見事である。入園料が必要であったから、押すな押すなと言うほどには花見客は来ないし、手入れも行き届いていたように思う。吉永小百合が出た映画「細雪」にもほんの瞬間だったが映し出された。4姉妹の着物姿がイメージ的に重なって、全く美しい画像であった。最近のニュースで醍醐寺のしだれ桜・土牛の桜のクローン苗木が、順調に住友林業の研究所で生育しているという話を知った。もう老木で、接木や挿木あるいは種子よりの繁殖は不可能になっているのを、クローン技術で救ったと言うことらしい。秀吉の醍醐の花見の頃は700本を数えたが、今は20本という。土牛の桜の樹齢は150年と言うから、秀吉の頃と同じ桜は1本もないはずだ。血を伝える桜はあるのだろう。これに祇園公園のしだれ桜を入れて、京都しだれ桜三大名所と思おう。祇園のは代が替わっているが、やはり見事である。
- 周山街道は若狭湾の小浜まで続く。苗子が働く北山杉の産地・北山町は高雄からさらに山奥へ進んだ位置にある。私は紅葉の頃の高雄には何度か来たがその先は知らない。うかつにも北山杉とは京都北方の杉全体を指すのかと思っていた。八瀬大原、鞍馬、貴船の奥にだって杉林が連なっているからである。安い輸入木材が入るようになり、和風建築が減少してゆく中で、産業として生き続けているのだろうか。枝をうち払いうち払い、「切り花」のようにまっすぐに育てられる杉の林は、まだ原形をとどめているのだろうか。志麻の映画で見た皮をむいた丸太の列を今も眺められるのであろうか。西陣織の機の音、加茂川で晒していた友禅染の長い反物、店と住まいが一つになった室町の呉服問屋のたたずまいなど、小説に描かれている風物は、かっては身近な親しい存在であった。今の京都では、ゼロではないにせよ、探訪しないと見つからない風景になっているのではないか。
- 再び志麻の「古都」を思い起こしてみる。千重子の義父・太吉郎を演じたのは宮口精二であった。原作と比較して一番忠実に演じられた人物であったと今思う。千重子への慈しみ、家業の帯の図案がまとまらぬ時の苛立ち、人付き合いが苦手で投げやりとも受け取れる言動など実に見事に演じられている。「新選組!」には悪いが、演出力も含めて「月とすっぽん」という言葉が頭をよぎった。
('04/04/07)
