宮本武蔵
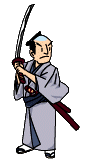
- NHK大河ドラマ「武蔵MUSASHI」は既に33回を終えた。延べ時間にして25時間に近い。あと何回か知らないが、映画が、内田吐夢監督作品のように五部作になっても、せいぜい合わせて10時間なのに対し、圧倒的に長時間のドラマになる。原作にはない登場人物が色んな挿話を埋めてゆくのは新鮮で楽しい。映画では不急の閑種はカットの対象になるのに、創作の小話を入れるのだから色んな武蔵を見てきた目には趣がかわって面白い。新しいキャラクターを創造するには実力のある俳優が必要だが、お篠に宮沢りえ、あかね屋絃三に江守徹、お菊に広末涼子など豪華である。描かれた男女の群像が戦国の自由闊達な雰囲気を出しているし、なによりも彼ら特に女性が従前の作品より自意識を持って行動する姿がいい。剣の対戦相手では、鎖鎌の宍戸梅軒(吉田栄作)かつ(水野美紀)夫妻が土臭い演技で気に入った。 癒しの環境を演じた本阿弥光悦(津川雅彦)と妙秀尼(淡路恵子)、特に後者は秀逸であった。
- NHKはこの大河ドラマに合わせて過去の武蔵映画を何本か放映した。私は昭和29-31年の東宝・稲垣浩監督の三部作を見た。武蔵を三船敏郎、小次郎を鶴田浩二、お通を八千草薫、朱実を岡田茉莉子、第1作の又八を三国連太郎、その他黒沢組として有名な助演陣が良い演技を見せる。新・平家物語とほぼ同じ時期の、正に日本映画黄金期の、充実した作品である。私は第1作を多分封切り時に映画館で見たと思う。
- どの連作でもあらかたそうであるように、稲垣の宮本武蔵でも第1作が一番いい。お通は楚々として初々しく、たおやかで一途である。しかし原作にあるように、芯の強さを秘めて行動する。八千草薫は、かってお通を演じた女優の中では、今も現役で姿を見せる数少ないお人である。当時は清純派で鳴らしていたのではなかったか。乙女の恥じらいとはこんな姿態を指したかと思わせる、化石のようなシーンが幾つかある。封切られた年代の未婚女性の(男から見た?)理想像であろう。関ヶ原の合戦、敗残の中でのお甲、朱実親子との出会い、野盗集団との斬り合い、故郷美作国宮本村における残党狩り、大杉に吊された武蔵などどのシーンがリアルである。三船がもう少し若い時代に作られたならもっと良かった。剣の達人よりなにより先ず生きるのに必死な姿が胸に迫る。
- 第2作の見どころは、副題の通り、一乗寺村の下り松における決闘のシーンである。原作では当主清十郎、弟傳七郎は既に倒されたあとで、一門が甥の源次郎を名目人にして戦いを挑むことになっている。一門が総力戦を挑むお膳立てとしては、こうでなくてはならぬ。武蔵は勝利を決定付けるために、この13、4歳の子供をあえて切る。映画ではこの残酷さを避けたかったのかフィルムの長さの関係か、清十郎との決闘を下り松の決闘に組み込んでしまった。ちょっと惜しい気がする。
- 一乗寺はその頃は廃絶されていた。現在は近くに詩仙堂があるが、江戸時代に入ってからの建立だ。それに今は側を南北に白河通りが走り、すっかり住宅街らしくなった。正月の駅伝ではこの道を通って、ランナーが宝ヶ池の国際会館で折り返すから、全国的に著名になっている。だが決闘の頃は映画のようにわずかの田畑と山林の田舎であったに違いない。存分の戦いに絶好の環境である。演出も、いまどきの怪我人を出さない安全第一の殺陣ではないから、なかなかの迫力である。
- 第3作の値打ちは勿論巌流島における対戦シーンだ。この映画では未明から早朝、朝日が海上に昇り始める頃に決闘の時間を設定した。小次郎が贈られた神仏の護符を焼き捨て、鷹を城に放ち、松明をかざして島を目指す。薄明るくなった頃に武蔵の舟のシルエットが浮かぶ。小次郎は波打ち際に武蔵を釘付けにし浜に上げない。しかし武蔵は朝日が昇ると光を背にすることになり、足場の不利はそのメリットに相殺される。
- 小次郎は巌流島に早く到着しているが、遅れた武蔵を詰ったりしない。原作のそれは技巧に過ぎると常々思っていた。小次郎が長剣・物干竿の鞘を捨てたとき、武蔵は「小次郎つ、負けたり!」などと言わない。原作のこのセリフは実はキザっぽくて嫌いなのである。二人は黙々と穏やかな松林海岸で朝日に赤く染まりながら、あるいはカメラ・アングルによっては影絵のようになって戦い続ける。朝日がこんなに赤いとは長い間感じたことがなかった。昼色近い色に思っているのは人間の目の錯覚である。フィルムの感光薬品は正確に光を捉えているのだ。ラストシーンのこの美しさに、流石、巨匠・稲垣と喝采せずにおれなかった。
- 時代劇を見るときはいつも、製作当時には、主人公が生きた時代にどんな社会通念がまかり通っていたと観念するかが気になる。観客動員のためにも演出姿勢として無視できない因子だからである。武蔵はアウトローの自由人の立場を終生崩さなかった。組織人であれば一所懸命の伝統の下、帰属組織への忠誠心は建前ではなく実質で、組織の利害には命がけであった。卑怯とか未練とか侍の意地とか、そんな倫理感覚が時代のバックボーンになった理由である。一方裏切りなど茶飯事だし、主義主張が合わねば主人を捨てる自由もあった。社会が固定化せず流動的であった特徴で、原作にもよく表現されているから、どの作品でも彼を初めとする男の群像には映像表現に安定感がある。
- 問題は女性像だ。話が飛ぶが、向田邦子原作のテレビドラマ「阿修羅のごとくⅡ」に、母の遺品を整理すると男女がまぐあい合う春画が出てきて、大騒ぎをするシーンがある。娘が処女で嫁ぐのが当たり前であった時代だから、親が性教育資料として手渡したものだったのだろう。私の母の嫁入り道具にはそんなものはなかったようだった。でも木版の「女大学」を持っていた。読んだことはない。しかし、女は従うものという思想で貫かれた教育書で、そこでは「三従の教え」といって、「家にあっては父に従い、嫁しては夫に従い、夫死しては子に従え」と指導したはずだ。今頃そんなことを云ったら半殺しになりそうな文句である。女大学は江戸中期の儒者・貝原益軒の作と伝えられる。封建制度が定着した頃で、体制の中の家族制度の維持強化に役立った。今次大戦に敗れるまで修身教材として使われたという。こんな雰囲気に育った世代が現役の多数派であった時代は昭和40年代までであったろう。稲垣の描く女性像にはその影響が強く感じられる。お通の本位田家に対する服従、廓の女に一旦は落ちぶれた朱実が、「身体は汚れても」と表現するのはいい例である。
- 宮本武蔵が生きた時代は、戦国期最後の関ヶ原合戦から豊臣滅亡の頃あたりだから、本当はさほどに儒教思想が浸透していたはずがない。反面、女は従属的でないだけ自立性を求められていたと思う。女大学は家庭の女の話であるが、遊里の女にしてもより縛られぬ生活をしていたであろう。姫路城に幽閉されるまでの若き武蔵が見せるように、生と死がギリギリに隣り合った境遇で必死に生きたのは、女でも同じだったから、暴力に怯えながらもあらゆる奸智を働かせ巧妙に狡猾に立ち回って、懸命に命を繋ごうとしたに違いない。そう思うと、稲垣のお甲(水戸光子)親子よりMUSASHIのお甲(かたせ梨乃)親子の方が、もっと時代に近い演技である。
- 平凡社の世界大百科事典には宮本武蔵を主人公とする映画は1914年に始まり'73年まで次々に製作されたとある。最後の作品は高橋英樹の武蔵、松坂慶子のお通となっている。吉川英治の小説が完成したのは'39年の昭和14年だ。映画は殆どが吉川武蔵だが、そうでない武蔵も無視できないほどにある。もう見ることが出来ない武蔵もあろうが、そんな場合でも台本ぐらいは残っていよう。武蔵-お通と言う共通項でくくれるという利点があるのだから、89年昔から今日までの、制作時に観念した武蔵存命時代の男女社会通念の変遷を追っかければ、楽に文学部の卒論ぐらいにはなるのではないか。
('03/08/20)
