生体肝移植−京大チームの挑戦−
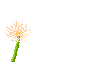
- 5/5の読売の一面トップに京大病院で生体肝移植提供者(ドナー)が死亡したというニュースが載った。既に2300例の実施例があるが、提供者が死んだのはわが国では初めてだそうだ。外国には数例あるという。今回の手術はひどく複雑な移植で、臓器受容者(レシピエント)の娘に先ず父親が肝臓を提供し、8年後その娘が再び容体悪化したために今度は母親が肝臓を提供した。娘は快復した。しかし母親は摘出後肝機能障害を起こし、名大病院の患者より肝臓をドミノ移植されたが快復しなかった。名大を入れると摘出縫合に7回の手術が関係している。5/7の社説では続けて、その後の調査で、母親が非アルコール性脂肪性肝炎で肝臓提供者としては不適であったと判明したと述べた。移植のための切除で30%は残したいところなのに、26%しか残せなかった点を問題にしていた。提供者に危険性の説明が適切に為されていたかも疑っているようだった。父親はこの不幸にもかかわらず外科医に感謝の言葉を述べたという。
- 後藤正治:「生体肝移植−京大チームの挑戦−」、岩波新書、'02はこの事件の前に書かれた本である。記事は医療チーム各員と患者および臓器提供者へのインタビューをもとに書かれている。読売の批判の妥当性を考えるのにもいい材料である。
- 京大チームは生体肝移植の900例を執刀し、手術日には国内外の研修見学医が絶えない。肝移植は世界的には脳死者からの臓器提供の方が圧倒的に多いが、わが国ではその特殊事情からこの本が脱稿された時点で僅か20例で、生体肝の場合の1/100にも達しない。生体肝と脳死肝では移植の困難さにそう大きな差はないという。だが狭義の外科手術としては、後者は全肝移植であるだけ脈管の縫い合わせが楽だそうだ。生体肝の方が、はるかに高い手術技量を要求されると思っていいのだろう。医学界で世界のメッカと言えるのはわが国ではこの分野だけだという。
- わが国における第1例は京大ではなく島根医科大学において執刀されたが、手術としての成功にもかかわらず、年を経ずして患者が死去したためか、あるいは外科チームの層の厚さに問題があったのか、島根医科大学がこの手術のメッカになることはなかった。手術数第2位の信州大学は政治家河野親子の生体肝移植で大変有名になった。HPによれば、河野洋平氏はC型肝炎による肝硬変だったそうである。
- 人間では肝臓が唯一再生できる臓器であると聞いたことがある。生体肝移植はそれを頼りに生きている人から肝を取り出して、病肝の患者に移植する。正常肝はギリギリ20%残せばドナーは生き返れるという。60歳代の人でもドナーになっているとは驚きだった。脈管を挿んで非対称に40%の左葉と60%の右葉に別れる。患者は貰える肝臓は大きいほどいいらしい。患者は年少者ほど助かる確率が高かった。一つは幼少者は生長途上のためか拒絶反応が軽くて済む場合があることだが、その上、子が貰う肝臓は親を初めとする大人のもので大きいからである。ある時期までは大人の生存率は60%台で子供より20%は低かった。従来は左葉移植だけであったのを、大きい右葉にまで可能にしたのはこのチームであった。今では右葉移植が当たり前になりつつあるという。
- ドミノ移植は新技術である。移植後の拒絶反応で再移植をドミノ移植で行ったが、手術の成功にもかかわらず感染による敗血症で亡くなった例が記されている。再移植は5例中3例が不成功という困難な手術らしい。拒絶反応に対して免疫抑制剤を服用するが、普通なら何でもない細菌に対して免疫が利かないための感染症を起こす。エイズで死に至る最大理由がこの免疫不全であることはよく知られている。
- ドナーの危険性については初っ端から何度も触れられている。ドナーは手術によって得るところはなにもない。それだけにドナーの安全が最優先課題になっている。肝動脈への血管造影もやめている。被手術者との面談には2時間は掛ける。さらに2度3度と会う。余人を交えずに会う機会を作る。これは例えば夫に対する妻のように、周囲の圧力でドナーを立候補せざるを得ない立場もあるからだという。生体肝移植は切ない手術なのだ。倫理委員会の委員の内科医が来る。第3者としての公平な立場でのヒヤリングなのだろう。直前にも嫌なら止めてもいいのだよと最後の確認を取る。脂肪肝が手術に向かないと言う認識も何度も出てくる。
- さて今回のドナー死亡事故に戻って考えてみる。京都新聞HPに「移植前の検査で、脂肪肝と診断され、家族はいったん移植をあきらめたが、女性自身が「それでも娘を助けたい」と申し出たという。」と記載されている。この話は読売には出ていなかった。父親は最初のドナーになっているからもう母親しかドナー候補がおらなかったのであろう。先述の通り再移植の死亡率は高いのである。娘は十分成人しているから、脂肪肝ならなおさらに大きく肝臓を切り取らなければ娘を助けることはできない。チームはドナーとレシピエント双方を生かす最大限の切除を冒険したのであろう。
- ドナーの肝臓組織を取る「生検」は行われなかった。ドナーの非アルコール性脂肪性肝炎は分からぬままに手術が進んだ。私の「家庭医学大事典」にも載っていないからかなり特殊な病気らしい。脂肪肝にこの不幸が重なってドナーは死んだと言える。「生検」をやっていたら肝炎が分かり再移植が中止になって、確実、娘の命に障る結果だっただろう。どう転ぼうと、やるせない親子関係である。母親へのドミノ移植がもっと早く実行できたら、あるいは悲劇は避けられたのかもしれない。ギリギリの選択にツキがなかったと思わざるを得ないのではないか。ドナーへの危険性説明が不十分だったという。だが、本書に書かれているインフォームド・コンセプトの手続きは踏まれているはずだ。決心が先に走っている当事者から見れば、きっと通過儀礼の一つとしか感じなかったであろう。危険だと云われても、手術はどれでも危険で素人には危険度の程度の判断が付かないのが普通である。
- 京大チームには他施設では不可能な患者が回されて来るという。メッカとしての宿命である。肝移植としては世界最先発ではなかったのに、ここまでの評価を勝ち得た理由は優れた外科医集団の積年の真摯な努力と云うしかない。先端であればあるほど医療事故に足を取られる。医学上の未解決問題の他に、事あれかしの医療報道という難物が足をすくう。患者を取り違えて健康人の子宮を取り去ったという事故や、未熟医が動脈を切り死亡させたという手合いの事故とはわけが違う。人類未到の困難な手術に挑戦するチームにエールを送るような報道姿勢が望ましい。あの読売の報道は、一般人には「京大チームはしくじりよった」と受け取られている。廻りから聞えてくる感想である。
('03/05/18)
