パロマーの巨人望遠鏡
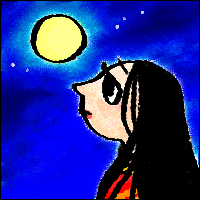
- 今ではハワイのマウナケア山に建てた、わが国国立天文台の「すばる」が世界一(323インチ)だが、それまでは表題の反射望遠鏡が世界一(200インチ)であった。60年以上の長い期間、世界一であり続けた大天文台がいかにして生まれたか。巨大科学は卓越した指導者の熱意のもとに、科学者、技術者は勿論財界人果ては一般人までが結集して初めて可能である。D.O.ウッドベリー:「パロマーの巨人望遠鏡(上)」、関、湯澤、成相訳、岩波文庫、'02を読んでの総括的感想である。
- まずアメリカの大天文台が民間の寄付で建造されていることに驚く。パロマーはロックフェラー財団、パロマーが出来るまでは世界一であったウィルソンはカーネギー財団である。わが国の財界人が数々の文化貢献行為を行って来たことはよく知っているが、大体がハコモノ寄贈コレクション寄贈で、サイエンスの分野を特定し、その先駆的な進歩に貢献した事例は知らない。財力の差は勿論ある。しかし、天文物理学というこれからの学問に思い切った投資を行う眼力に、尋常でないアメリカの馬力と水準の高さを感じる。
- 技術的に最も詳しく描かれているのは、反射鏡の製作に纏わる苦心談である。大きな反射鏡は明るい視野と良い分解能を与える。分解能とは2つの星を分離し見分けることが出来る最小角度のことで、レンズ直径に逆比例する。理由は光の回折である(吉田卯三郎:「三訂 物理学(下)」、三省堂、'47)。地上の観測には限界があるが、その限度に達するまで天文学者は大きな望遠鏡を要求して止まない。だが、小さな反射鏡が出来たからと云って、大きな反射鏡がすぐ出来るわけではない。大きくすると「何が起こるかわからない」。未知の技術的因子が新しく登場し、行く手を阻む。それに観測者は、膨張係数が低い材料で反射鏡を造りたい。大きな反射鏡では、観測時に鏡面を安定させたいために、熱膨張を極端に嫌うのであある。製作時の熱歪み回避のためにも、それは必要である。
- そこで最初に取り上げられたのが溶融石英であった。石英製品は電気屋の独壇場であった。請け負ったGE社の技術陣は当代随一のスタッフを集めて全社的にとりくむが、2フィート直径の反射鏡までしか成功しなかった。理事会は、パイレックス・ガラスで次の開発に取り組む決定をする。パイレックスは担当するコーニング・ガラス社の商標で、彼らにとっては手慣れた材料という利点がある。熱膨張率は石英よりはやや大きいが、普通ガラスよりは遙かに低く、軟化点も石英よりは低く、作業性もまずまずである。
- 彼らはスーパー・パイレックスという一段と熱膨張率の低い材料を開発した。だが、小さい試作品段階ではよかったが、直径30インチぐらいから例のスケール・アップ問題が頭をもたげ始めた。重量を減らすために、同じ材料のリブをつけた円盤構造にする。つまり強度保持目的以外の肉は殺いだ構造である。勢い複雑な形状になるが、その鋳型の耐熱材料と構造が難しいし、まんべんに、溶けたガラスを流し込んだ上、ゆっくりゆっくり何ヶ月も掛けて焼き鈍さねばならない。焼き鈍しは、装置が巨大になるほど、成否を握る重大問題になる。NHK番組「日本人の質問」において、水族館の透明壁(多分poly-MMA板)の最終工程が出題されていた。「海の日」に因んだ質問であったと思う。だれも焼き鈍しを言い当てないのでガッカリした。チェルノブイリ事故と同型の旧ソ連原子炉でも、焼き鈍しの不完全さが問題視されている。
- 200インチの反射鏡用ガラス円盤の鋳込みは、反射鏡に仕上がるまでにまだ長い工程が残っており、望遠鏡は尚先、大天文台はそのまた先という位置付けであったのに、大勢の見学者を呼び込んだという。科学者、報道陣に一般参観者が合計1万人もいたという。70年も昔の出来事だ。アメリカ人の凄さを感じる。この鋳込み円盤は参考品にしか成らなかった。2回目の円盤の成功で反射鏡は現実味を帯びる。上巻はここで終わっている。円盤の反射鏡化は下巻に記されるのであろうが、100インチ反射鏡の場合、それを磨いた科学者と技術員は、あまりに長期に及ぶ精神集中のため精神異常をきたし、完成と同時に天文台から姿を消したとある。世界の先端を走るものの緊張ぶりは、私も少しは経験があるのでよく分かる。
- 巨人望遠鏡でどんな成果が生み出されたか。200インチの場合は下巻に出てくるのだろう。ここではウィルソン天文台の成果を総師ヘールを中心に眺めてみよう。太陽の黒点の研究が異彩を放っている。先ず酸化チタンの分子スペクトルの存在から、黒点が、元素解離まで行かない低温であることを見出した。黒点では荷電粒子が渦巻いている。その事実を水素の赤色光のゼーマン分裂から証明する。当時やっと濃い赤色に感じる写真乾板が発明されたばかりであった。スペクトルの研究にはローランドの回折格子が利用された。分散能で格段に勝るこの回折格子なしには研究は進まなかった。この技術も生まれて間もなしであった。ゼーマンにせよローランドにせよ、大研究には周辺に画期的な発見発明が、不思議に同時多発するものだ。同僚達の研究には恒星の直径測定、ケフェウス変光星の発見と距離測定への応用などがある。どういう原理なのかはっきりとはわからない。ビッグ・バン論に繋がるハッブルの法則もこの頃の発見だった。
- ウィルソン天文台の前はヤーキス天文台である。ヘールは弱冠29歳で初代台長に就任したという。わが国では起こり得ないことだ。日本科学未来館と言う昨年開館した壮大な博物館がある。館長はあの宇宙飛行士の毛利衛さんだ。例外的に若い館長さんだと思ったら、その上に総館長として元東大総長吉川弘之氏が納まっていると言う(小泉成史:「おススメ博物館」、文春新書、'02)。ヤーキスには総台長は記録されていない。このヤーキスは、そこの大屈折望遠鏡を寄付した財界人の名前だそうだ。ヘールは太陽のスペクトル研究を推進し、天文学と分光学を結ぶ天文物理学雑誌を発刊、世界の権威誌に育てた。台員たちも多くの仕事を残した。数多くはないが、地球の公転直径から星との距離が定められた。スペクトルのドップラー効果から地球と星の相対速度が調べられた。スペクトルから恒星の実際の光度を知る方法(私の物理学の知識ではどのような原理かよく分からない)は、後日、視差では解らぬほどに遠い、地球と恒星の距離を測るのに利用される。
- 私は「すばる」の今後の成果に期待したい。しかし、地上の大望遠鏡による成果は、もう200インチ望遠鏡で、あらかた刈り取られているのではないかとも危惧する。今後の大発見は、現にそうであるが、探索衛星だとか衛星望遠鏡であるとか、技術的に全く違う、「地上」をブレークスルーした、異なる原理の観測設備によって行われるだろう。「すばる」は過去の延長をなぞっただけと云える。例えば、当時はまだ今日ほど騒がれていなかった「生命科学」に、「すばる」などうち捨てて、失敗覚悟で飛び込むような研究戦略がなぜ取れなかったのだろう。私はあの頃、新入社員(東尾君、彼の名誉のために)が「これからは生命科学だ」と言ったのを憶えている。残念ながら私も凡庸の化学者だった。化学大発見時代の余光がまだ輝いていて、目を振り向けることが出来なかった。超一流のリーダーを見つけて任せるシステムは、どうすれば機能するのか。常に頭から去らない問題である。
('02/07/27)
