日蝕
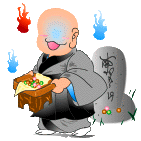
- 「芥川賞全集 第18巻」、文藝春秋社('02)の中の平野啓一郎:「日蝕」('98)を読む。平野は今はこの賞の選考委員だという。新潮に発表された116pの中編小説で、在学(京大法)中に受賞した処女作。選評を読むと、選考委員会でははじめから抜き出て評判が高かったと判る。
- 漢文学に造詣の深い明治の文豪のような文体で書かれている。ヨーロッパの地名が漢字で記述されている。パリが巴里ではなく巴黎となっているが、これは初めてお目にかかる字体だ。Copilotに聞くと中国表現だと答えた。パリ大学で神学士号を得たばかりの若者ニコラが、異教であるギリシャ哲学の克服を目指して、南仏のリヨンから北伊のフィレンツェを目指す。イタリアではルネッサンス運動が勢いを増し、哲学はもちろん宗教、文学、美術芸術の文化全域に「異教」文化見直しが進もうとしている。15世紀後半。日本の明治維新において西洋文明に対峙した文人たちの文体を模して、キリスト教の世界に流れ込む、ギリシャ文明の香るルネッサンスを知ろうとするニコラを描く。なかなか凝っている。
- ニコラの目的に対してフィレンツェ行きを勧めたのはリヨンの司祭であった。本質をルネッサンスの本場で学べと云うことだった。そしてその前にリヨン近郊の錬金術師を訪問するよう紹介状を書く。彼の自然学を学べと云うことだった。このHPの「東欧旅行-その4 チェコ」('02)に、チェコ・プラハの黄金の小路を歩き、錬金術師の家屋を見た記事が出ている。金を生み出すことはできなかったが、錬金術は現代化学の源流となった。異教的な秘術を、魔術呪術と切り捨てずに、自然学の萌芽と見た司教は立派だった。
- ニコラが貰った紹介状は、錬金術師のいる郊外の村の司教宛であった。錬金術は微妙な立ち位置にあるから、リオンの司祭は筋を通したのである。当時の南仏の村落の生活状態ことに宗教者の実体を活写してある。清貧を貫くドミニカ派の僧ジャックが熱烈に辻説法を試みている。鎌倉時代の日蓮上人とか戦国期の本願寺派の僧を思い浮かべたらよいのか。農民は貧しい。農耕地には三圃制が残っており、土壁藁葺きの粗末な家に居住する。その村人たちは迷信深く信心深い。取り囲んで聴き入っている。
- ニコラも教会では改革派と言えるドミニカ派で、托鉢と司牧の義務を免除された学僧だとある。トランプ大統領が看破するまでもなく、大学には進歩思想が浸透しやすい。それに学僧はジャックらの布教現場の僧とは感覚の違いがあるようだ。立派な石造りのカトリック教会に納まっている司教、助祭の酒食女色にただれた姿は対称的。司教らは一括してドミニカ派を乞食坊主と陰で嘲る。とにかくどの話も私にとっては異次元で、例えば鞦韆(ブランコ~俳句の季語にあるそうだ)とか股栗(恐怖と驚愕のさま)といった難しい漢語が、ばんばん飛び交うのに、その先はその先はという読書欲が優先する書きぶりだ。
- 錬金術はアラビアが源流だ。Copilotによると「中世ヨーロッパでは、12世紀頃にアラビア語の錬金術書がラテン語に翻訳され、学者たちの間で研究が進みました。特に「12世紀ルネサンス」と呼ばれる時期に、イスラム世界の科学や哲学がヨーロッパに流入し、錬金術もその一部として受け入れられました。この流れの中で、錬金術は単なる金属変成の技術ではなく、哲学や医学とも結びつき、知識人の間で重要な学問として確立されました。」という。ピエェルの書斎には関連書籍が並び、その道を究めようとする道士のような、人を容易に寄せ付けない風貌の男だった。
- ピエェルの理論が出ている。彼は神の創った世界の秩序を信じるカトリック教徒だ。その前提で「有らゆる金属の裡に黄金の実体的形相の生ずる可能性」を信じていたとある。錬金術師は、賢者の石(Wikipediaには「中世ヨーロッパの錬金術師が、鉛などの卑金属を金に変える際の触媒となると考えた霊薬である。」と書いてある。)を、すなわち物質に顕現した存在そのものを手中に収め、それを肆(ほしいまま)に用いむとするものである。3pほどに亘って解説される論理だが、とうてい現在の読者(私も)は理解できない。作家だって判って書いているのでは無かろう、だとすると古文献からの引用だろうか。ニコラは理屈はともかく「絶望的な試み」と考える外無かったとあるので安堵する。ここで「お説ごもっとも」とやられては、あとが現代の小説にならない。
- ニコラはそれから何度もピエェルをおとなう。周囲の評判も耳に入ってくる。村は殆どが都会の不在地主の下の貧しい小作人と云った伝統社会だ。ピエェルに対しては悪評紛々で、身のまわりの世話をする、手間賃稼ぎの鍛冶屋(実はのちに告訴人になる)以外は誰も寄り付かないようだ。その鍛冶屋も村では下層扱いだ。読み終えたので先に云っておくが、本小説のフィレンツェでのお話はごく僅かだ。ニコラは錬金術者の不可思議な世界に魅入られる。そしてピエェルが魔女として捕らえられる直前まで付き合う話になっている。ニコラは、村を立ち去ってから何年も経て、彼が獄死したことを知る。私は作者のルネッサンス論(そういえば本書には一度もルネッサンスという言葉は出てこなかった)が、若き進歩的神学士の口を通して語られるのだろうと期待したのに、残念だった。
- NHKプラスで「「シリーズ 人体・特別版 神秘の巨大ネットワーク(5)“脳”ひらめきと記憶の謎」」という番組を見た。自然散策などで、平素と違った刺激が与えられると、脳は閃くことがあるという。ピエェルの日常生活に、村人が不気味がって近寄らぬ暗黒の森に夕方紛れ込むという習性にニコラが注目する。私は、てっきり、行き詰まっている錬金術の第3(最終)段階へ、開眼するための合理的といえるピエェルの行動だと「現代脳科学」的に考えた。でもそれは、開眼手段だったかも知れぬが、全くの妖術的魔術的幻惑的行動だった。奥深くの鍾乳洞窟での両性具有者(アンドロギュノス)との密な情交換であった。両性具有者とは何かのニコラの観察が詳しく述べられている。私は全く知らない性だ、なんともおぞましい記述だった。
- 両性具有者についてCopilotに聞くと、「社会的な扱いについては、時代や地域によって異なりますが、古代ギリシャではアンドロギュノス的な存在が神話の中で肯定的に描かれる一方で、キリスト教の影響が強まる中世以降は、両性具有的な存在が異端視されることもありました。しかし、近代になると、性の多様性に対する理解が進み、アンドロギュノスという概念が再評価されるようになりました。」と答えた。我が国では、認識はあったろうが、隠し事秘め事として世に出ることはなかったのではないか。
- 村は天候不順に不作が続き不穏な雰囲気にある。両性具有者が突発的事件の犯人~魔女に仕立てられる。ジャックが異端審議官になり、容赦のない拷問(容疑者は骨は折られ爪は剥がされと残酷極まりない半死人状態になっていたとある)で魔女焚刑という判決を下す。火炙りの準備が進められる。集まった村民の前で、ジャックが長々と判決に至った経緯を読み上げる。我が国の歴史には出てこない、ギリシャ・ローマ以来の西洋文明の基本形だ。炎が天空を焦がしたとき日蝕が起こる、人々は男女のとてつもない巨人が現れたと感じ驚愕する。「日蝕」のもたらす光と影だったと私は解釈した。
- 陰ではピエェルも魔女という風評が強まっていた。魔女は女に限らない。ジャックは彼との交流を重ねるニコラに警告を発し立ち去るよう要求した。ピエェルが逮捕されたのはニコラがフィレンツェへ去った後だった。
('25/5/19)
