おろしや国酔夢譚
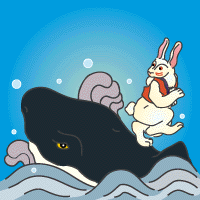
- 井上靖:「新装版 おろしや国酔夢譚」、文春文庫('14)を読む。約400pの8章立て。'66年から連載が始まった作品という。すでに世に著名な作品だが、これまでに読む機会がなかった。たまたま毎日新聞の「なつかしい一冊」に出たのと、NHKの「ブラタモリ 伊勢神宮への旅・第三夜」で白子宿が紹介されたのが読む契機となった。江戸期の白子宿は紀州藩の飛び地で巨大港が整備され、往来と物流の中心地として栄えていた。この小説の中心人物・大黒屋光太夫は史実の人で、遭難廻船の船頭であった。その出帆(1782.12)港が伊勢白子の浦だった。
- 本小説の一章には難破船内の描写がある。で、つい脳裏の中の映像を検索する気になった。私は青森の「みちのく北方漁業博物館」で係船された復元千石船をみたことがある、船箪笥などの調度品も展示されてあった(「大人の休日倶楽部パス(東北スペシャル)」('12))。和船内の生活はTVドラマでいろいろ目にしたが、NHKの「お登勢」('01)の記憶が鮮明だ、最後は北海道へ移住させられる船旅だった(「徳島県立博物館」('02))。NHK大河ドラマ「獅子の時代」では、北海道からの船内の様子が出ていた。
- 白子の浦を全17名で出航してから漂流8ヶ月。その間の犠牲は1名。少なかったのは漂流が厳寒にはならない海域だったのと、大量のコメを積んでいたのが幸いしたようだ。アリューシャン列島の中央に近いアムチトカ島に無事上陸できた。すでにロシアの商人の手先が基地を設けており、原住民を指揮して海獣を獲らせ買い入れていた。すぐ彼らが難破船一行の身柄預かり人となる。ロシアへの漂流はそれまでに既に5回あった。台湾では、先住民による琉球遭難民54名殺戮事件があった(「台湾の歴史」('25))。何が全員無事と全員殺戮の差を生んだか、興味深い。
- 冬に入り、6名物故。原住民上がりの牧師の祈りを受ける。全員仏教徒だったと思うが、本書を通して讀経とか仏式儀式の話はあまり出てこない。ロシア人の猟を手助けをして暮らす。また1人が他界。4年経って、商人手先の交替船がやってきた。しかし難破。ロシア人も日本人も力を合わせて新船を造り、ベーリング海を西へ航行、1ヶ月あまりでカムチャッカ半島に到着。
- 私はカムチャッカ半島のペトロパブロフスク・カムチャッキーに寄港したことがある(「北海道・カムチャッカ・クルーズ」('06)、「千島~カムチャッカ」('06))。船中で講釈師・旭堂南左衛門の「音楽絵巻「ある日の大黒屋光大夫」」(原作:井上靖、作:中野順哉)を聞いたと書いてある。船内放送で、アッツ島で玉砕した戦士を悼んで黙祷したように思う。「刃凍る北海の」で始まり「山崎大佐指揮を執る(繰り返し)」で最初の節が終わった軍歌を歌える世代が乗船客に多かったのだろう。寄港した街は味気ない場所だった。カムチャッカはより大陸性の気候だったのだろう、一行はその冬に3人を壊血病で亡くす。厳冬の厳しい食糧事情で、ビタミンCがとれなかったのだ。エスキモー(イヌイット)は同じような食糧事情だが壊血病にかからない。海獣生肉、生魚肉には微量のビタミンCがあって、生食の彼らは壊血病を免れているという。光太夫は土地の長官を通じてロシア国の文化を信頼するようになる。
- 「ロシア領になる前のシベリア」('07)にはロシア化前の原住民の消息を伝える。本小説には方々に被支配民である原住民の生活が出てくる。彼らはロシア人が現れるまではかなりの人口だったようだが、今はその文化もろともに逼塞している。カムチャッカでの原住民取扱は酷いもので、奴隷化された方が自由民よりも多かったと歴史は伝えているそうだ。ロシア政府のシベリア経営は毛皮貢税徴収を主眼としていた。その財政に占める割合は大きかったそうだ。乱獲がみるみる毛皮の数を減らしていった様子が数字で示されている。毛皮動物は原住民の生きるための資源だったろうから、人口減少に歯止めが効かなくなったのではないか。アメリカ・インディアンの人口減少(「アメリカ先住民激減の歴史」('16))でもそうだが、「文明の衝突」などと済ましておられぬ暴虐を感じる。
- 物資集散地オホーツクはカムチャッカ半島の対岸の地で、そこまでは船旅、そこから冬に入るというのに、ヤクーツクに原始林を行く2ヶ月の旅が待っていた。ヤクーツクは知事駐在の中心地で、木造の砦を囲む数百の家屋があった。極寒の地であった。鼻や指など露出部が凍傷で欠けた人が目撃されるようになる。宿舎をあてがわれ、ここでも次の旅費の支給を受ける。1ヶ月のちに、付き添い役人と共にイルクーツクに向けて雪橇で出発。ヤクーツクからイルツークまでは駅逓が各所にあって、橇が到着すると、馬の取り替えが行われ、迅速に出発できる制度が整備されていた。モスクワ(旧首府)からペテルブルク(新首府)に繋がるようなメインロードになると、橇1台は馬8頭を使い、山路ではその倍ときには3倍を使うという堂々たる交通システムであった。イルクーツクあたりでは駅逓機能の維持はヤクート人の役目で、彼らにとっては重い責務だった。
- イルクーツクはアンガラ川の始点にあり、そこからバイカル湖々水が流れ出る。北極海に流れ込む大河の氷結や解氷の模様は、TV番組で紹介されたことがある。その荒々しい情景を描写してある。一行が幾多の困難を乗り越えて州都に入ったのは、帰国願いを聞き届けて貰うためであったが、埒のあかぬ役人仕事が待ち構えていた。半年待ち、また半年待ちしてやっと届いた中央からの返答は、ロシアに滞在して日本語学校の教鞭を執るべしであった。過去の日本難民を教師に何代も続いていた学校だったが、今は教師不在で閉鎖状態だった。ロシアは、遠く離れた地図上でしか認識されていない国の言葉を習得させる学校を、何年も官が経営していた。長年の東進南下の経験がそうさせたのだろうが、それにしても東進南下の侵攻が、民族の本能になっていると感じさせる事実である。光太夫が拒絶すると、それまでは続けられていた官からの生活金給付が打ち切りになった。
- 光太夫は諦めなかった。彼は中央とのツテを求めた。彼の見識とか人柄とかを褒める旅行家レセップスの記録が残っているという。役人ながら研究家肌探検家肌の人物ラックスマンと交流できるようになり、その従者のような資格で新首府へ随行する機会を得る。6年あまりで光太夫の部下は既に5名になっていた。さらにイルクーツク滞在中に1名を亡くし、1名は片足切断、1名は病床に伏せるという状況だった。その2人はロシア正教に改宗し、日本語学校教師の道を選ぶという。オーロラを見た。光太夫は介護に健康な2人を残し、単独随行の道を選ぶ。イルクーツクからはますます街はロシア風になって行く。既述の通りの駅馬車が旅客を効率よく迅速に運ぶので、1791年の厳冬の中のこの長大な距離をわずか1ヶ月ほどで走り終える。まともな宿泊はモスクワでだけだったとある。
- 露土戦争たけなわだった。トルコが誇るイズマイル要塞はその年に陥落し、ムスリムの男女老弱を問わぬ大虐殺が行われた。イズマイルはドナウ・デルタにあり、現在はウクライナの地域最大の港である。女帝エカチェリーナ二世は王城ペテルブルクにはなくツァールスコエ・セロ(デジタル大辞泉:ロシア連邦北西部、レニングラード州の都市サンクトペテルブルグの南約25キロメートルにある、かつてのロシア皇帝の避暑地。ロシア語で「皇帝の村」を意味し、エカチェリーナ宮殿、アレクサンドル宮殿などがある。)にいた。拝謁が叶う。女帝は2回に亘り時間をかけて漂流事情を問い質し、深い同情を示した。光太夫一行はこれまでにもほうぼうで貴族や高級官吏、あるいは豪商などの館に招かれては漂流談義を行ってきた。
- さて光太夫は数々の贈り物を頂戴し、月々の給付金まで与えられることになる。女帝は難民送還の指令を出していた。オホーツクに大船の建造が行われていた。かねてより鎖国解放による貿易国交ルート樹立がロシアの長期戦略にあったようだ。アメリカのようないきなりの砲艦外交策は選択されておらず、まずは国書を持参して門を叩くことになる。光太夫らは絶好の手土産という位置にあった。
- 択捉、国後の海峡を抜け西別を経て根室で停船する。アイヌ部落の中に松前藩の屯所があり、海路を函館へ回る。そこから松前までは国使来迎という形で、大騒動になる。450人からの行列を組み、80kmほどを3泊4日という時間をかけて松前まで行く。槍鉄砲弓。「国使」殿は御駕籠。警護のトップは馬。要するに大名行列で、それも20万石以上の格式だ。松前藩は、他の藩と異なり、アイヌとの交易収入が主だから正式な石高がないが、目の玉が飛び出るほどの出費だったろう。接待の模様も記録に残っているという。ありとあらゆる馳走が並んだ。難儀なお客は歓待に次ぐ歓待をして、穏やかに引き取って貰うという戦術だ。鎖国の国是を松前藩1藩で勝手に破ることなどできぬ相談であった。幕吏がきて国交は長崎が窓口だとさとし、長崎への紹介状を手渡し、けりを付けた。国書は受け取らなかったが私的に写しが渡された。窓口論争で多大の日時を費やした国使はこれで引き上げ、女帝からは勲章授与の評価を受けた。乗組員はついに日本国に一度も上陸することができなかった。
- 10年ぶりで一行は故国の地を踏んだ。でも故国は夢に見た懐かしの故国ではなかった。学び取り影響を受けた進取的なロシア気質と何かしっくり行かぬ。光太夫一行は根室で1人を亡くし2人になっていた。彼も壊血病であった。2人はそれからは役人監視下で江戸での取り調べに向かう。最後は御簾中の将軍が列席した幕府要人による尋問だった。2人は要望に従ってロシア礼服で登場した。珍問答が繰り返されたらしい。光太夫はお上の立場を配慮した答弁を繰り返し、日本批判の匂いを一切隠して身の安全を図っている。国禁を犯した立場を怖れていた。その後も光太夫らは故郷には戻れず、江戸で殆どを軟禁状態で一生を過ごした。兄が伊勢から尋ねてきても、面会では役人が立ち会った。貴重な外国知識は、蘭学者の聞き取り本となって残ったが、影響力のほどは不明だ。
- ロシアでは日本の国情や文化に対する知識が広くオープンになっていた。光太夫らの知識の拡散が怖れられたのと好対照である。どちらがお国のためか明らかだ。家康の鎖国は、250年の徳川政権の安泰とそれによる国内平和維持に貢献したが、国家の進歩には有害であった。
('25/4/16)
