歴史学はこう考える
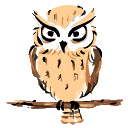
- 松沢裕作:「歴史はこう考える」、ちくま新書(2024)を読む。270pの6章立て。目次を見ると歴史学の歴史という印象である。マルクス主義的経済史という節が目に入る。著者は慶応大経済学部教授。私の経済学はマルクス主義者・大内兵衛の「経済学」(岩波全書)から始まった。そこだけは読んでみようと思ったのが、本書を取り上げたきっかけである。
- 第1章「歴史家にとって「史料」とは何か」。
- 歴史を歴史学に持ち上げたのはランケ(1795~1886)であった。歴史を研究することと、歴史を何かの目的に使うことの間に一線を引いた。できるだけ信頼できる記録を使って歴史を書く。目的(多くは政治目的)はなくてよい。彼の実証主義は歴史の法則性など素直に肯定しない。近々の世界情勢を見ると、人間社会の複雑怪奇性は、とてもじゃないが大内兵衛流のような一刀両断の法則など存在しえないと思わせる。最近はやりの深層学習のAIからの類推に過ぎないが、私は、色んな法則ライクな擬似?原理のネットワークが働いて、何とはなしにその次が決まるのが人の世だと思っている。マルクスの「価値は労働から生まれる」もその中の重要な駆動力の一つだ。
- 史料に目的はつきものかと云えばほぼイエスだろう。先日「月ぞ流るる」を上梓した。国選史に対してであるが、「史実ただし覇者に偏向の史書」「覇道の正当性を記すだけの史書」と書き、対して赤染衛門の「栄花物語」という歴史物語が実体を意図するものと強調している。結果的には道長家系のための道長ヨイショになっているらしいが、宮廷人の肉付け部分には、学に重宝な史料価値が認められるようだ。本書には我が国の歴史学の流れは出てこないが、江戸期に開花した国学には、歴史を俎上にした科学の芽生えが感じられる。
- 第2章「史料はどのように読めているか」。
- 明治期の「逓信次官照会」と、北条泰時の「御成敗式目」の読みこなしについて考察してある。前者は逓信省の非正規雇用の女子事務員のうち優秀なのを、判任官(ノンキャリアの一般職国家公務員)に引き上げたいがどうかと、内閣書記官長(今の内閣官房長官)に照会した史料だ。官吏は男性に限られていた時代だが、能力では男を凌駕する女性が多いことに目をつけている。後者は阿仏尼(「十六夜日記」の作者)60才の鎌倉下向訴訟で有名だ。彼女の死後だが、彼女の勝訴になった。時代祭でも彼女の旅姿を見ることができる。武家の法度には相続変更に対する規定があり、明記されていない公家法より、幕府の法度に判断を委ねたのであった。彼女は公家出身である。
- 前者の内容は1世紀半のちの今日でもほぼ正確に理解できる。人情や常識は今とは異なろうが、法体系官僚体系などは今日に継承され、何よりも史料豊富である。後者は、 日本最初の武家法で、鎌倉幕府を開いた源頼朝以来の先例と道理(武家社会の習慣や実態~常識)をもとに制定された。常識は同じ時代でも地域や立場で微妙に違っていようし、時代が変わると変遷する。今となっては、背景が出所あるいは歴史により、しっかり判る律令~公家法朝廷法の方が、読み辛くとも明確に内容が把握できる。
- 脱線だが、鎌倉幕府が倒れてからもこの式目の精神は明治まで受け継がれた。Wikipediaを見ると「御成敗式目は女性が御家人となることを認めており、この規定によって戦国時代には女性の城主が存在し、井伊谷城主の井伊直虎、岩村城主のおつやの方、立花城主の立花誾千代、淀城主の淀殿などが知られる。」とある。NHK大河ドラマ:「おんな城主 直虎」は戦国時代の虚構ぐらいに思っていたが、その女城主が実在した人物であったとは驚いた。
- 第4章「論文はどのように組み立てられているか(2)-経済史の論文の例」。
- 取り上げられた論文は、今日でも参照されることがある名著だという、石井寛治:「座繰(ざぐり)製糸業の発展過程-日本産業革命の一断面」、社会経済史学28-6(1963)である。'50~'70年にかけては日本経済史の標準的研究方法はマルクス経済学準拠だったとある。石井もその範疇にあった。しかし彼はこの論文ではマルクス流の歴史の必然を問うたのではなく、座繰りの手繰り製糸業のマニュファクチュア的解釈が誠か嘘かを実証する研究をしたのであった。
- 私が初めて読んだ「経済学」(1951)は、たまたまそれが本屋の書棚で部外者に手頃と思える冊子であったからだったが、それがマルクス主義者の著作だった背景には、そんな事情があったのかと今になって思う。私は理系でも工学系。量子力学には議論紛々だったが、私が扱う工学の力学は完璧に統一された理論が支配していた。その流れで、学という以上は、教養レベルの経済学なら、どの本も似たり寄ったりで、土台が揺れ動くことはあるまいとぐらいに思っていた。経済学は立場が違えば土台がころりと変わるとサジェストしてくれる人はおらなんだ。
- 養蚕業、製糸業の発達はあちこちの地域博物館(「蚕糸王国・岡谷」('03)、「産業博物館」('08)、「高崎日帰り観光」('11))で見学した。先日上梓したばかりの「焼き芋とドーナツ」('24)でも製糸業の女工を取り上げている。小学生の頃は西陣の近くだった。糸巻き機がたくさん動く家屋を覚えている。多分養蚕の生臭い匂いを知っている最後の世代だろうとも思う。
- 石井は、江原家に残った天原社(1879~1906年)史料を解析した。素封家には輝いた時代の歴史資料を大切に保存しているものが多い。家自身が博物館になって、その家を中心にした地域の歴史を伝えているものもある。最近では、私は長岡市の旧機那サフラン酒本舗(「大人の休日パス東日本SPの旅」('23))を見ている。養命酒と覇を競ったサフラン酒の醸造所兼住居跡だった。
- マニュファクチュアとは、資本が用意した施設や材料のある工場で、賃金労働者多数が大規模の、未だ手工業レベルの生産をするシステムといった印象の言葉だ。石井は生産設備を分析して、糸をとる作業自体は従来の農村副業としての屋内工業的小生産者の業務で、天原社は彼らの小枠に巻き取られた糸を「改良」揚げ返し機で大枠に巻き返すだけ、つまり座繰は昔のまんまで、座繰の大工場など存在しなかったと判定する。従来の誤認は、統計資料の上っ面を読んだだけだったためだと判る。やがて器械製糸工場に後れをとり閉鎖になる。
- 電子立国日本とNHKが唱った時代が、あっという間に中国や韓国に打ちのめされた。日本の有頂天(高集積回路メモリーの工業的成功)は「日本海軍の光学技術」と「微小粒子のIC収率に対する影響の発見と対策の成功」のおかげだった。IT産業会社のオリジナルは生産現場環境のダストの悪影響の発見だけだったわけで、それも詳しく見ると除去装置も分析法も外部依存の技術に過ぎなかった。座繰大工場が幻だったという話と何か共通した面を感じるがいかが。
- その「電子立国日本」ではNECの技術者が、電卓用ではあったが、世界初のCPU作製に成功したと報じていた。NECのPCは自社製CPU時代が長かったが、今はインテルかAMD製だ。CPUもGPUも世界のシェアの殆どはアメリカに行ってしまった。関連産業、周辺産業の急速な発展に、NEC程度の規模の組織では、資本的にも技術的にも、対応しきれなかった。
- 高集積回路メモリーの成功が仇になって、未来への危険な投資を忌避させたとも思う。今になって政府がIT産業に大型投資を試みているが、泥棒に追銭的印象で、先行投資しなかったツケは取り戻せそうにない。「電子立国日本」が生きていた時代に、なぜアメリカに対抗できるほどの国策国営会社を打ち出さなかったか、私は現役で会社生活を送っていた頃、「何かやらかしてみろ、ものによってはフォローしてやる」と云った上司の発言が、我が国IT産業の今日と重なる。著者の目論見は歴史学が科学であると論証することにもある。でも理系の私にはいちいち当然のお話で面白くもおかしくもない。しかし例題にでている論文の内容には興味を惹かれるので、ついつい現代の問題への応用に視線が移ってしまう。
- 第3章「論文はどのように組み立てられているか(1)-政治史の論文の例」では、高橋秀直:「征韓論政変の政治過程」、史林(1993)が取り上げられている。第4章の「天原社」が店を閉じた主因は繭市場の動向だったのに対し、征韓論の行方を決めたのは西郷隆盛の政界における立場だった。社会改革期の政治家のリーダーシップの大きさを論題にしている。「一般的にマルクス主義的歴史理解では、経済的な要因が重視され、政治や法律、思想と言った領域は、経済的な要因によって影響を受ける対象として考えられます。経済を「土台」、政治や法律などを「上部構造」と呼ぶこともありました。」と出ている。最初が大内兵衛本だったせいか、私の社会を見る目もその流れのようだ。ひよこじゃないが、大内さんを「刷り込」まれているらしい。
- 第5章「論文はどのように組み立てられているか(3)-社会史の論文の例」には、鶴巻孝雄:「民衆運動の社会的願望」、(1992)を取り上げる。政府の支出削減による深刻な不景気(西南戦争による戦費調達で生じたインフレーションを解消しようと、大蔵卿松方正義が1881年(明治14年)より行った、デフレーション誘導の財政政策による)~松方デフレーションで立ち上がった民衆運動を取り上げる。研究対象は武相地域の質地騒動。江戸時代は、原則として農民が質入れした田畑を質流れにすることは禁止されていた。しかしその禁令が緩和されたことがあり、元に復する段(緩和取りやめ)になって、取られた農民が取り返そうと騒動を起こした。NHK大河ドラマ「獅子の時代」の最後を飾った秩父事件は近隣の騒動だった。
- 第6章「上からの近代・下からの近代―「歴史についての考え方」の一例」。
- 「焼き芋とドーナツ」('24)には、日米の女性解放史を階級闘争的に記述した湯沢範子の力作を紹介した。マルクス主義にジェンダーという視点が入り、地域の発展段階という視点が入っている。本章に「ジェンダーと階級」という項があって、「男性の」労働者階級に偏った捉え方に、女を登場させる意義を論じてある。その次の「近代さえもきていない?」という項は、まさに日本の、非近代と近代のごっちゃまぜ資本主義体制を論じており、その延長に「植民地近代化論」が見られるとある。生活感覚とか幸福感とかも含め、人間の持つゼニ以外の価値感をマルクスの論理に被せるような方向に歴史学は進んで行くのであろう。
('24/12/20)
