焼き芋とドーナツ
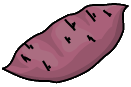
- 湯沢範子:「焼き芋とドーナツ~日米シスターフッド交流秘史」、角川書店(2023)を読む。コトバンクには、シスターフッドとは「ウーマン・リブの運動の中でよく使われた言葉で、女性解放という大きな目標に従った女性同士の連帯のこと。」とある。焼き芋は日本、ドーナツはアメリカをさす。日米間という意味ではなく、日本とアメリカそれぞれでの女性解放連帯史といった意味のようだ。何か視点の新鮮さを感じさせるので読むことにした。360pと言う大部の作品だ。第1部の日本に関しては1~4章の19世紀後半から、第2部のアメリカに関しては5~8章の19世紀初頭から20世紀いっぱいの歴史を取り上げている。
- プロローグには「「わたし」を捜す」と言う副題が付いている。
- 細井和喜蔵の「女工哀史」から始まる。このHPの「蚕糸王国・岡谷」('13)に、私にとって印象深かった「女工哀史」関連の見聞と、それに対する感想を列挙している。哀史ではなかったが楽史ではなかったと最後に書いている。哀史は格好の社会研究材料として文化人や学者、ジャーナリストらに取り上げられたようだが、筆者は女工の日常茶飯の生活にある労働としての視点に重点を置く。生産労働を支える裏方労働~陰の労働~には家事という表現では言い尽くせないネットワーク事業を受け持つ仕事がある。無駄話もその一つ。この家事、無駄を意識した歴史を紡ごうというのだ。このプロローグには著者本人による詳細で的確な各章の総括がある。よってここでは本の主題にある「焼き芋」と「ドーナツ」の章を紹介するに留める。
- エピローグには「「わたしたち」を生きる」という副題が付いている。
- 津田梅子の我が国女子高等教育に残した功績はよく知られている。150年前にアメリカに留学、その後さらにもういちど留学し、そのときの経験が我が国での津田塾大学設立に繋がった。森有礼が同じころアメリカにあり、梅子が受けたであろう女子教育環境を具体的に書き残している。彼は後に初代文部大臣になったが暗殺された。梅子は国の制度改革には挫折を味わったが、森を失ったことも影響しているのだろう。長岡藩家老の娘のアメリカ経験談(「武士の娘」 ('15))は読んだ。文化ギャップの大きさにはあらためて驚くし、梅子の苦難に思いを馳せる。この国の指導勢力は、資本主義社会を支えるシャドウ・ワークとして、「内助の功」「良妻賢母」の論理を意図的に、社会制度、家族制度に組み込んでいったのである。
- 「わたし」「わたしたち」を今ではSNSが、仲間の中でときには不特定多数に向けて、直接的に媒介する時代になった。アメリカ・ファースト的あるいは強権主義的動きは、もはや無視できぬ流れだ。細井の内縁の妻・高井としをの「わたしの「女工哀史」」が陽の目を見るのに何十年も必要だった時代とは異なり、生身の人間の判断とか感情が、日常生活の世界にタイムラグなしに流れ込み、日本を世界を動かす、政治家や企業家や学者の見識を左右する時代がやってきた。もう一つ、現在の日本~先進諸国~は少子化によってどんどん過去をもてあまし、将来の取り分を失ってゆこうとしている。子をもうけることは、今や生身のヒト~ことに女性~が切実に意識せねばならぬ責任だ、今日に至る経過を精密に論証した著者に、この2点をどこかで是非語って貰いたいと思う。
- 第2章は「焼き芋と胃袋−女工たちの身体と人格」。
- 高井としをは10才(1913年)で炭焼きの家庭から、女工募集人につれられて工場の糸くず拾いの仕事1日13銭!を与えられる。働いて儲けの現金をわが手にすることに憧れていたとある。彼女は身の回り品をわが手で買い揃えた。伝統の農山漁村社会ではあり得ない経験だったろう。著者は「女工哀史」を資本主義的搾取論から離れて、時代に生きた下層の女の目で話そうとする。女たちの最大の関心事はもちろん食い物で、女工からは最も出しやすい工場管理者へのクレームであり、工場も対応せざるを得ない要素を含んでいた。引用されたエピソードが、企業側の女工に対する姿勢を具体的に教えてくれる。高井としをが就労した頃は寄宿女工が大半になっていた。企業は衣食住込みで女工を雇う、経営家族主義を実行するようになっていった。
- 職工計80万内女工50万の時代になり、工場の健康環境整備が問題になる。工場法公布が1911年施行が1916年で、高井としをの就労期と重なる。栄養学的見地からの要求が出る。カロリー、動物性タンパク質などが寄宿舎の献立や体重変化調査から指摘がでる。第三者的な労使関係協調会によって、産業福祉を推進しようとする動きが積極化した。具体的にはまず「工場食」と「共同炊事」だった。企業側にしても食い物の恨みは怖いから乗らざるを得ない。労使にとって絶好の駆け引き材料でもあった。
- そのころの日本経営陣を代表するヒトとして、「温情主義」「経営家族主義」の鐘紡・武藤山治と「人格向上主義」の倉紡・大原孫三郎がでている。前者は生活改善には努めたが、欧米の女権運動に批判的であった。資本側の大勢を代表していた。後者は請負制が普通であった炊事場と食堂を工場直轄とし、工場が住民の共同作業場にと、寄宿舎ではなく職工社宅村を建設した。先進的資本家だった。
- 焼き芋は女工が工場と寄宿舎の外に自由に出られる権利の象徴である。「寄宿女工を自由に外出させること」と言う女工たちの待遇改善要求が入れられたのは、1927年(昭和2年)だった。だが女性には敗戦のときまで選挙権はなく、政党活動も認められなかった。1890年の集会及政社法では女性の政治活動は禁止され、政談集会参加主催ができるようになったのは1922年だったと言う背景がある。
- 第8章は「ドーナツと胃袋−台所と学びとシスターフッド」。
- アメリカで女性が参政権を得たのは1920年だった。この章にはボストンを中心とする地域で、それまでの女性たち自身による分厚いシスターフッド活動の眺望が記述されている。通読してみて彼我の比較がついつい頭を過ぎる。我が国戦前にも相当する活動はあったが、継承性に乏しく、ネットワーク性も脆弱で、かつ限られた一部階層とか一握りの先進思想者といった、いわば自己膨張性に乏しい運動のように感じた。社会を引きずるような中産階級層の活躍が見られないのだ。判ってはいたが、敗戦の結果アメリカに与えられた参政権でしかなかったことに、女権思想浸透の遅れをあらためて感じる。
- 本章はまずエレンという田舎娘の19世紀後半における活躍ぶりを紹介する。花嫁学校ではない初の女子大を出、マサチュ−セッツ工科大学MITの科学学士号を取り、公衆衛生の進歩に業績を上げ、女性教育に貢献する。家事と化学を繋げる家政学の萌芽的存在になる。25才で女子大に入学できたが、学資300ドルは自分のアルバイトで作ったとある。二十歳そこそこでしかない若い女性が、自前で大型資金を作れる社会環境にあったことに驚く。
- ボストンは移民で溢れていた。1850年では人口の46%が移民だった。内85%がアイルランド系だった。女性の単身渡航者も多かった。渡航者の所持金はボストンでの1週間の生活費9ドルぐらいだった。不健康な社会を台所から変える運動として、エレンは低所得者層居住地域にパブリック・キッチンを設ける。困窮者に健康食を提供し、調理方法は公開して食水準の向上教育に資するといったものらしい。「人々がよりよく食事ができる方法」の科学的研究が目的だと唱われている。利用者の多くは「パン屋もの」で食事を済ます縫製女工だった。パン屋ものとはどうも菓子パンクラスのファースト・フードらしい。表題の「ドーナツ」はここで顔を出す。自炊する時間も空間もない劣悪な労働環境だった。
- ボストンで前米初の学校給食が始まる。「栄養学」が認知されエレンが給食事業の諮問を受け、パブリック・キッチンの中央調理室から各校に運ばれた。以降30年、エレン没後は、女医が幅広い女性の支持で動かすWEIUなる組織で、2006年まで活動が継承された。やがて全米の公立学校へこの学校給食が普及した。本書は「「最低賃金」ではなく「生きるための賃金」を」と言う題で、アメリカ女性労働運動の今後を締めくくっている。生きるための賃金とは、命の維持のほかに人間らしく生きるための出費を含む賃金という意味である。
('24/12/7)
