鶸(ひわ)
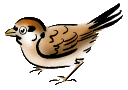
- 三木卓:「鶸:芥川賞全集 第十巻」、文藝春秋社(1982)を読む。この作品は昭和48年('63年)上半期の第69回芥川賞受賞作品である。毎日新聞に「三木卓さんお別れの会「戦後文学の輝ける恒星」」という記事が出て、この作家と代表作を知った。30pほどの短編小説。題名の鶸を平凡社の世界大百科事典で牽いてみた。スズメ目アトリ科ヒワ亜科の鳥の総称で、ヒワ類の代表的な飼鳥はカナリアであると書いてあった。
- 明記してないが敗戦直後の真冬の新京(今の長春)が舞台のようだ。新京は旧満州国(中国東北部)首都。ソ連兵が闊歩する中での日本人の逼塞呻吟状況を少年の目で描く。少年の家庭は、祖父母、父母、兄(中学生)を入れての6人。住宅街に住んでいたということは、敗戦まではきちんとした生活基盤があったということだろう。父は占領軍の国家保安部の追求を怖れて町中に潜んでいたが、高熱を発し帰宅する。送り届けたのは開拓団の難民収容所のヒトだった。極寒の地には逃げ隠れする場所などそう多くない。
- 医師の往診で発疹チフスと判る。発疹チフスとは懐かしい病名だ。戦後の日本で怖れられた病名の一つである。Webには「シラミなどが媒介し、潜伏期間を経て、39〜40℃の高熱、頭痛、寒気、吐き気や嘔吐、だるさ、手足の筋肉痛などの症状が現れ、発症後は発疹がでる。幻覚、けいれん、昏睡などの神経症状、咳などの呼吸器症状や頻脈を伴うこともある。適切な治療を行わないと10〜60%が死に至る。」と出ている。小説最後の頃の父は幻覚+昏睡段階のようだ。今なら適切な抗菌薬が使えるが、当時の医師は食塩水とビタミンぐらいしかなかったようだ。介護人への感染防止のシラミ退治については書いてなかった。まだ医家は、疑いは持っていたかも知れないが、シラミによる媒介と明確に意識していなかったようだ。
- 占領軍兵士の白昼堂々の略奪ぶりが書いてある。少年は家計を助けようとタバコの露店売りをやっているが、兵士が値の高そうなものを片っ端から取り上げてポケットにしまい込む。私も京都の四条河原町の街角で、簡単な台に「宝くじ」を広げて売ったことがある。アメリカ兵がいきなりそのくじの束を「サンキュー」といって持ち出した時は仰天した。でもこれは彼の冗談で、私が慌てるさまを見て満足して返却してくれた。敗戦国とはいえ日本はまだまだ道徳性高い国民で、少年の店から強奪する人間など考えたこともなかった。
- 隣の物売りが「あいつは囚人部隊の生き残りだろう」と同情する。現在ウクライナ戦線で、ロシア軍は囚人部隊を繰り出していると聞く。ロシアには囚人を戦場に駆り出す伝統があったのだ。ウクライナ軍もやっている。するとスラブ民族の文化にそのような徴兵を許容する心情があるのかもしてない。
- 敗戦国少年に対する現地・満州国民の姿勢は、恐怖感を与えるようなものではなかったようだ。考えてみる。満州国民には日露戦役以前からのロシアの横暴ぶりは身に染みついていただろう。それ以降の日本に対する感情も決していい方ではなかったとは思う。でも敗戦までは、一応平和裏に付き合いができた相手であった。敗戦でいずれは引き上げてゆくだろうとは誰もが納得していいただろう。満州国民にとってもっと心配のは、中国本土から来る国民党軍と共産党軍だろう。
- 彼らには、戦勝国気分も解放国民気分もなかったのではないか。旧満州の当時は、中国本土とは異なり、中国人も進出していたろうが、満語のツングース族を主体とする多民族構成だったと思っていいのだろう。朝鮮民族は南東に多数居住していたし、主に都会であったろうが、白系ロシア人も勢力を持っていた。その上に日本人が軍勢力を背景に幅を利かせていた。そんな中での満州国民の反応が、平均してどうだったかは、私のみならず読者はなべて関心があるのではないか。
- 新京の街はもう水道が止まっている。井戸水を石油缶に入れて天秤棒で担いで帰る。凍てついた一帯の危険な重労働ぶりを描いてある。電気は来ないのだろう、市電は動かず、往来には荷馬車が活用されている。現在国連の救済機関がTVの宣伝で使っている映像そっくりの状態だったようだ。兄弟は医者への支払いのために、乳母車に値打ち品を積んで市場に出かける。邦人の家財は現地人には儲けの対象になるものが多かった。市で店を開けるまでに大勢の現地人が兄弟を取り囲み、てんでに品物を吟味し、1/3から1/5の値をかってにつけて強引に引き取ってゆく。支払いはソ連の軍票だが、ソ連軍の引き上げは軍票価値の下落を意味するから、その処置に対する不安が少年の胸から消えない。引き上げは新京が中国軍に引き継がれたあとのようだから、まだ邦人にとっては先の見えない不安な毎日であった。
- この小説の意味は、そんな歴史事情の下で、少年の疑心暗心が、さしあたっては兄のような身近なところから、次第に日本人社会全体の広がってゆく姿を描いている。貧すれば鈍するというのか(これが作者の主題だったろう)、これまでに営々と培われてきたであろう相互の信頼関係が失われてゆく。兄が続く失敗から半ば自棄になったように、この次はなにもかも売って金に換える、鶸を欲しがる床屋がいるからそれも売ると少年に命じた時、少年は鬱憤を晴らすように鶸を絞め殺す。鶸は少年が愛する家禽でよく懐いていた。
- 戦後の満州の記憶を持つ年層が元気で、日本の中堅を担っていた頃の作品だ。私の周辺には戦中の満州帰り、ソ連占領を経験した満州帰り、朝鮮からの引き揚げ者などがいて、彼らが問わず語りで異国を語ってくれた覚えがある。そんな経験からいっても、本書の著者の環境描写にあまり無理はないと思う。著者は、幼少期を満州で過ごし、終戦後に大陸を転々とした後に帰国したという。
('24/6/10)
