ネアンデルタール(その二)
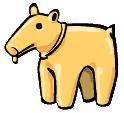
- ネアンデルタール人はネアンデル渓谷で1856年にはじめて発見された。1886年に完全骨格が出土した。そして現生人種でない絶滅集団と認知された。過去の最近縁の人種への特別の関心は、考古学の長足の進歩をもたらす一方、人々の想像力を掻き立て、その時代の思想潮流を背景に、さまざまなSF小説をヒットさせた。
- 学問的には、発見当初から、白人至上主義の科学的根拠に組み込まれた。奴隷制や植民地主義を正当化するために利用された。有色人種をホモ属の原始的な分岐とみなす。20世紀に入っても、ネアンデルタール人は人種差別的信念を強めるために利用され続けた。この姿勢は二次大戦が終わってからも続いている。アポリジニは偏見の対称だった。最近になって、先住民の狩猟採集民の知識と世界観を、考古学に活用しようとする動きがある。
- 恐竜の絶滅が巨大隕石の衝突だったとよく言われる。(一瞬に絶滅したのではなく、数千年数百年をかけて数を減らしていった。ネアンデルタール人の絶滅はもっと長い期間が掛かっているだろう。) ネアンデルタール人の絶滅には、隕石衝突のような明晰な理由は出てこない。いろいろ考えられているようだが、有力なものに気候変動の影響が考えられる。ネアンデルタール人が消えた4~4.5万年昔は、5.5万年昔から始まったMIS3(間氷期)だった。その期間内ではさらに亜氷期と亜間氷期が繰り返されている。
- 同時期のハイエナは、劇的に獲物が減少していたMIS4の氷期の影響を克服しMIS3の間氷期に入って頭数を回復したが、ネアンデルタール人は回復し得なかった。この天地ほどの相違に対して、彼らが小集団単位で行動していること、その密度が、私には、フラクタール幾何学で言うところの臨界密度を切ったために、繋がりが薄れ、よその遺伝子をもらえない血族結婚の弊害で、徐々に人口を減らしたことが考えられる。あの広大な面積に総人口20~30万程度では、この危険はどの動物にも存在したはずである。ハイエナ:イエス、ネアンデルタール人:ノーはそんな偶然で、ぎりぎりの厳寒地帯ではあり得ることだったのだろう。
- 第5章の「氷と火」に、氷期、間氷期の説明がある。MISは長期の気候変動サイクルを示す海洋酸素同位体ステージのことで今はステージ1の間氷期。ネアンデルタール人らしい特徴は、およそ35万年前以降の間氷期MIS9から顕著になる。ネアンデルタール人は氷期が来ると記録からあらかた消えはする。だが極寒を避け、草原や木立に囲まれた温暖な地域で生き延びたらしい。マンモスだって氷期には温暖の地で化石になったものがいる。MIS3での最悪の状況は別として、彼らは氷期を複雑な技術的文化を武器に何度も切り抜けたのである。第6章の「岩石は残る」には石器の、第7章の「物の世界」には槍から始まる道具の解説がある。
- さて第8章から第13章までは、ネアンデルタール人の生活や社会に繋がる研究の成果である。遺跡発掘出土品と遺骨形質などから、従来の考古学的研究に加うるに、近年の精密な分析化学がかなり詳細に教えてくれる。第2章の図1に進化系統図がある。ヒト科ヒト亜科(ホミニン)に20種以上、ヒト科ヒト亜科ヒト族ヒト亜族ホモ属(ヒト属)に11種、内8種は初期(3−2百万年前)のホモ属から枝分かれしていったとある。
- 第8章は「食べて生きる」。このHPの「カロリー換算」('13)に日本人の1日消費熱量は2000kcalとしていた。私ら老人はその2/3ぐらい。ネアンデルタール人は3500~5000kcal、寒冷地(ヨーロッパ遺跡跡あたりは当時は寒かった)では7000kcal必要だった。
- 彼らはハイエナのような死肉あさりはしない。遺跡の動物遺骨の表面観察や統計から判る。槍で直接突き刺して仕留める。大型獣に立ち向かう。まさにマンモスハンター。サイや500kgからの大型の馬の遺骨も出てくる。鳥魚貝甲殻類昆虫から哺乳類小中動物など手当たり次第に肉を集めた。炭素と窒素の同位体比率から、オオカミやハイエナと同じように肉食が多かった寒冷地区(ベルギー)があったと判っている。
- 暖かな地方の炉あとからは数多くの植物が出てくる。ナッツ、果実、根茎、種子(イネ科植物、エンドウ豆、レンズ豆)。北ヨーロッパの遺跡からも報告されている。直接的証明は歯に残る摩滅パターンと歯石のDNA分析。寒冷地の方が肉食が多い。それでもタンパク質の最大1/5は植物由来である。
- 肉には生食もあったが加熱調理料理もあった。串刺しのシシカバブーなど想像するが、焼き肉より煮込みが多かったのではないか。歯石はデンプンが加熱処理によって変化していたと教える。植物性食料は煮炊きされた。「どんな器で?」に答える遺物はない。保存倉庫や保存食への加工を示唆する遺物はない。発酵の証明もまだないようだ。彼らは狩り、解体、運搬を共同作業で行い獲物を分け合った。ホモ・サピエンスでの食料の分配は社会発展の土台の一つとされている。ネアンデルタール人にも見られることは重要だ。
- 第9章は「ネアンデルタール人の住居」。我らの祖先と同じく、ネアンデルタール人の生活も炉を中心として構成されている。住居は目的に合わせて別々のエリアを使っている。使い回しの証拠もある。狩猟採集民だから定住的ではないのだ。獲物の解体などに共同作業があった。種火は自然界の炎が主だったろうが、火打ち石方式を使った証拠がある。二酸化マンガンが着火剤(助炎剤)になっていた場所がある。地域によっては燃料に褐炭を使った形跡も残っている。
- 第10章は「あの土地へ」、第11章は「美しいもの」、第12章は「内なる心」。
- 第13章は「さまざまな死に方」。ネアンデルタール人に墓葬はあったか。高等動物には、家族ことに母親に、死を悼むあるいは黄泉がえりを期待する行動が見かけられる。私は宮崎県の西都原古墳群の見学から戻ってきたばかりだ。ホモ・サピエンスは太古から死者を墓に葬る制度をどの民族も維持し続けてきた。ネアンデルタール人の遺跡で墓と過去において認定されたものはいくつかあるが、近代の再分析で確定的でないとするケースが相次いでいる。
- 墓所を思わせる複数人の遺骨が見つかる場合がある。生活には不便な場所に、しかもハイエナなどに荒らされたあとがない、部位が繋がった遺骨が出てくる。供花は否定されているが、人工遺物が遺骸の側にあるケースもある。解体された人遺骨が多く発見されている。狩猟動物同様に頭骨を含めた骨格すべてに、皮を剥ぎ、肉を削り落とし、時には粉砕されている。しかし骨に歯形が残っていない。ホモ・サピエンスには人食いの習性が歯形として遺骨に証拠を残しているケースがある。ネアンデルタール人の解体対象は誰だったか。
- 人喰いはあったろう。チンパンジーやボノボとの比較は、同胞遺体解体が特別のものであったことを示唆している。遺骸の扱いに関して、彼らと初期のホモ・サピエンスの境界はぼやけてきた。でも3万年前ごろからホモ・サピエンスの屋外埋葬が目に付くようになる。そして副葬品に両者の顕著な違いを見せるようになる。筆者は、故人の遺物を大切に残す我らの習性を、ネアンデルタール人の人喰い的風習の延長先に見ている。キリスト教の聖体拝領で、パンと葡萄酒を授かるのは、信者がキリストと一体になる儀式だが、人喰いはそれと同源なのではないか。
('23/4/2)
