三木城合戦記
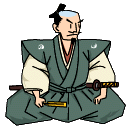
- 天野純希:「もろびとの空 三木城合戦記」、集英社(21)を読む。このHPの「新書太閤記 第五分冊」('19)、「新書太閤記 第六分冊」('20)に秀吉側から見た三木城攻略戦の詳細と背景が載っている。秀吉の兵糧攻め(干殺し)を受けながら、城兵3500(数千とも言われている)はよく戦い1年10ヶ月を持ち堪えた。最後は城兵城内民の命と引き替えの城主・別所長治とその女こどもを含む一族の自決による開城になった。
- 「一向一揆と石山合戦」('21)には、一向一揆の石山本願寺に対する信長の「大坂根切り(全員殺戮)の覚悟」命令や、戦国では領民の安全を保証してこその領主であったこと、戦になれば、領民は城に一斉に逃げ込むのが当たり前だったことなどが指摘されている。三木城は領民収容型の総構えだったとされている。播磨一帯は浄土真宗が浸透していた地方の一つで、その中心に三木氏に属する英賀城の城下町に英賀御堂(本徳寺)があった。三木城には多くの門徒が抗戦に参加したと思われる。
- 三木城趾は、随分昔〜半世紀ほどになるか〜だったが、神戸電鉄に乗って一度訪れた。一国一城令により江戸時代に廃城になった。遺構らしい遺構があったようには覚えていない。地図にはたくさんの出城または砦の跡が載っている。いずれも石碑程度だ。別所家の墓所のあるお寺は訪れた。三木の町にはお寺が多い。そのときの記憶にはないが、一族自刃の時の辞世は石碑になっているという。長治(23才):「今はただうらみもあらじ諸人(もろびと)の命にかはる我身を思へば」、長治妻(22才):「もろともに消えはつるこそ嬉しけれ後れ先だつならひなる世に」。あの若さで立派なものだ。長治の辞世の「もろびと」が本書の主題名になったことは明らかだ。
- 本小説の主人公は百姓の娘・加代。父は室田弥四郎というもと別所家の元剣術指南役。戦記物の主人公は男性なのが普通だが本書では女性である。したがって彼女の周辺に登場する人物は女性が半分だ。ことに波という筆頭家老にして城主の叔父・吉親の正室は、男勝りの武芸者で時には出撃に加わる女武者組を率いている。女の目で語る戦記物だから、第一線で戦う女武者が必要なのだ。波は加代を上回る紙面を占めているときがあるから、ともに主人公だとしておくべきか。彼女は歴史上の人物らしい。
- 年若の長治に代わって叔父2人が別所家を牛耳っている。吉親とその弟・重宗。前者は別所家の家格と播磨武士のプライドを大切に思う保守派の頭目であり、後者は信長の将来の覇権を考えた大局観からくる進歩派の旗頭である。城内は吉親派が優勢となり重宗は秀吉のもとに脱出する。吉親主導の反信長戦は、毛利の援兵と武器兵糧補給を当てにしていたが、小早川隆景の率いる8千は秀吉に阻まれ退却。二度と援軍は現れなかった。飢えがまず城に逃げ込んだ住民から始まる。
- 飢餓が迫る様子はよく描写されている。食料の傾斜配分は戦局悪化とともにひどくなる。戦闘要員から遠いほど配給事情は悪い。太平洋戦争当時もそうだった記憶がある。領民のなかでも壮年男子は動員される分手厚いが、役立たずの老齢者女子こどもは、最後には穀粒を探さねばならぬほどの粥にでも炊き出しにありつければいい方だ。草木の食えるもの、壁土、牛馬、ネズミから昆虫まで食って命を保つ。城の明け渡し前ごろになると、死者の肉を半ば公然と口にするようになる。軍兵ですら幽鬼のような戦ぶりになってきた。講和の道を探る波は、吉親から追い払われ第一線に出ているが、前線に食料が途絶えたのを知ると、戦場の屍を集めるように命じる。追い詰められた旧日本軍を思い出させるような記述だ。
- それでも徹底抗戦する理由は、信長の根絶やし作戦がかけ声だけではなく、殺戮(撫で斬り)を実行してきた過去への、生命の本能的なおののきと嫌悪心敵愾心などが、ことに上層部で激しかったことである。さらに秀吉軍が、宇喜多勢が敵対していたころにその支城である上月城、福原城を陥落させたとき(第一次上月城の戦い)、撫で斬りをやった。同じ播磨であったため、三木の将兵にはその恐怖が根強く残った。
- 戦況不利とともに、下層部ことに領民あたりから降伏助命の主張が出るようになる。長治が戦意維持のための行動が記されている。支城とか砦がことごとく陥落しのこるは本城のみになると、全体への配慮の手を打とうとする長治に主戦派の吉親は意を決してクーデターを実行する。これは作者の創作だろう、史書にはその記録はないと思う。長治一家を城内の一角に閉じ込め軍議民政から隔離、吉親独裁へ走る。非勢の中の主戦論だから、吉親は降伏派の締め付けに奔走する。長治一家も吉親の妻・波も、もう戦の無意味を悟っていた。
- 秀吉側の忍者(甲賀もの)組織が暗躍している。城側の摘発はきびしい。ゆえなくまきぞえで死んで行くものも描かれている。長治の密使が女忍者の手引きで城を脱出する。密書の内容は別所家の血の断絶による城兵の助命保障確約要求だ。上月城の尼子が毛利に降参したときも(第二次上月城の戦い)、尼子を名乗る一族が自決し、武門としての尼子氏は完全に滅亡した。主家が滅びても係累が残ると再興紛争が持ち上がるのは、再々歴史に見られる事実である。根絶やしに勝利側が直系の男子の首級だけで済ませるときもあったが、別所家の場合は妻子まで犠牲になった。
- 助命の約束は守られたか。ウクライナ侵攻のロシア軍が撤退したあとに、あちこちで、集団墓地が発掘されている。それに類した集団墓地が三木にもあるそうだ。撫で斬りまでは行かなかったが、抗戦組が相当厳格に追求されたか、あるいは戦後に城内の死者を葬ったあとなのか今となればもう不明である。
- 開城派にとっては城主長治の復権が不可欠だった。まだ抗戦派が幽閉状態にしている。この小説では図抜けた名将とか図抜けた剣豪は出てこないが、長治救出には相応の勇士が出現している。吉親の近習だった。裏切りをなじられた彼は、長治が主君で吉親の臣ではないと言い放つ。「見知りの百姓娘が、父母を失い幼い妹を亡くした上昨夜逝った。想い人を作る。子を産む。そんな当たり前のことを何一つできないまま、飢えに苦しんでこの世を去った。その責任を問う。」とした。
- 評定で降伏が決定したあとも、吉親派の悪あがきは収まらなかった。再度のクーデターを試み、長治の指揮で降伏派と秀吉勢に討ち果たされる。吉親を切ったのはその近習で、彼はそのあと自刃。太平洋戦争に敗れたときも、本土決戦を主張する大本営の陸軍の若手参謀が反乱を起こし、宮中の天皇の身柄を確保しようとした。それにヒントを得たフィクションであろう。
- 加代は女武者組に入り、波に信頼され行動をともにするときが多かった。さいわい開城まで生き残り弟妹2人とともに、出身の村に戻る。一家は家族の半分を失っていた。波のもとで女武者組の世話役を務めており、出撃の時は長治から軍目付を仰せつかったという、「死に損ない」と自虐する若侍と所帯を持つことができた。彼には朝鮮戦役のときに有力藩から武将待遇での仕官の誘いがあるが、百姓に留まる。これがこの小説の落ち着きどころである。
- 播磨国は群雄割拠のまま信長勢の侵攻を受けた。播磨およびその近隣諸国の波多野秀治、荒木村重、中川清秀、高山右近、宇喜多直家、小寺政職さらには播磨守護赤松氏などの去就は、彼らの地位がいかに不安定であったかを物語る。毛利勢と信長勢の狭間にあり、朝廷、将軍家、宗門が大型化できない武士団と微妙にバランスを保っていた。
('22/9/23)
