黒牢城
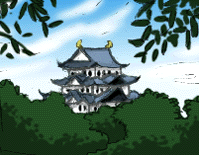
- 米澤穂信:「黒牢城」、角川書店('21)を読む。 2021年下半期 第166回 直木賞受賞作である。440pほどの中編時代小説だ。信長から離反した荒木村重を、その居城の有岡城(伊丹城)に、翻意を促す信長の使者となって訪ねた黒田(小寺)官兵衛が囚われの身になるところから、解放されて後、斬られたと観念していた人質の我が子・松寿丸(後の黒田長政)と再会するまでを描く。
- 村重の軍略は見事だった。播磨から備前、備中へ秀吉軍が進むときに、安土との中間で反信長勢が立ち塞がる。軍兵5千。毛利からは支援の確約が届いている。信長の城攻めを待つのであって野戦はやらない。有岡城は田畑ぐるみ町ぐるみの総構え型で、その防御持久力には自信があった。兵糧・軍需品の蓄えは十分だった。村重の武名は高く、軍兵はよく統率されていた。村重は「人は城」と信じて、内部からの崩壊・寝返りには万全の用心を怠らなかった。外郭の高山右近の高槻城、中川瀬兵衛の茨木城の降伏は予定に入っていた。
- 狂いも生じる。大和田城が信長に下る。大和田城は本願寺がこもる大坂と有岡城の重要な中継ぎ地で、有岡城は現地では最重要の味方・本願寺軍から孤立してしまった。首謀者の質子・安倍自念の厳罰問題が重臣から提議される。信長は反逆者には熾烈に対応した。謀反と感じた瞬間、躊躇なく質子の成敗を命じるのが普通だった。それに反して、村重の人質に対する価値観は違っていた。何かにつけての価値観の差は袂を分かった大きな理由である。彼は離脱した右近の質子2名を殺さず、瀬兵衛からは質子も取っていなかった。織田の城目付も斬っていない。自念は閉牢になる。だが収まらぬ御前衆が士気高揚のためにと彼を刺殺。地道に立証されてそれがばれる。だが命に反した御前衆は罪を許され、恩義に感じて突撃戦死。村重の並々ならぬ統率力と、それを支える人となりを示すエピソードになっている。
- 村重側が小競り合い程度ながら夜襲で勝利する。信長側の馬廻り役の若手・大津伝十郎が功を焦ってか、最前線に100名ほどの陣を敷いた。村重は御前衆30名、雑賀鉄砲衆(一向宗徒、大坂本願寺派兵)20名、高槻城反信長の離脱組(南蛮宗徒)20名の70名を自ら率いて、月明かりのもと急襲し、主将の伝十郎を討ち取り残敵を蹴散らして引き上げた。この風変わりな村重側の陣容は、家臣と与力(寄騎)の微妙な立場の差や、教会焼き討ちなどが起こる宗教間のいがみ合いの調整という意味が含まれていた。村重は、信長陣からの矢文で、彼の着陣と、備前・宇喜多直家の信長側への寝返りを知る。宇喜多の動向は家臣の誰にも明かさなかった。直家はそれまで毛利側に与しており、毛利軍の早期東進を容易にする存在と見られていた。
- 織田は攻め急がない。城の包囲網は厳重になる。外部との連絡に支障を来す。城に忍び込む諜者間者が増え、第3列的暗躍が絶えない。栗山善助が官兵衛を探して本曲輪まで忍び込んでくる。史実らしくドラマにもよく出てくる逸話である。城内の往来が警備のために不自由になる。宇喜多寝返りは衆知になって行く。兵士や民に厭戦気分が流れることを警戒せねばならない。和平交渉は、有岡城開城が信長にとって価値ある状況で行わねばならない。光秀担当の丹波ルートが開ければ摂津の重要性は落ちてくる。村重はごく内密に使僧を通して明智光秀との接触を試みる。
- 光秀側の応対は斉藤利三が行った。村重の親書は光秀に届かなかった。利三は、包囲下では人質送付は困難ゆえ、天下に名高い茶壺・寅申(とらさる)を引き出物として要求する。名物・茶釜の平蜘蛛譲渡を拒んで自刃した松永弾正久秀の事件は1年半の昔だった。茶人・村重はその轍を踏みたくはなかった。使僧に密書とともに寅申を託す。だが使僧は城外に出るまでに刺殺された。犯人の調査が村重自身の手で行われる。なかなか見事な推理で解明が展開する、この第3章だけでもちょっとした時代探偵小説だ。
- 使僧は二重スパイであった。というより依頼されれば、だれにでも役に立とうとする構えだった。有岡城内に、時とともに希望が失われて行く形勢に対し、織田に秋波を送る武将・瓦林能登が出現し(もう籠城開始後8ヶ月になろうとしている城内の士気の変化を代表させている)、使僧はその連絡役をこなしていた。この能登は常に露見の危険を感じている。村重はどこまで知っているか。使僧の出立前にその情報を入手しようとして、密議の中身を聞き出そうとする。使僧としての本分からであろう(ここの説明がしっかりしていない)、守秘を通す相手に対し能登は刃傷沙汰に及んだ。
- 村重が決め手とした証拠は、宿泊所となった草庵の寺男の、帰ったときに見えた使僧らしい男(実際はすでに殺害されて犯人が替え玉として振る舞っているのだが)が唱える経が真言のようと言ったことだった。使僧は日頃念仏を唱える僧である。寺男は生涯のほとんどを一向宗の寺で過ごした。彼には顕教(一向宗など)と密教(真言宗など)あるいはそれ以外を容易に区別できた。犯行の武将は僧形ながらほとんど経文に縁がなかった。事件後も光秀との接触は試みられる。しかし史書にはそれに対する言及はない。
- 解死人(げしにん)を加害側が被害側に送る和解の作法があったという。室町時代からの古法だ。類似の話は例えば剣術商売:「その日の三冬」にも出ているが、そこでは解死人にされているとは知らずに使いとして被害者宅に出かけていって、主人の詫び状で初めて知るという話だった。真の加害者でなくてもよい、身代わりでよい、お詫びの印に解死人を被害側にどうでもしてくれと送る、本書では解死人は斬られずに送り返されている。喧嘩の原因は、たとえ戦のない日でも、1日5合の配給米では足らないという食い物問題であった。たまたま巡覧中に村重はこの解死人届け隊に出会う。村重は城内の出来事に目が行き届かなくなり、判断が村重を通らずに行われる風潮を感じた。
- 使僧刺殺事件犯人の能登は、捕り手に包囲されたとき落雷を受けて死んだ。だが同時に能登を鉄砲で撃ったものがいる事実が判明した。能登の口から漏れることを警戒する織田内応の輩がいるのかも知れないと、村重は訝る。
- 村重の年若の妻・千代保をあしざまに表現したドラマや小説にはお目に掛かったことがない。今までは何となく善良で影の薄い存在という印章だった。本書には大坂本願寺の坊官の娘で、もちろん門徒だが、村重(禅宗)に念仏を進める風はなかったとある。一向宗に使者の菩提を弔う教えはない。でも宗旨に反して千代保は持仏堂で数々の死者の菩提を念じている。
- 彼女は伊勢長島の一向一揆の数少ない生き残り。凄惨極まりない戦闘を経験した。最後は城塞の中で2万が焼け死んだ。本願寺の、進むは極楽、退くは地獄などは祖師の教えではない、それは一揆軍の使う方便で、進もうにも進めぬもの、つまり小刀一つなく法敵に挑むすべのない民草にも極楽はあるのだと周囲に伝える。死しかない局面で、民は来世は極楽であってほしいと願うのみである。彼女の人徳を慕う人が増えて行く。有徳の僧(使僧)を殺した能登を雑賀衆に撃たせたのは彼女であった。村重には、仏の罰があることを民に信じさせたかったためという。絶望の城内に、かすかにでも光る灯明を灯したかったのであろう。
- 村重は毛利援軍の直談判を発案し、茶壺・寅申をもって少人数で有岡城を脱出、籠城開始後10ヶ月。主を失った城はたちまち瓦解。女子どもを含む多数の処刑者が出た。千代保のすがすがしい刑場姿が描写されている。辞世:「みがくべき心の月のくもらねば ひかりとともににしへこそ行(ゆけ)」は、極楽浄土(西)への期待を表現している。仕えた女房衆も従容として死を受け入れたとある。千代保の信仰は本物だった。
- 今「おんな太閤記」(本HP:「おんな太閤記(前編)」('14))が再放送中だが、そこでは松寿丸をねね(北政所)が、信長の命に逆らって、義母なか(大政所)につけて郷里の中村郷のお寺に小坊主として匿ったことになっている。本書では、竹中半兵衛(療養中の軍師)が隠し通す。吉川英治の新書太閤記もそうだった(「新書太閤記 第五分冊」('20)、「新書太閤記 第六分冊 その1」('21))。NHK大河ドラマ「黒田官兵衛」でも同じだった。黒田家は幕末まで続いたから、松寿丸の危機は史実だろうが、誰が隠したかまでは不明なのだろう。
- 村重は事件のたびに官兵衛を地下土牢に訪ねている。村重は下克上でのし上がった代表的存在だ。放浪のすえ池田家に任官、頭角を現し主家を乗っ取った。人脈は薄く信ずるに足る人材は少ない。天下を論じられる配下は皆無。官兵衛はまたとない慧眼の士。獄死と引き替えに彼から形勢判断を引き出す。村重には官兵衛も一目置いていた。官兵衛は福岡藩に家訓を残した、そこには村重から学んだものもあるようだ。
- 神の罰より主君の罰おそるべし。主君の罰より臣下百姓の罰おそるべし。
('22/8/24)
