南アジア~15世紀(その2)
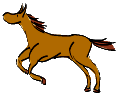
- 二宮文子:「南アジアにおけるムスリムの活動とイスラームの展開」。
- 私たちは、シルクロードのオアシス国家の歴史で、「コーランか剣か」が如実に実行されたことを知っているから、南アジアに侵攻してきたムスリムにも苛烈な行動を予想してしまう。だがオアシスでない。異教徒が多数派の大陸で少数派の彼らがどう行動したかは興味ある問題だ。11世紀からムスリムの本格的進出が始まる。
- 11世紀末ごろには、北西インドから東のベンガル地方まで、肥沃なガンジス川流域を中心とするインド大陸の最もおいしい地域に、イスラム勢力が進出する。南インドへも侵攻するが、在来君主を従属化する程度とし、せっかちな直接支配はやっていない。それが14世紀初期。彼らはアッバース朝のカリフからスルタンと認められる。実質のインドの中央都市デリーを根拠とするスルタンは、特にデリー・サルタナトと呼ばれる。中央政権が弱まると地方王権が独立活動に入る時代が繰り返された。
- デリー・サルタナト成立前から、8世紀ごろからの海洋進出を通じて、ムスリムの南アジア移住は始まっていた。モンゴルの侵攻(1210~)やティムールのインド侵攻(14世紀末)が流れを加速させた。アラブ系、イラン系、アフガン系、モンゴル系(新ムスリム、13世紀後半)などが濃淡の程度は場所によりけりだろうが、イスラーム化が在来文化と融合しつつ起こる。多神教の世界観から一神教の世界観との混和・融合は、民間信仰の5人の聖者を引用して説明してある。5人にはイスラームとヒンドゥーの双方から出ているという。よくは解明できないものらしい。
- 都市部はほぼムスリム、農村部はほぼ非ムスリムといった構図だった。非ムスリムの奴隷や捕虜がスルタンなどの有力者に仕え、多くは改宗したが、出世して歴史に名を残した例がいくつもある。出自にかかわらず能力主義で、多様な人々を支配層として受け入れる仕組みは、イスラームの伝統だった。後宮の女性もムスリムが妃の条件だったろうが、非ムスリムのままだったものもあるという。ムスリムは一般には軍事的・政治的な優位を勝ち取り支配層を形作って行く。だが非ムスリム側は、同じ枠組みの中で政治的覇権を競い手を結ぶ新たなグループとして、もともと多様性の高い南アジアにきた新参として受け入れて行く。
- この本の枠外だが、ティムールを継ぐムガル朝は、それまでの(13~16世紀)ムスリム王朝のように(デリー・サルタナト(デリー・スルタン朝)時代)、首都をデリーあるいはその近隣に置き、16世紀から、19世紀にインドがイギリス植民地となるまで続く。だから中央支配層はずっとムスリムだった。だが今日の南アジアは、中央部のインドがヒンドゥー(8割弱、ムスリムが14%強)で、それを挟むパキスタン(ヒンドゥーが1.5~2%)、パングラディッシュとアフガニスタンがイスラムだ。イスラム優位待遇社会は数世紀に及んだが、オアシス国家やステップ国家の場合ような、完全な人心支配はできなかった。
- デリー・サルタナト時代の文化が、非ムスリムの先代王朝から受け継いだ文化を発展させたものであることは容易に理解できる。モスク建築でヒンドゥー教やジャイナ教寺院の素材を転用するが、人型の装飾は棄損するが動物は残す、幾何学的装飾素材は目立つ位置に置くなどの配慮が認められるとある。行政や文芸活動は主にペルシャ語で行われ、歴史書や伝記集など、サンスクリット語やブラークリット語では見られなかった形式の作品が書かれるようになったという。だが14世紀以降にはペルシャ語だけでなく各地の言語を用い、地域文化に根ざした文学作品がムスリムによって著される。
- インドの言語事情は複雑でよく判らない。Web(世界史用語解説)によると、ヒンディー語は現在の公用語の1つだが、ウルドゥー語(ペルシア語とヒンドゥスターニー語などが融合して出来た言語)からペルシア語やアラビア語の語彙を取り除いた人工的な言語で、イギリスがイスラーム教徒とヒンドゥー教徒を分離する施策を採ったことと関係が深いという。イムラン:「文学面から見たヒンディー語の歴史」には、ヒンディー語の大古代の様式はヴデッキ語、古代にサンスクリット語、上代にプラクリット語、中古にパーリ語、中世にアパブランシャ語、近世からヒンディー語と呼ばれるように、言語的に時代によって大きく変質しているとある。普通の日本人は仏典の関係で、サンスクリット語は聞いたことがあり、パーリ語もかすかに覚えている程度だろう。
- 和田郁子:「インド洋海域史から見た南インド」。
- インド洋に突き出た半島の沿岸には、東西の物産を運ぶ交易船が、モンスーンを貿易風として活躍する。沿岸には交易基地(居留地)と運輸業や商人のコミュニティが出身文明ごとに形作られた。古くは西からはギリシャ、ローマからペルシャ、エジプト、アラブなど、東からはマレーさらに遠く中国から。時代が下ると、西欧のポルトガルがゴアに基地(1510年)を築き、16世紀後半には日本に南蛮船として顔を出す。胡椒のほかに馬(下記)が重要交易項目だったという。
- デカン高原以南の南インドに居住するのはドラヴィダ語族で、彼らは、北インド中心の印欧語族ではない。先住民族でもない。世界史用語解説には「彼らは、西方からインドに移住し、先住民を征服してインダス文明を築いたと考えられている。しかし、前1500年頃に西北からインドに入ってきたアーリヤ人に押され南インドに追われ、南インドでサータヴァーハナ朝、チョーラ朝、パーンディヤ朝など、独自の文化を持つ国家を展開させた。」とある。世界に2億以上いるという。
- 印欧系のデリー・スルタン朝は時代により異なるが、南インドを版図に加えた時代は短い。非ムスリム系王朝であったり、ムスリム系でも地域王朝であったりする。南インドの王朝は商人に特権を与えることにより経済的な利益を上げる。それによる軍事威力の向上が、領土拡大とインド洋交易の覇権争いに向けられる。
- 13世紀のユーラシアを統合したモンゴル帝国の影響は交易品にも出ている。インド全域で従来の象と歩兵から騎馬主体へと戦闘様式が転換し、軍馬の需要が高まった。だが馬の飼育にインドの風土は適さない。大型の軍馬は中央アジアや西アジアに依存した。各地の王朝がこぞって馬を買い漁っている。
- 鈴木恒之:「インド洋・南シナ海ネットワークと海域東南アジア」。
- 上記和田郁子論文はインド西方との海域交易を主に取り上げているので、もう一方の東方~中国との交易をこの論文で眺めてみる。本論文自体は東南アジアに視点を置いている。歴史資料的には中国文献の比重が高い地域で、東南アジアからは碑文とか寺院遺跡などの考古学的資料以外にあまり今後も期待できないという。
- 東(南インドから見て)海路による交易は、今はマラッカ海峡経由が当たり前だが、3世紀ごろではまだマレー半島横断の陸路を挟む方が有力だった。インド洋・南シナ海をモンスーン1回で行ききるのは困難で、風待ち湊、荷の中継の港町を必要とし、そこには人が集まり経済的に発展する。交易には宗教や文化、制度が同伴してくる。インド化が進む。
- 中国船が遠洋航路に現れるのはまだ先で、中国に到着するのはマレー船だった。600~700人が乗せられ、900トンが積載できたとある。本当とすれば随分大きな船だ。千石船だって150トン積みだ、ちょっと誇張がすぎるのではないか。マレー人は東西の物産のほかに東南アジアの芳香性樹脂類を商品化し大いに儲けた。法顕は5世紀初め海路中国へ帰国した。どの船も200人ほど乗っていたとある。交易の中心はインドシナ半島の海岸域にあり、地域民族+中国王朝勢力(都護府)が支配権を争う構図の興亡が続いた。
- 7世紀に入ると唐王朝下に東西交易が大繁盛する。マレー人の大国・シュリーヴィジャヤ王国が大乗仏教の擁護者として現れ、パレンバンに王宮を築く。義浄が報告を残している。南シナ海、インド洋に跨る交易網を構築する。唐に朝貢している。8世紀には中部ジャワに統一王権・シャイレーンドラ朝が現れ、大乗仏教に深く帰依し、ボロブドゥールなどの仏教寺院を建造する(「悠久のオリエンタルクルーズⅤ」('18))。両王朝が一体化し、勢力を拡大し、マレー半島北部にまで版図が延びる。8世紀半ばには広州や揚州に、ムスリム商人の居留地(蕃坊)の記録があり、彼らが直接海路で往復したことを示す。
- 今はマレーシア、インドネシアは宗教的にはイスラム教が支配(バリ島を除く)する国である。その一方、この地域の有力経済人には中国系が多い。シンガポールやマレーシアには中国系と並んでインド系の経済人が活躍するという。本書は、9世紀から15世紀までの複雑な政治情勢を海のシルクロードをわたる物産や商人で紡ぎながら解説して行く。題名だけを書き上げておく。三仏斉(さんぶっせい)・ムスリム商人、チョーラ朝の海峡域進出と中国商人の活動、マジャパヒト王国、イスラーム化の始動。
- 三仏斉とは、この地域から中国へ朝貢する国家群の総称で、10世紀前半ごろではシュリーヴィジャヤが中心だったという。9世紀末交易中心地・広州で外国人の大虐殺があり、拠点が散ってネットワーク拠点が強化された。拠点ことにムスリム商人のそれが国家群の一つ一つになっているようだ。チョーラ朝は9世紀から13世紀にかけて、南インドを支配したタミル系(ドラヴィダ語族の有力1派)のヒンドゥー王朝。
- マジャパヒト王国はジャワ島東部のヒンドゥー教国家。ジャワ島東部は12世紀には胡椒の中国への輸出が進み繁栄していた。13世紀末、元のフビライの遠征軍による混乱の中から成立した。元軍はビルマ、ベトナム、チャンパー、ジャワへ遠征軍を出したが、ビルマを除くと短期で敗退している。イスラーム化は13世紀末、スマトラの北東岸から始まった。
('22/8/7)
