ホモ・デウス(第1章と第1部)
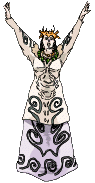
- ユヴァル・ノア・ハラリ:「ホモ・デウス(上)~テクノロジーとサピエンスの未来」、柴田裕之訳、河出書房新社、'18を読む。上巻には序論に相当する第1章、第1部の第2、3章、第2部の第4、5章を含む。第2部は下巻の第6、7章に繋がるので、第1章と第1部への感想をここに纏めることにした。どちらも100pほどの内容の濃い論文である。ことに第1章はそれ以下の総まとめだから熟読の価値がある。しかし本HPに先取りで「ホモ・デウス(第3部)」('18)に著者の議論の中核を書いてしまったので、ここでは落ち穂拾い的に目に鱗のトピックス記事を書き抜くことにする。
- このHPでは「感染症は世界史を動かす」('06)などに感染症の恐怖について書いてきた。本書第1章にもその恐怖を歴史から数値を上げて説明している。免疫のない地方を襲った黒死病(コレラ)、スペイン風邪、天然痘などは人口の何割という死者を出すほどの猛威だった。ただし「アメリカ先住民激減の歴史」('16)に述べたように、アメリカでの先住民の極端な減少には、感染症以外の「インデアン狩り」的な説明が必要である。新型感染症だったエイズ、SARS、エボラも押さえ込まれた。医学の進歩は、感染症による死亡は、いまや非感染症による死亡に比してごく小さな割合にまで減少させている。
- 病原菌との戦いは耐性菌と新薬のせめぎ合いである。抗生物質は最近新種が発見されなくなった。スクリーニングに使える培養可能な土壌微生物がほぼ出尽くしたからだ。ところが未培養の土壌菌をin situで培養する新システムを使って、新抗生物質テイクソバクチンが発見された。これは細菌に対し二重標的機構を持ち、細菌に耐性を作らせにくい。未培養の土壌菌は培養可能種に比し膨大であるから、行き詰まり掛けている抗生物質に明るい将来を将来する可能性がある。
- ナノロボットの研究も画期的で、微生物やがん細胞には40億年の抵抗戦略の歴史があるとは云え、こんなに原理がまったく新しいキラーに対して有効な防御法を見付けるのはきわめて困難になろう。バイオテクノロジーは反面悪用による大量殺害の脅威をもある。しかし自然からの脅威は過ぎ去っている。
- 餓死よりも飽食肥満対策が重要になった。新兵器群は間違えたら世界終末戦争になると誰もが考えるようになった。小規模のテロとか地域限定戦争はあるだろう。古代では死因の15%が人間の暴力によるものだったが、今は1%に過ぎないという。
- 我らは前例のない水準の繁栄と健康と平和を手に入れた。次ぎに目指す可能性の高い目標は、不死と幸福と神性であろうという。人間を神にアップグレードしようとする。まずは非死から。21世紀に平均寿命が150才になったらどんな未来になるのだろう。子育てが終わる40才からさらに110年を生きるとは、どんな生活だろう。70才になったら人生をリセットして一からの新分野に歩み出せるか。100-150才の夫婦生活とは何か。結婚は何度が適切か。何10年経ってもポストのない停滞社会ではないか。「科学は葬式のたびに進歩する」というプランクの言葉は死語になるのか。
- イギリスには「3人の親を持つ胚」法がある。ミトコンドリアの遺伝子は両親ではない第3者のものを取り入れた胚だ。ミトコンドリアは細胞のエネルギー産生に関わる。赤ん坊の形質は両親から貰った細胞核DNAできまるから、エネルギー産生に関する遺伝病だけを除けるというわけ。両親の遺伝をどう貰うかはお神籤と同じ。試験管にたくさんの組合せを作って、その中から親が望む遺伝子の組合せを持った胚を母親の胎内に返せば、両親としてはもっとも望ましい赤子を作ることが出来る。まだ許可されていないが、神へのアップグレードの可能な第1歩第2歩ぐらいは、科学的に既に準備ができている。さらに進んだ遺伝子操作によって、生命40億年の歴史がなしえなかった新生命を誕生させることだって、決心次第のところまで来ている。「ホモ・デウス(第3部)」('18)には、この危険な試みを中国研究者がやったというニュースを載せている。
- 我らをホモ・デウスへと駆り立てるdriving forceは幸福の追求だ。本HPの「サピエンス全史(下)Ⅲ」('17)には幸福論がある。また「脳内麻薬」('15)、「なぜ皮膚はかゆくなるのか」('15)には、快楽への細胞レベルの生化学的な解説がしてある。悪いことに幸福感には持続性がなくすぐ飽和して次を欲しがる。ブッダの幸福観は生化学的な見方との共通点が多いという。ブッダは飽くことなき幸福追求への渇望を癒す道として、心の鍛錬を主張した。しかし人類は今のところ生化学的な解決法に力を入れている。新しい鎮痛剤であったり、新しい飲食品だったり、新しいゲームソフトであったりだ。
- 19世紀半ばに、カール・マルクスは見事な経済的見識に到達した。このままであれば、先進資本主義国には革命が相次ぎ労働者階級が勝利すると彼は予想する。しかし資本家は「資本論」の論理を活用して社会を解析し、自分の行動を変えた。マルクスのミステイクは、資本主義者も本が読めることを忘れていたことだと皮肉ってある。純科学的予想とかそれに近いテクノロジー的予想はおおむね正しい場合が多いが、社会とか経済あるいは政治など人文社会的な予想は、警鐘としては有効でもフィードバックされてブレーキを踏ませ方向転換させる力になる。
- 神へのアップグレードをするときに取り得る道は、生物工学、サイボーグ工学、非有機的な生き物を生み出す工学のいずれかだろうという。最後の工学が人工知能AIである。神性獲得の道は、ヒンドゥー教の神々やギリシャ神話の神々のような欠点の多いヒト臭さに満ちたプロトタイプから始まるのだろう。それがマルクス主義が辿ったように叩かれ踏みつけられしつつ、お互いの肥やしになりあって、ついにホモ・デウスという種にまでaufhebenするのだ。
- ここまでが「人類が新に取り組むべきこと」と題した序文(第1章)である。以下からは第1部で「ホモ・サピエンスが世界を征服する」という題で、「人新世」「人間の輝き」の2章からなっている。ここには含めないが、第2部「ホモ・サピエンスが世界に意味を与える」に続く。最終の第3部「ホモ・サピエンスの制御が不能になる」のこのHPでの紹介はすでに「ホモ・デウス(第3部)」('18)でやっている。
- 「人新世」は著者の造語である。人類が万物の霊長に駆け上がる姿を、狩猟採集民時代、農耕時代、科学産業時代に分けて、人と動植物の相対関係として解説する。重要なのは神の地位だ。狩猟採集民時代のアニミズムは人と他の生命体を対等の立場で扱った。農耕時代に入ると家畜が飼育され耕作により農作物が生産される。人は生命体の支配者となる。理由付けに神が出現する。聖書は農耕時代に書かれた。アニミズムの否定が見られる。インドのいまだに狩猟採取生活を続ける民でも、家畜農耕を覚えると、野生の生命体と飼育耕作の生命体を区別して呼ぶという。後者はアニミズムの対象にならないのだ。
- 科学革命は人間至上主義の宗教を誕生させた。人が神に取って代わった。宇宙すべての万象は、ホモ・サピエンスへの影響に即して善悪が決められる。工業式畜産業はその象徴だ。「生き物はアルゴリズム」という項に、ブタの情感が人間と同列にあることを説明する。ブタはイノシシの時代に生得した情感によって生命を維持し継承してきた。少なくとも哺乳動物には共通の機能である。生きるアルゴリズムの一環を担っている。だがブタの工業的生産は、このアルゴリズムを一顧だにせず、ビーカーで肉を製造しているような姿勢で臨んでいる。メスブタは、幅60cm奥行き2mの横たわることも向きを変えることもできない檻で、ストレスに悲鳴を上げながら、強制妊娠させられては取り上げられ、また妊娠させられて一生を過ごす。最後は食肉になる。哺乳類ではないが、TVで時折お目に掛かる産卵機械化した養鶏場も似たような風景だ。実験動物生命の容赦のない取り扱いもこの至上主義の行き着くところである。
- 「人間の輝き」は命の価値の比較から話が始まる。人の価値を魂に持ってくるのは一神教だ。だがその存在には科学的証明が一切無い。意識ある心を持つのはホモ・サピエンスだけという説もある。魂と違って意識はfMRIによって存在が確かめられ、脳内の電気化学的反応によって生成していることはわかる。心の流れとは感覚から欲望への道である。だがそれは動物にもある。で、感覚と情動は生化学的なデータ処理アルゴリズムとする説がある。ロボットやコンピュータと同じではないか。少なくとも生きるための基本的な心は、無意識のアルゴリズム(言い換えれば本能だろう)ではないか。
- 800億を超えるニューロンが複雑極まるネットワークを作っていて、インプット信号に対して、異なる現象の愛や怒りのような総合的な反応を示すのが意識の流れである。でもこれは言い換えに過ぎない。心と意識の謎はまだ殆ど理解されていない。脳の電気信号の集まりがどうやって主観的経験を生み出すのか誰も知らない。ホモ・サピエンスとホモ・デウスの境目にこの難問が存在する。外部からの刺激に、心は記憶や想像や思考を重ね合わせて反応を決めるように見える。でもそれは何処にある。脳で起こらないことで、心で起こることは何か。生き物はアルゴリズムだとしたら、いよいよ心が宙に浮いてくる。「生命の方程式」の項にこんな議論が延々と続く。
- 動物の心に関する実験がいくつも紹介されている。その中の「賢い馬」の話はどこかで聞いた覚えがある。20世紀初めにドイツで賢い馬が発見された。ドイツ語が分かり初等算術がやれる。研究の結果は、この馬が天才的に質問者のボディランゲージや表情を注意深く観察して、相手が満足する答を出していると云うことだった。擬人化して理解することの落とし穴を指摘している。
- ゾウにせよ猿にせよライオンにせよ、つい先日NHKの「ダーウィンが来た!「学校が決め手!ハイエナ大繁栄の秘密」」のハイエナにせよ、動物にも集団生活を営む種が結構多い。彼らは家族主体の小グループである。人間も狩猟採取民時代には小集団であった。だがヒトは動物と異なり大人数の集団を作ることが出来る。小集団では平等主義が優勢(「家族進化論Ⅲ」('16)には、徹底した分配と交換で権威を抑える仕組みを持った社会に生きているとしている。)だが、大人数になると支配権を握る少数のエリート層の「脅しと約束」のもとで、ときには命を投げ出しても忠誠に働く。ヒトは「想像上の秩序」に乗って「共同主観」的な社会を維持し個々の命を繋ぐ。歴史は共同主観がもろくも崩れ去り反古になった事例を多々経験した。民主主義がこの先その一例にならないとは誰も保証しない。
('19/12/6)
