トンネルの森1945
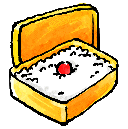
- 角野栄子:「トンネルの森1945」、角川書店、'15を読む。9/26の毎日夕刊の特集ワイドに、この本を中心とした著者の紹介記事が出た。著者は国内の(児童)文学賞を総なめにし、今春には国際アンデルセン賞を授与されたヒトである。私は児童文学は殆ど読まない。ただ彼女が原作のアニメ映画:「魔女の宅急便」は、私のトップクラスのお気に入りで、鑑賞を繰り返している。太平洋戦争の'41~'45のご自身の経験を元に、この「トンネルの森1945」を書いたという。
- 本の表紙には、水彩画で森の中の少女像、扉を開くと、2pいっぱいに鉛筆画で森にたたずむ少女と遠くの大人の人影が描かれている。少女は本の主人公であり著者に重なる。大人は本に出てくる脱走兵らしい。私は著者と同年代だ。正確には著者の方が2学年下だ。だから描かれた少女像には記憶がある。もんぺに防空頭巾。下駄。ずた袋、手製のお人形。トンネルと少女は大分?で起こった痛ましい事件を思い出させる。戦災孤児になって親類に引き取られたが、そこにいたたまれず、洞窟暮らしをして結局は飢え死にした少女の話だ。
- 長い間私は、太平洋戦争の頃の自分をきっちり思い出そうとしたことがない。良い機会だから物語の主人公イコちゃんと対比しておこうと思った。
- イコちゃんは深川で、祖母父母弟との5人家族で不自由なく下町生活を送っていた。ただお母さんは継母で、弟は異母姉弟である。物心が付いてからの継母だから互いに遠慮がある。微妙な継母との関係が言葉使いや、日常生活学校生活への対応などに出てくる。それがさりげなく書き込まれている。父は再婚がイコちゃんの1年生の時で、すぐ召集令状で軍に入隊する。太平洋戦争が始まり、4年生になったとき、病気で父は召集解除を受け家に戻る。
- 東京は大火災を防ぐための街区整理で、建物強制疎開を行う。一家の家は取り壊されることになり、一家は疎開を決心する。疎開先は江戸川と利根川が分かれるあたりにある松田村とある。この物語の主たる舞台である。祖母は長男の世話になると云って、イコちゃん一家とは離れる。イコちゃんとは2度と会えなかった。イコちゃんには、大きな西洋人形を手作りして残していった。イコちゃんが家族を戦災東京へ探しに行こうとしたとき、背中に括り付けていた人形だ。
- 建物強制疎開は私が住んでいた京都でも行われた。御池通、堀川通とか五条通が幅広いのはその名残だと思う。私はそのための疎開ではない。学校単位の集団疎開を親が選んだ。家族の残りは京都在住のままとした。京都が空爆で家族全員が焼死しても、私が血を受け継ぐからという理由だったと後に親は云った。父は独断的なヒトで、ご本人には決まるまで知らされなかった。私は母から手作りのお菓子をたくさん持たされ大満足で、突然のピクニックぐらいの気持ちで出掛けた。疎開先は舞鶴北の漁村だった。
- イコちゃんは村に溶け込もうと努める。土地の訛りをフォローしようとする。私は言葉にはあまり注意しなかった。集団疎開は部落(小字)ごとにあるお寺に分宿する。寮長(1名、派遣学校の女性教諭)、寮母(2名)で10名余りの3-6年生を管理する。始めからこのお寺の寮生は1つの団体として行動したから、個人疎開のように身の置き場を一人で開拓するような必要はなかった。疎開先学校には小学部の上に高等部の2年があって、彼らが威張っていが、敢えて逆らわねば大目にみてくれるといった状況だった。寮生でいじめにあった子はいなかった。
- お寺には和尚と大黒がいて日頃のお勤め行事は欠かさなかった。仏壇の間は住職専用で、その横の大広間が我らの居室寝室だった。お寺さらには村人たちとの関係は良かったようで、村人や地元生徒からの悪い噂はついに耳にしなかった。低学年の子がたまに寂しがって泣いたりはしたが、どこかの集団疎開児のように集団で脱走するような事件はついに起こらなかった。寺の前にちょっとした広場が生け垣で囲まれてあり、お寝小布団が並ぶこともあるが、良い遊び場だった。
- 生垣にチャが植わっていて、和尚さんが紙製の大笊に摘んだ葉を載せて火に掛け、お茶を自製していた。都会よりはマシだったろうが食糧は不足気味だった。いろんな自然の果実を摘んでは食べた。クワの実はよかった。村の子が貴重品扱いにする蜂の子、蚕の蛹はちょっと手に入らなかった。失敗もあった。お寺の藤の大木がたくさん実を付けたので、それを炒って皆で喰ったら、全員下痢して往生だった。とにかく林間学校が引っ越してきたような感覚で、地元をそれほど意識せず、約半年その村にご厄介になった。明日の食い物の心配などしたことがないから、個人疎開とはだいぶ違っていた。
- イコちゃん一家の引っ越し先は孤立した廃屋だった。脱走兵が隠れ住んでいたという噂を引っ越し後聞く。学校には、森の暗い樹木のつくるトンネルを1人で通り抜けねばならぬ。4年生の女の子にとってそれは恐ろしい難関だった。自分に呪いを掛け、時には大声で歌いながら時には森の精に話しかけながら通る。脱走兵は森の中を現に徘徊しているらしい。ハーモニカを吹くのが唯一の慰めらしく、イコちゃんの歌を遠くからなぞったりしてくる。必ずしも脱走兵の存在が立証された風な書き方でなく、イコちゃんのおびえが混じった感覚で物語ってある。
- 太平洋戦争の勝利に関しては、どんなに物資が不足し生活が窮乏化しても、今から思えば信じられないほどの超楽観的ムードが、市民にも村人たちにも行き渡っていた。疑念を挟む言動には、非国民のレッテルを貼られる可能性があった。アッツ島玉砕後ですらそうだった。最後は神風が決着を付けるという。そんなムードが一変するのは東京空襲で一家の東京親族が行方不明になり、ある日の大空襲ののち、松田村からも南の空が赤く染まって見えてからだ。物語のはじめの方に、東京の下町で行われる消火訓練に小さいイコちゃんが一家の代表で参加する姿が描かれている。バケツリレーは私もやった。あんなレベルの火災ではないのだ。雨あられの焼夷弾は、家の下の防空壕の避難民をも焼き殺す。我が家でも、畳を上げて、地下水が湧き出るほどの深さにまで、防空壕を掘った記憶がある。京都は焼夷弾攻撃から外されたので、我ら一族は難を免れた。
- 東京が焼け野原になったという情報は、我ら疎開児童には伝わらなかった。日々は小学(国民学校)生も授業の半分は勤労奉仕で、川の土手まで開墾して、大水の時どうすると古老の顰蹙を買ったりしていた。だが敗戦間近を感じる瞬間が来た。舞鶴軍港爆撃の米艦載機が投下後の「散歩」にやってくるようになったのだ。我らの校舎は赤屋根で周囲では目立つ存在だった。ある日休み時間に突然艦載機が低空飛行で飛来した。私は夢中で廊下の壁影に飛び込んだ。撃たれたかどうかは記憶にない。死んだら何処に行くのだろうと真剣に考えたことを今も記憶している。
- 小学生が機銃掃射の犠牲になる事件は起こっていた。学校には照明弾や米機の残骸など展示してあった。本土に飛来した米機に対する反撃やその撃墜は、いっこうに目にしなかった。我らはすでに戦争の行方に悪い予感を持ち始めていた。
- 東京大空襲以後音信不通になっていたお父さんは、大けがで記憶を喪失していたが、言葉の端から疎開先家族が解り、松葉杖の姿で松田村に生還する。敗戦の日、暗いトンネルに脱走兵の影が無くなる。代わりにトンネル出口に松葉杖のお父さんが立っている。本書最後の一行は、このときのお父さんの「イコ、戦争が終わったよ」だ。我らの家族面会は1回あった。例外なく来るのは母親だったのに、私には父が来た。予感があったので、その時ばかりは強く母に来てくれと手紙したのだったが、父だった。
- 我らには父子らしい会話は殆ど無く、あっても「お指図」「ご訓導」の類で、私は嬉しくなかった。父は周辺の大人との交際に時間を費やしていた。敗戦で家に戻ったとき、母は私に、手渡ったはずの数々の品の行方を聞き正した。覚えがないので私は驚いた。本書に闇米列車取締の話がある。管理統制はうるさく、疎開児童に対しても例外でなかった時代だった。それでも他所のお母さんは、我が子に、人目を盗んで、個人的受け渡しを禁じられていた愛情の品々を渡すのを盗み見していた。母が来てくれていたらこうだったのだろうと、その時は残念に思っていた。
- 敗戦後1ヶ月ほどしてから我らは疎開先を辞去している。村人が送別会を開いてくれた。成人して思い出したらまた来てくれという送辞を忘れなかった。戦後世の中が落ち着いてから私は2回集団疎開先を訪ねた。一度は現役時代に集団疎開児同窓会として出掛けた。お寺は閉じられていた。和尚夫妻は他界して他所のお寺の住職が管理を兼務していた。それでも元集団疎開児童のために、寺を開けてお経を上げてくれた。多くはなかったが村人との交流もあった。二回目は現役引退後の個人訪問だった(「京都から丹後へⅡ」('15))。もう昔を語りあえるヒトとは出会えなかった。その後の家族の歴史を振り返ると、私は集団疎開を経験して、少なくとも独立心に関しては、兄弟よりは早熟だったと言える。
('18/10/08)
