アーレントの政治哲学
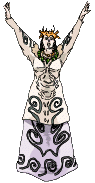
- 仲正昌樹:「今こそアーレントを読み直す」、講談社現代新書、'09を読む。アーレントは幅広く政治哲学を語った人で、ドイツに育ち、ナチスの迫害を逃れて、フランスから米国に渡ったユダヤ人女性学者である。とうに鬼籍に入っている。
- 序章はアーレントの思想概要と本書の姿勢だ。アーレントの思想は複眼思考のつかみどころに苦労する内容らしい。単純明快な原理によって行方を指し示すどころか、かえって当惑混乱させるらしい。軸足が何本もあって複雑怪奇にせめぎ合っている現世世界政治だからこそ「アーレント」だと著者は云いたいらしい。安倍さんの「アメリカいのち」がいいのか、韓流の「煮ても焼いても食えぬ(つきあいきれない)姿勢」がいいのか。書評らしき記事の多いこのHPにも多分にそのけがあるが、本書は「著者がアーレントになりすまして」一席ぶつ話にしているとある。
- 第1章は、本書へのきっかけになったNHKの「100分de名著 アーレント"全体主義の起原"」が中心の話である。"全体主義の起原"は本HP最新の記事:「ビルマの歴史」の英国側の信条を語る基礎としても参考になるお話だった。対談のゲストは本書の著者である仲正昌樹・金沢大教授である。第1回が「異分子排除のメカニズム」(元本の第1巻「反ユダヤ主義」)、第2回が「帝国主義が生んだ"人種思想"」(第2巻「帝国主義」)、第3回が「"世界観"が大衆を動員する」(第3巻「全体主義」)、第4回が「悪は"陳腐"である」だった。
- ただし第4回は「イェルサレムのアイヒマン」について語る。アイヒマンは収容所へのユダヤ人移送計画の責任者。2次大戦後南米に家族と共に逃げていたが、イスラエルの特務機関により逮捕され、イェルサレムで裁判にかけられ絞首刑になった。「悪の権化」であるはずの彼は、実際には、与えられた命令を淡々とこなす陳腐な小役人で、自分の行いの是非については全く考慮しない徹底した「無思想性」を示した。
- 国民意識民族意識に目覚めている、でも混乱期にあって不安を抱える無思想性大衆の受け皿になるのが、全体主義の世界観政党で、ナチス(やソ連共産党)が格好の例だ。緻密だが何か狂った構築の世界観であることは、第1回、第2回から縷々導かれた通りだ。人は、意見を持ち行動する市民から、市民運動の結果としてそこそこに実利を獲得した結果、難儀で怖い事は誰か(政党とか組合など)に依託してしまって大衆になる。彼らは首尾一貫性のある虚構(空想)に嵌められやすい。その虚構には現実が、第3者的にはねじ曲げられたご都合的な独自の解釈とともに顔を出す。それが大衆を嵌める有力な罠になる。
- 「イェルサレムのアイヒマン」も「全体主義の起原」も座り心地のよくない後味の悪い著作である。「自由意志を持ち、自律的に生きており、自らの理性で善を指向する主体」という西洋伝統の人間像は、アイヒマン裁判では自己矛盾に陥った。ナチスの歴史も与えられた環境の大衆の必然!に近いと言う論理を生じ、断罪どころではなくなる。アメリカからアフリカやアジアの席巻に乗り遅れたドイツは、東欧に向かっての帝国主義植民地主義の拡張など考えずに、指をくわえて先発のイギリスやフランスを眺めておったらよかったんだというのでは、話にならぬ。彼女はそこで西欧的な「人間像」の源流を探究しようとする。第2章は彼女の著作「人間の条件」を中心に展開する。
- 資本主義の発展で、経済的利害を中心に画一的に振る舞うようになった市民たちは、思考停止し、自分とっての利益を約束してくれそうな国家の行政機構とか世界観政党のようなものに、機械的に従うようになっていく。これはアーレントが描いた全体主義の母胎としての大衆社会の姿そのものだ。社会的領域(公の場に私の場が入り交じった、マス・メディアが「社会問題」として取り上げるような内容)が拡大し続ける近代の市民社会は、ほぼ不可避的に大衆社会的状況を到来させることになる。この大衆社会は全体主義体制を生み出す潜在的可能性を秘めていると書いてある。
- アーレントの近代市民社会ことに大衆社会に対する見方はきわめて悲観的だ。そう言われると、私には、民主主義国の衆愚政治、非民主主義国の極端偏向がすぐ頭に浮かぶ。
- ヒューマニズムに基づいて万人に普遍的な人権を付与し、民主主義の拡大を図ってきた西欧の市民社会が、大衆社会的な状況に陥って、政治的に不安定化し、全体主義の母胎になった。こうなれば、おそらく民主主義を殆ど呼吸したことのない大衆社会と政治の質は外見では同等になるだろう。アーレントは、曲がりなりにも公の立場で複眼思考が出来たギリシャ時代のポリスの市民層から説き起こし、人間性に過剰な期待を寄せるヒューマニズムはさておき、全体主義に通じる「思考の均質化」だけは防ぎたいと云っているのではないかと著者は考えている。
- 自由とは構成すべきもので、フランス革命派のような、解放によって自然状態=生来のエゴイズムに戻ることではないとアーレントは考える。史上数ある革命の中で、米国の独立は優れた構成=憲法=国家体制に到達した。憲法は容易には改正できない制度の下に、安定して公的活動の自由な空間を保障し、民意の複数性を容認確保した。アーレントにとっては公/私の区別が大切だ。
- 公的活動とは、公的領域に於いて各市民=活動主体が、他の市民にアピールするために、良き市民としての「仮面」をかぶって「活動=演技」することだ。「人格」は、「公衆」の目を意識した活動に於いて演ずべき「役割」で、公衆の眼差しに晒されない「私的領域」の素顔ではない。
- インターネットの炎上事件などは、匿名の私的動物感情の無責任発言の寄せ集めで、公的活動からはほど遠い場合が多い。近頃はあまりマス・メディアのニュースにならなくなったのはよい傾向だ。このHPの著者名「志野原 生」はもともとはペンネーム、今はハンドルネームだから匿名だ。でもその人の本名は知る人ぞ知る。掲載はもうほぼ四半世紀と永いから、かなりの範囲で知られているはず。そんな場合は公私半々というのかな。
- 全体主義は思想の均質化と表裏の関係にある。アーレントの唱える複数性を増殖させる活動の真意は、全体主義の脅威の排除にある。活動と観想=理論は車の両輪の関係だ。彼女は観想的生活の開明を後期の最重要課題と位置付ける。その中心著作が「精神の生活」である。第一部「思考」と第二部「意志」までは書き上がった。だが第三部「判断」を未完にしたまま逝去した。幸い「判断」の方向性を示唆する「カント政治哲学講義」を遺している。
- 著者はアーレントに成り代わって「精神の生活」を補完し、著者の見たアーレント像を総括する。「精神の生活」の紹介は本書の第3章までよりは遙かに純粋哲学的で、私には要約出来るほどの腕はない。この第4章は「傍観者」ではダメなのか?と、いたって砕けた表題になっている。その中から美味しそうな文を掻き集めて、私の感想文を締めくくろう。
- 各人がいかなる物理的制約も受けることなく、自由にコミュニケーションできる「公的空間」さらには「公的空間」を舞台裏から支える「私的領域」をも備えた「政治的共同体」が、多元=複数性のある健全な社会を作る。そこでは他者の視点から自己の精神の働きをチェックし続けることが出来るはずだ。
- なぜなら観客=注視者は現に活動している人たちよりも事態を公平に見ることができ、注視者の視点が活動者の中にも埋め込まれるようになるから。直接的には表舞台に加わらないという意味では、観客は第4章の表題に含まれる「傍観者」なのだろう。でも彼らは様々な視点から問題を注視している。それが政治に複数性をもたらす。アクターになろうとしない人を、安易に卑怯者呼ばわりすべきでない。
('17/10/01)
