アメリカ先住民史Ⅲ
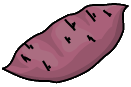
- 以下はチャールズ・C.マン:「1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見」、布施由紀子訳、日本放送出版協会、'07の、第3部とエピローグの章に対する私の感覚である。
- アメリカ中央部を流れる大河・ミシシッピー川の流域に先住民は文明を育んだか。だだっ広い草原地帯に部落が点在する程度の原始的過疎地域ではなかったか。第3部は「人のいる景観」という題で、まずアメリカ平野が先住民の焼野原管理をする自然牧場だったという、意表を突く説明から始まる。
- 欧米型の牧畜業者は家畜を囲いの中で育てるが、先住民は囲いを造らず、家畜を造らず、ただ森や草地を焼き払って、野生の草食動物に適切な食草が育つ環境を造るだけだという。春日大社の三笠山(若草山)には春に山焼き行事があるが、神鹿の居住環境整備の意味があるだろう。焼畑農業を野生動物牧畜業に応用したようなものなんだと著者は云いたいらしい。だから始めて訪れた欧米人が描写した先住民の居場所の近辺はもう人工的景観だったのだ。その彼らが居所を転々と変えて行く。自然の復元へのサイクルは長い。世紀の単位だろう。大陸の中央部は、インディアンの野焼きと自然のせめぎ合いで出来た景観だ。
- ミシシッピー川流域には万を数えるマウンド遺跡が残っていた(今はブルドーザーで潰されて形を遺さなくなったものが多いという)。中南米遺跡にもマウンドという言葉がしょっちゅう出てくるが、日本の大型古墳のようなものらしい。意義は場所によって異なるだろうが、宗教的に神聖な場所であることには代わりがない。集落があった証拠である。ペルーではマウンドから地元民の盗掘で出土した人骨が、ゴミ捨て場にうずたかく積まれていたというような記事もあった。
- セント・ルイス近くのミズーリ川川辺にあったインディアンの都市カホキアは、ギザのピラミッドより大きい4段の土造りのマウンド(しょっちゅう洪水に見舞われる氾濫原にありながら今日まで原形を保てるだけの土木工学的工夫が成されている)を中心とする120基のマウンド群が並ぶ、人口1.5万以上、面積13平方kmという流域第1の1100年頃の大都市で、船便による交易の中心地として栄えた。
- アメリカ大陸では、牛車のように荷車を家畜に引かせるような運搬手段は発達しなかった。日本の伝統的な藁葺き農家のような木造の家が建ち並びと書いてある、トウモロコシ畑の灌漑や運送小舟用の運河が走っていた。復元図はなるほど、京都のかやぶきの里(「丹波路」('10))のような雰囲気である。絵師は逆にかやぶきの里を見て復元図を描いたのではないかとさえ思う。
- カホキアの頃になると狩猟対象動物が減少し農耕の比重が増大した。森、畑、果樹園のバランスの取れた管理地が広がって行く。果樹園も結構大切だった。私は青森の三内丸山遺跡を思い浮かべた(「縄文文化の扉を開く」('01))。主食がクリで穀類のヒエも栽培されていた。インディアンはドングリも食っていたとある。「科学の常識2」('14)には、関東に残っている(縄文期の)考古学的証拠によると、ドングリは水で晒しあく抜きし、練り上げて団子状にし、焼いて食ったという。我らの御祖先と似たような生活をしていたと思うと親近感が湧く。カホキアには川筋の改修跡もある。だが洪水と大地震と内乱でカホキアは衰退に向かい、1350年頃には都市は無住の地に変わる。これ以後はカホキアほどの大都市は生まれなかった。
- 第8章の後半はマヤ文明だ。メキシコ湾に突き出たユカタン半島のマヤ文明遺跡は、アメリカのクルーズ船の格好の訪問地になっていて、TVのクルーズ紹介番組にしばしば登場する。実現しなかったが、かって22万トンのメガシップ進水が話題になった頃その航海に乗船を申し込んだことがあった。一度はこの目で見てみたいと今も思っている。ユカタン半島のハイライトはカーン(カラクムル)の石造ピラミッド遺跡だ。今でこそ公園化され観光客を受け入れているが、発見は半世紀ちょっと昔で、著者が1980年代の初めに現地視察を試みた頃は、食事は喉を通らず、寝台は吸血虫(ノミ?シラミ?)の巣で、停電で真っ暗な宿舎での生活だったと述懐してある。
- カラクルムは人口57.5万広さ60平方kmの都市国家で、中心の町には5万人ほどが住んでいた。マヤの最盛期は200-900年。それ以降は急激に記録が途絶え20世紀に発見されるまで忘れ去られた。マヤの絵文書は悉くをスペイン人が破棄してしまい、今は4冊を残すのみと云う。カラクルムのほかにもう1つの有力都市国家があって相争った話が出ている。マヤの崩壊原因には過剰人口、自然資源の過剰利用、干魃などが上がっている。
- 第9章の表題はアマゾニアだ。下流地帯では4千年前頃にはすでに農耕が始まっていた。少なくとも138種の作物の栽培があったという。中心はキャッサバ(澱粉のタピオカの原料)だった。このHPの「アマゾン河の博物学者」('97)は1863年が初版の11年に亘る原著者のアマゾン記録に対するコメントである。当時の先住民の生活とか精神活動についてかなり触れている。「ブラジル」('12)では、先住民人口はポルトガルが「発見」した時は200万人はいたとしている、「グレートネイチャーⅡ」('13)はアマゾン河を遡りペルーに達する現代の探検隊のTV報告である。本章冒頭にはその逆を通り、「アマゾン女族」を報告した1541年のスペイン探検隊の記録の真偽(そんなに人が住んでいるはずがない)が論じてある。
- 1580年頃では「アマゾンの住民は数を知らず、総督や政治家を言い表す用語を持たず、従属も貧富も知らず、服も農業も金属も持っていない」と思われていた。18世紀中頃には「彼らをキリスト教に改宗させるより先に、まず人間にしなければならない」と云った学者があった。1970年代の考古学会では、乾期2km幅の川が雨期に50km幅にも増大する鬱蒼たる原始熱帯雨林地帯では、先住民族人口は千人が上限で、焼畑耕作レベルの文明に到達するのがやっとだと言った意見が支配的であった。
- 1990年代に古い絵文字のある岩絵洞窟が発見され貝塚が見つかり、その下に12千年前の遺跡が出た。中州遺跡の科学的調査が、そこが優に10万を超える人口の千年を超える国家だったと教える。その頃から1000年そのまんまの生活者というイメージが疑問視され出す。
- Wikipediaは、ヤノマモ族は「南アメリカに残った文化変容の度合いが少ない最後の大きな先住民集団である。」としている。ブラジルとベネズエラの国境あたりに住む。本書には、彼らは、コロンブスが上陸したとき、アマゾン盆地に定住し、村落をつくって暮らしていた。やがてヨーロッパ人が持ち込んだ伝染病と奴隷狩りによって村はずらずたに引き裂かれ、多くの者がオリノコ川へ逃れて狩猟採集民になった。(培った文明から切り離され、原始の時代へ押し戻された。)彼らは17世紀に鉄器を手に入れ、それを使って半遊動民的な狩猟採集生活から(再び今日に見られるような)農耕生活に戻り、村落をつくってほぼ定住するようになったとある。狩猟採集で生き延びられた理由の1つに、モモミヤシがあった。インディオが時間をかけて造った、手間のいらない栽培種らしく、「妻と子の次ぎに大切」に重宝されている。
- 先コロンブス時代の先住民の農耕は焦がし畑耕作で、17世紀以降の(高能率の鉄器による)焼畑耕作とは、土壌を痩せさせないという意味で、徹底的に異なるという。熱帯の多雨地帯の土は、長期に亘って直接雨に叩かれると養分を失った貧しい土壌になる。インディオが何百年に亘って耕作した土地は、多数の土器破片と木炭破片が出てくる黒土(テラ・プレータ)で、農業に適した肥沃な土壌に改造してある。彼らは野焼きを不完全燃焼に終わらせ、有機物残渣混合などの工夫を加えてこの大地を手に入れた。近年多くの集落遺跡が発見されているが、その人口保持がこのテラ・プレータと言う森の改造結果によると云えるらしい。
- 第10章はこの本のここまでの著者の結論である。コロンブスが到着したころ合衆国本土の2/3では農耕が始まっており、灌漑と段畑のあるトウモロコシ畑が見られた。集落からは遠くない位置に、総数6千万頭というバイソンがインディアンの狩猟対象になっていた。メキシコ盆地とユカタン半島のインディオは土地を農耕に適した人工的環境に変えていた。アンデスの西斜面には段畑や用水路が広がり石の街道が走っていた。農耕はアルゼンチンとチリ中央まで広がっていた。アマゾン川流域のおそらく森林の1/4を耕作地や実の採取できる人工林に転換していた。
- 動植物界が微妙なバランスの上に成り立っており、僅かの変化が大きな変動要因になることは、現代では常識である。表題の通りの人工の原生自然であった西半球は、人工の頂点に立っていたインディアン、インディオの消滅、ポルトガル系の進出で環境改悪の方向に舵を切られている。
- エピローグの第11章にはさらに驚くべきお話が書いてある。アメリカの自由平等気質がインディアンの生活姿勢から大きく影響されたとする話だ。コロンブス到着前後200年ほどはおそらくリオ・グランデ川以北では最大の先住民政治組織であり軍事同盟であった東部の部族連合が、大いなる平和の法を持ち、その117の条項が、西欧的な意味ではないが、当時の欧米人が驚くほどに、個人主義的自由主義的民主主義的姿勢に貫かれているという。接触した人々の証言もいろいろ上がっている。俄には信じがたいお話ではあるが、一読の価値はある。
('17/06/09)
