近代天皇像の形成Ⅰ
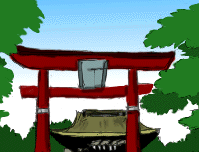
- 安丸良夫:「近代天皇像の形成」、岩波書店、'92を読む。目次を見ると(見なくても当然だが)先に感想文を上梓した、同じ著者による「神々の明治維新」と重なり合っている部分が多いと感じさせる。「神々の明治維新」は新書版で、一般教養書スタイルだったが、それでも難しい漢語概念語が結構多く苦戦した。今回は単行本でより専門的なのだろうから、読みこなせるかどうか自信がないが、図書館の貸出期間延長が認められた唯一の書だったので、半自動的にこの本を読むことに決まってしまった。本書には小さい字の註書きがたくさん入っているが、飛ばして読むことにする。老眼に辛いという理由だ。
- 「あとがき」から先に読んでみる。多分と思っていたが、先生は私とは同年配で、私とは遅生まれか早生まれかの差しかないと知った。富山の農村出身で、その実家で過ごした幼少の頃の思い出が出ている。この年齢になるまでいろんな人と知り合ったが、概して私生活を開けっぴろげにして語る人が友として残っている。私に対して事細かに私生活に踏み込んでくる割に自分を紹介しない人とは、たいてい浅い付き合いで終わってしまった。飾り気なく自分を表現する人は、何か聞く方読む方に安心感を与える。安丸先生はどうもその部類のようだ。先の「神々の明治維新」では本願寺派の民衆への浸透ぶりが語られていたが、経験に裏打ちされた話だと分かる。先生の実家が東本願寺派で、実家の信仰心の篤さは私の家(真言宗)よりかなり上だと感じさせた。
- 本書は、近代転換期における天皇制をめぐる日本人の精神の動態解明に重点がある。その時期は明治維新を挟んでの約1世紀、18世紀末から19世紀末あたりだ。日本の社会は内なる動揺に加えて、外からのきわめて強力な圧力に脅かされていた。ついには日本社会の秩序が崩壊するのではないかという、強い不安と恐怖が存在した。体制的危機意識が国家民族意識を刺激し近代天皇制をもたらす。近代天皇制に対し4つの基本観念が提示されている。1.万世一系の皇統=天皇現人神と、そこに集約される階統性秩序の絶対性・不変性 2.祭政一致という神政的理念 3.天皇と日本国による世界支配の使命 4.文明開化を先頭に立って推進するカリスマ的指導者としての天皇。
- 1と2については「神々の明治維新」でかなり議論された。中心的役割を担うのが国家神道だ。国家神道は儀礼をもつが体系立てられた教義を持たない。明治の神道国教主義は教義の体系化を試みたが、成立せず、教義を持った宗教としての神道は教派神道各派に委ねられた。国教としての神道が祭祀儀礼へと後退したことで、近代日本には曲がりなりにも、ヨーロッパ各国が要求して止まなかった信教の自由が成立した。
- 天皇家は応仁の乱前の15世紀中頃には、世俗的権力はおろか叙任権や祭祀権まで失っていた。それでも権威的存在ではあり続けた。戦国時代には戦国武将のニーズの高まりもあって権威筋として評価は高まった。和平交渉の仲立ちに朝廷の名が役立つような例が見られる。信長が自らを神に任じながら、右大臣の官位を叙任され、秀吉は太政大臣、家康は征夷大将軍を朝廷から与えられている。権威は認めているのだ。徳川幕府は朝廷の監視管理体制を強め、紫衣事件を経て天皇は皇居からは出られぬようになり、朝廷は儀礼的権威のみの逼塞状態になっていった。
- 権力交替を知徳、道理、名分の喪失に結びつけるのが儒教の立場である(「儒教とは何か」('16))。江戸をリードした儒者は、必ずしも日本を代表する知識人ではなかったが、権力側の理論的支柱となった。彼らに云わせれば、朝廷が治政の実力を失ったのは、武家側に責任があるのではなく、朝廷側が、腐敗、無智、驕奢、柔弱で尊大と、権力に相応しい能力を失ったためとする。後醍醐天皇や南朝側忠臣に厳しい批判を行っている。確かに今思い返せば、皇国史観に基づく南朝史の独善的解説はまともでなかった。秩序原理としての天皇を認識しているが、実質は将軍=国王で、朝鮮との外交関係に於いても、将軍を双方で「日本国王」と称した。
- 荻生徂徠の頃の上総国の淫祠が書き上げてある。不受不施派(日蓮宗の異端一派)、業平天神、小六明神、根津権現、大杉大明神(次段に別記の流行神(はやりがみ))。禁令があるのにもかかわらず異端邪説がはびこる。これは道心者(乞食坊主)、乞食、非人、遊女、無宿、盗賊、博徒、通り者(通り魔、通り悪魔:気持ちがぼんやりとしている人間に憑依し、その人の心を乱すとされる日本の妖怪(Wikipedia))などのすでに秩序逸脱的な人々の存在と通底し合っている。彼らは社会秩序を根底から脅かす威力を秘めた存在である。体制側の思想家が求める天皇の重要な役割は邪祀の影を清める正祀で、天皇の御勤行が天子の御家職なのであるとする。そんな思想から「神々の明治維新」に通じる祭祀一致が生まれ、儒者の中には朝廷から仏教色を一掃すべし云う議論が出ている。朝廷の衰微を「過半ハ崇神佞仏(ねいぶつ)ノ惑ヨリ事起」ったとした。朝廷と仏教の結びつきに秩序紊乱(びんらん)の根源を求めた。
- 民俗信仰は世俗権力の作る秩序の範囲内にある限りは、権力側の関心を呼ばないが、ダイナミックな展開で問題的な存在になると介入が始まる。大杉大明神は常陸から上総、下総を経て江戸に届いた流行神で、祭神は弁慶と並ぶ義経の家来、常陸坊海尊の御霊。御輿が村次に送られて江戸では華麗な行列になり、「出ぬ町は恥」(町組単位の祭礼形式)とばかりに増え、笛太鼓に合わせて人びとが踊り騒いだ。おかげまいり、ええじゃないか、御鍬祭り(豊作祈願祭)、豊年踊り、砂持ち(神社敷き砂入替行事)などでも祝祭的熱狂が起こり、簡単には制御できないエネルギー発散が起こる。
- 祭りの中核的な担い手は若者組であった。彼らの中にはアウトロー的行動力があり、秩序に対する不満のはけ口を求める人物もいただろう。狙われた金持ちにだけお札が降り、彼らは大量の酒・食物を振る舞わされる。暴走を食い止めるべく村役人や神官は降って湧いたお祭りに日限を2夜3日という風に区切る。だがお札が広域に降り、止めようのない爆発的流行になる場合が起こる。幕末の「ええじゃないか」の狂乱風景はときおり時代劇に、どちらかと云えばコミカルな背景として出てくるが、時代に生きた人々はあれを世情不安の象徴として捉えていたはずだ。
- 社会変革期の祭礼をめぐる対抗に「オージー的高揚」の重要性を指摘したのが、堀一郎である。オージーをWeb検索してみた。「日本のシャーマニズム-堀一郎『日本のシャーマニズム』を中心として-」に、オージー=人格の転換、社会秩序の倫理的拘束が一時的に破棄されるような集団的恍惚と興奮の状態としてあった。暗闇祭り、押合祭り、喧嘩祭り、尻ひねり祭り、暴れ祭り、悪口祭り、種貰い祭りなどが原型である。物騒で怪しげで興味津々のお祭りばかりだ。暗闇祭りと種貰い祭りは同じような祭りで、京都・宇治の県(あがた)祭りが有名である。今はもう暗闇で御輿を担ぐ程度であるが、昔は暗闇で相手構わず男女が交合してよい祭りであった。妊娠すれば「神から子種をさずけられた」とした。県神社は大きくもないお社で、今は、昔に爆発的熱狂などあったとは信じられぬ佇まいである。
- 近世社会を脅かす反秩序の契機が異端のコスモロジー構想にも見られる。大塩の乱の大塩平八郎は天皇の政治社会における役割を重視した神儒一致論だったという。前橋藩の農民闘争にかかわって永牢処分を受けた林八右衛門は「上御一人ヨリ下万人ニ至ルマデ、人ハ人ニシテ、人ト云字ニハ別ツハナカルベシ。(当時にしては凄い発言である。)最トモ貴賤上下ノ差別有リトイエドモ、是政道ノ道具ニシテ、天下ヲ平ラカニナサシメンガ為ナルベシ。(これまたもの凄い。)」と書き記した。儒仏を神道的に表現したとされる。江戸時代の異端には三教一致論的性格を持つことが多いと指摘されている。精神史は大枠は伝統主義的であるのにもかかわらず、異端性が包蔵されていて、正統を脅かすといった過程を辿る。
- 著者は、本居宣長から平田篤胤を経て藤田東湖の水戸学に至る系列に、世の危機意識の構造を捉えている。水戸藩は東湖の死後の内紛で多くの人材を失い、幕府や他藩への影響力をなくした。しかし維新政権の祭政一致や神道国教主義の理念は、水戸学や国学が呼び起こした幕末期の危機意識の構造の延長にある。多くの人々の不安や恐怖に理論的バックボーンとして登場し、それが時代潮流となって維新に向かわせたと云える。イギリス人水戸藩領上陸事件で外交処理に当たった会沢某の「新論」が多く引用されている。私には「しっちゃかめっちゃか」な議論に映るが、当時の対外的危機意識の代表的表現と受け止められる。引用してこのエッセイの終わりにする。
- 「日本は天に近くてこの地球上では「首」(頭)にあたる位置にあるから、幅員は小さいが、万世一系の天皇の存在において世界に秩序を与え「万方に君臨する所以」を表しており、・・」の国体論から祭祀論に展開し「天皇は大嘗祭をへることで・・天照大神と一体の現人神となる」とある。日本の古典と儒教の古典を牽いて論じてあり、神儒一致説と云える。神儒一致の秩序が邪説の害により乱れてきた。まずは胡神=仏の一向宗だったが、危機意識を一挙に急迫させたのはキリスト教だった。武力がダメなら民心煽惑でくる。一旦民心を捉えた宗教が、権力の立場からしてどんなに手に負えない厄介者か。宣長、篤胤、水戸学者はちゃきちゃきの権力側保守主義者であった。
('16/04/22)
