日本神話Ⅰ
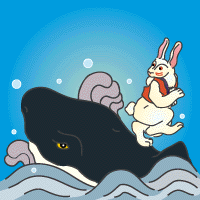
- 上田正昭先生(京大名誉教授)が亡くなられた。読売は先生の業績を上田史学と総括していた。先生の「日本神話」、岩波新書、'70を市立図書館から借り出してきた。かなり紙が黄ばんでいる。活字も私には小さくて読みづらい。序文を見ると、本居宣長、平田篤胤あるいは新井白石といった過去の碩学たちの、基本原典たる記紀への論評が、原文の文語体のままで解説無しに次々と引用されている。私の実力でこの本が読めるだろうかと一瞬迷った。私の世代、父母の世代は神話即史実の国史教育を受けた。でも明治の祖父母の世代は「神代ばくたり、ついに知るべからず」と教えられたようだ。
- ギリシャ神話やローマ神話は比較的聞く機会が多いが、それらを深く知っているわけではない。それでも私には、日本神話は、アマテラスオオミカミの子孫に位置付けられた天皇体制と出雲族を初めとする地方部族の隷属を正当化する政治的色彩が強い点で、範疇を異にする神話というイメージが強い。現代ですら歴史を政治家がご都合に合わせようとする。南京虐殺事件、慰安婦問題にも多分にその流れを感じる。ソ連では人類初飛行はライト兄弟ではなく、なんとかスキーと言うソ連人だった。記紀が、古代体制の正当化と言う目的を持って編集されている以上、当然地方は中央に向けて脚色されると思わねばならないだろう。神話上は征服側が被征服側に対して行う神たらしである。仏教には、バラモンの神がさほど重要でない地位を貰って定着している例が幾つもあるようだが、日本神話の世界も例外ではない。
- 素朴な民衆の神話がある。文字になる前の前の姿は推し量るべくもないが、銅鐸に描かれた絵とか出土状況から暗示される祈りが感じられる。神話は口誦で伝承される。口誦は語部が受け持つ。宮廷にも存在した。天皇の即位儀礼と関係がある大嘗祭の例が出ている。諸国語部が古詞を奏上する。この寿詞はすでに政治的な性格と役割を帯びるものに変貌していた。詞に舞が添えられる。舞はbody language。語部の古詞奏上の面影が吉野南国栖(古事記では国主)の浄見原神社の奉納歌舞に残っているそうだ。口鼓を打って詠い舞うそうだ。もともとは土地の神へ大御酒を捧げ奉ると詠うのだが、天子への捧げ物に詞は変貌している。歌舞の上手が宮廷に集められている。出身地は祝賀に出た語部とほぼ同じだという。
- 書いてはないが、神主の祝詞なんかも文字記録以前の神代を伝える、匂わすものがあるのだろう。日本人は一神教地域と違い自然発生的宗教を維持し続けたから、民族の連続性と文化の連続性を、並列的に維持することが出来たと云えるのだろう。このHPの「北欧神話」('15)にキリスト教以前の神話の燃えかすが整理してあるが、はて今の北欧人は、自分に繋がりのある話として受け止めているのだろうか。
- 記録化技術は万葉文字で一段落することはよく知られているが、そこに落ち着くまでの試行錯誤ぶりが簡明に描写されている。国字がないから漢字の音を借用する。万葉時代に入ってもヤマトは山常であり八間跡だった。地名人名は音の借用の典型である。一方では漢字の意味から訓を取る。5世紀末という古い時代の出土刀剣の銘に「治天下」とあり、「天(アマ)の下(シタ)を治(シラ)しめる」と読ませるそうだ。現在の河内は大和の西だから西(カワチと読む)を当てはめた。古い時代ほど文字の書ける人はおらず、書記は中央も諸国も帰化人や渡来人の技能集団に負うことになる。彼らの持ち込んだ中華思想で我が国に定着したものもある。倭人の倭は中国四辺を野蛮視する中華思想の現れである。
- 閉ざされた天の岩戸の前で踊るアマノウズメは、「神がかりして、胸乳をかき出で裳緒をほとにおしたれき。」(古事記)だったという。天の岩戸の神話は宮廷の招魂(鎮魂)祭礼の投影である。天武天皇の病状回復を願って11月の冬至に執り行われたという記事が初見だそうだ(日本書紀)。冬至は太陽神アマテラスオオミカミの力がもっとも衰える日。その活力の復活と皇祖神の位置づけのための宮中秘儀で、宮中には鎮魂呪法専用の建物「御窟殿」があった。
- アマノウズメは巫女である。天の岩戸(窟)は神の依り代に繋がる。依り代が本殿になるのは後の世で、古代では巨石や神木だ。三輪神社は三輪山がそれで、石上神宮でもかっては境内に「神ふる山の瑞垣」が聖地であったという。諏訪神社の御柱も依り代だそうだ。映画「羅生門」に巫女が神がかって死霊に証言させる場面がある。「羅生門」は平安末期に時代設定されている。現代の神社の巫女は、お神楽で神のご降臨を願うエンタテイナー役だ。さすがにもう神がからない。神まつりの原点は神迎えをして神の託宣をあおぐことにあった。巫女はその仲立ちとなる重要な立場であった。
- 巫女は神さま側で、そのお告げに対して人の立場から一定の判断を下す、具体化に関わる審神者がいた。こちらは男性である場合が多かったらしい。魏志倭人伝の2世紀中頃の卑弥呼女王は、年老いたオールドミスで、審神者1人と1000人の巫女を仕えさせて、神がかりのまつりごと(政治)をやっていたとあるそうだ。私は魏志倭人伝など、中国からは遠く離れた日本の噂話程度かと思っていたが、ときおり引用される内容がなかなか具体的で、史家が重視するのもやむを得ぬ仕儀だと思った。
- 天皇家を頂点とする有力氏族が権勢を振るう時代(弥生中期以降)に入ると、血縁関係、従属関係、相続者問題などが絶えず社会の緊張をもたらす。その確認は首長が逝ったときは喫緊の問題になる。葬儀(もがり)がそのための絶好の場を提供した。血族や各階代表者が読み上げる弔文(しのびごと)が立場表明の機会になった。日本書紀には天皇葬儀における立場表明の内容が書いてあるという。死者の「たま」は直ちに「もの(もののけのもの)」(死)の世界に入らず、しばらくは彷徨っているが、「たまよばい」することによって屍体に呼び戻し、鎮魂によって生者の「たま」と「魂触(たまぶれ)」するのだ。弔文は、今日のような冥福をお祈りしますといった儀礼だけでは納まらない仕組みになっていた。埋葬を終わってとむらいあげになった後でも、大王などの力ある死霊は甦ってくる。祖霊への昇華である。
- 記紀の編纂は壬申の乱を契機にしている。皇統の乱れは乱世に通じる。大宝律令は発布されたが、実行を見たのはその1つ2つに過ぎない状況だった。豪強の家が土地の私有化を目論んでいる。大和政権の安定化のための中央史観の調整が必要だった。編纂者の人選に皇子や宮廷官僚が選ばれている。地方の神話よりも高天原の神々を本流とする「皇室の御魂」を中心とする神話に造られて行く。微視的には記紀には結構食い違いがある。日本書紀には海外も含む引用文献が記載され、倭を排して日本を名乗る国際意識を持った史書になっている。
- Wikipediaには律令時代の風土記は56篇あったように書かれている。ほぼ完全な写本が伝わっているのは出雲国風土記のみで、一部欠損状態のが4本、あとは後世の書物に逸文として引用された一部が残るのみである。欠損状態のもの4本と出雲国風土記の間には大きな相違点がある。前者の編纂は中央から派遣された官僚の手になったのに対し、出雲国風土記は土着の豪族出身者が行った。出雲国風土記には土地本来の神話が残ったという意味で貴重なのだ。
- オオクニヌシノミコトに対する記紀神話では、彼が従順に服属を誓い、大社建造と引き替えに引退、国譲りをする(日本書紀)とあるが、岡本雅享氏(https://www.keiho-u.ac.jp/research/asia-pacific/pdf/publication_2010-03.pdf)によると、出雲国風土記では「(天照大神と同様に)天の下造らしし大神(命)」で、出雲国を譲らないし、隠れもしない。自分が造り治めてきた(周辺の)国を天つ神(征服部族側の高天原の神)の子孫に譲ると表明する一方、出雲の国だけは、自分が鎮座する国として、青垣山を巡らし、治め続けると宣言している。本書には出雲国風土記関連原文の読み下し文が掲載されているが、悲しいことに私には十分に理解できなかったので、岡本氏の論文を引用した。本書は教養書にしてはレベルが高い。
- 元に戻るが、国譲りの話は、他部族の神を配下に取り込もうとする覇者の意図がよく分かる神話改竄である。さらに出雲国風土記だけの神話、取捨選択の上関係を歪められた出雲の神々などが浮き彫りにされていて、中央の政治的意図が明確に感じ取らせる。スサノオノミコトは、記紀ではアマテラスの弟君で、たいそうな「ワル」に仕立てられているが、風土記では平穏な(岡本氏)高天原の神とは血縁など無い存在だ。記紀ではオオクニヌシノミコトはスサノオノミコトの子(孫)で、アマテラスとの血のつながりから国譲りが当然という論理に持って行くが、風土記では両者の血縁など全く触れられていないという。
('16/03/21)
