女ことばと日本語
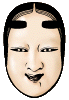
- 中村桃子:「女ことばと日本語」、岩波新書、'12を読む。女ことばを聞く機会はめっきり減った。それに使うのは中高年の女性で、娘盛りの女や少女が使うのを近年聞いたことがない。車中で「あいつ」「こいつ」の男言葉で会話する女子高校生を見ても、あまり奇異に感じなくなった。でもたまに上品な女ことばに出会うと、なんと耳当たりのいい日本語だろうと聞き惚れる。本書は日頃の気がかりを解いてくれそうだ。
- 序章の最後に、女の言葉遣いが規範の対象になるのが鎌倉・室町時代からだとある。平安期の宮廷女房文学の影響力を物語るのだろう。でも文学の言葉遣いは必ずしも話し言葉ではない。「あら、まあ、あたし、わ、よ、ね、かしら」なぞが女ことばと認識されるのは明治以降の近代からで、女ことばが「日本語の伝統」になったのは、第二次大戦中であるとある。そんな歴史はまったく知らなかった。
- 「学問のすすめ」(本HPに同名の記事あり)では自由民権思想が高らかに謳われている。福沢諭吉は先端を行く思想家であった。欧米の女権拡張は諭吉が留学した時代に重なっているはずだ。その精神的基盤としての、例えばルソーの「社会契約論」は明治維新の100年前に出ている。だが諭吉は、存外に世に知られていないらしいが、女権については伝統の男尊女卑からほとんど出ていなかったと云うから全く驚いた。福沢が最も嫌悪したのが、女が知識を開陳して議論することだったとある。慎み深い良妻賢母が新生日本の新しい女性像と成りつつあった時代だ。その流れに流されていたとするなら、彼も思想家としては二流であったということだろう。
- 私の母はとっくに亡くなっている。明治後年生まれであった。母の持ち物に「女大学」があった。和綴じで、よく読まれたのか、かなりぼろぼろだったように思う。調べてみると初版は1716年だ。諭吉は「新女大学」で幾分の修正は試みている。でも日常生活に合わないほどの慎みは止めようといった程度であったらしい。母は女大学の教えをかなり忠実に実践していた。大声、悪口、噂話、饒舌などは、なるだけ排除して生活していたように記憶する。病床に伏すようになって私が見舞いに行ったとき、たまたま担当医がカルテを置いたままにしていたので、読んでみたことがあった。「この物静かな患者は」という表現で始まっていた。当時にしては珍しい女学校出だったが、女らしさを地で行ったように記憶している。記憶だからかなり理想化している点はあるだろうが。
- 女大学思想は室町時代からと云う。儒教思想などとごっちゃに中国からもたらされたのだろう。国内は武家支配体制になり、支配者被支配者の区別が明示されだした。女は男の支配下に組み込まれる。男尊女卑思想が社会通念化する。女は何事にもへりくだり、目立たぬように慎み深く行動せねばならない。このつつしみの行動の事例を、具体的に述べたのが女大学をはじめとする諸々の成書である。つつしみ行動が社会に常識として受け入れられるようになると、その裏にあった男尊女卑思想は忘却されて、女らしさの指標に取り換わる。女らしさの表現に最も手軽なのは言葉だ。そこで登場するのが御所言葉つまり女房詞なのだ。14世紀前半には出ているという。鎌倉幕府が滅びたあたりだからずいぶんと歴史がある。宮中から将軍家へ、さらに大名、家来衆を経て町人層へ移る。江戸時代にはちょっと気取った言い方ほどの意味も含めて、普通に使われていたのだろう。
- 短縮した上で「お」をつける。これが女房詞だとは知らなかった。ダイコンをオダイ(京都の女性は今も使うが、関東では聞かない)、マンジュウをオマン(もう死語に近いのでは)、短縮して重ねる方法もある。コウコウ(京都では男女とも使っている)は香の物から出ている。短縮してモジを後ろに入れる。ソモジ(死語)。堅い感じの漢語を大和言葉に直したのは良かった。いろいろ出ている。でもまだ一般化していない時代には真似る方は往生だったらしいし、笑い話のタネにもなった。狂言の主人と太郎冠者の交わす駄洒落にも出てくるそうだ。
- 本HPの「国語元年」は同名のテレビドラマ(井上ひさし作、NHK)への感想である。このドラマはコミカルタッチで全国統一言葉(標準語)への取り組みの困難性を表現した。配役、演技とも絶妙で秀逸という名にふさわしい作品だった。今は伝説の女優兼歌手ちあきなおみが、鹿児島女弁でのんびりしゃべるあたり、忘れられぬシーンの連続だった。買い集めた女郎たちが、てんでにお国言葉で話してはさまにならぬから、吉原では廓言葉で統一している。標準語作成の参考意見に出てくる話だった。NHKアーカイブスで見ることができる。今の国語には明治の日本が色濃く反映されている。完璧な男社会である。女はお飾りの第二国民だ。民法には女の財産権すら認めなかった。女は男社会を支援し、子孫を絶やさぬようにしてくれればいい。だから男が社会運営に必要な共通言語を持てばいい、京都言葉は女っぽくていけない、首都と云っても東京下町は下品だし、社会を動かすのは中流以上だ、未来を担う書生語はたっぷり入れよう。まあそんなところだったと本書は解説する。
- 「国語元年」は極端だが、ドラマでは出身地とか所属階層とか職業とかの「らしさ」をそれとなく匂わす言葉の挿入によってぐっと引き立つ。小説でも同じだ。明治にはテレビなど無いから小説は話し言葉の指針になった。女学生言葉「てよだわ言葉」の人口膾炙は、小説家の工夫に負うところが大きい。学校が女性に解放されると、男子と同じ服装で書生言葉を使う女子学生が現れる。男社会から半男半女ぶりが非難され、女大学的らしさが要求されると、「てよだわ言葉」が一部女子学生で使われ出す。今ならほんの流行語だったかもしいれない起源不明の言葉らしい。
- 日本近代文学はまずは西洋文学の翻訳から始まった。基本的に男女に言葉の差がない西洋語の翻訳にはたいそうな苦労があった。それで眼をつけたのが「てよだわ言葉」だったという。それが新聞の家庭小説等々に定着して明治の後年には家庭の若奥様、と言っても東京の山の手だろうが、にまで浸透し、準標準語(口語辞典や国語読本からは排除されている第二国民用言語、標準語は第一国民用言語)の地位を獲得していった。本書では女子学生と女学生が区別してある。前者は学生に性別をつけただけだが、後者は芸者や遊女とは異なる、さりとて家庭に囲われているわけでもない新たなインテリ風の、男にとって性的魅力を発揮する若い女と言った意味合いがあるとする。現代の女ことばの多くは女学生言葉に起源を持つ。
- 国語への格上げは、最後は太平洋戦争に至る総力戦体制の構築と、日本が指導する大東亜共栄圏の精神支柱としての、圏内共通語化の目論見と並行して行われた国策の名残だという。どちらも第二国民(女性)はもちろん、植民地各国民をも吸収したアイデンティティ醸成を目指すものだ。いまでも多数民族国家は国家体制の維持に標準語化を推進する。女ことばは、その際、天皇制に繋がる優雅な女房詞と、世界に希な発展を見せた敬語体系との優れた組み合わせとして説明された。かの高名な国語学者・金田一京助もその筋の主張をしているという。
- 国家総動員法発令が昭和13年で、政治参加というアメで、第二国民を総力戦体制に組み込んだ。天皇を頂点とする家父長体制は国家体系として維持された。我々は陛下の赤子とよく言われたものだ。この秩序の中で女性に与えられた役割は銃後の守りである。国定教科書に女ことばが第5期の昭和16年から採用される。標準語はあくまで男言葉中心だが、女ことばも周辺にある国語の一部という位置を遂に獲得した。国語の中の女ことばは「山の手の中流女性」を想定して選ばれた言語で、実際に使われていたとは云えないようだ。女ことば(女語)が口語辞典に初めて単語として出てくるのが、やっと昭和44年だという。戦後24年を経てやっと辞典編纂者の認識するところとなった。広辞苑第二版であった。
- 敗戦により男女平等となり女性の参政権が認められた。女ことばは天皇制との繋がりからは外れて、自然発生説が世の流れになった。敬語多用にして婉曲に穏和に攻撃的言辞を避けるのは性から来る自然の発想で、その具体化に音声の違いを最大限活用したのが女ことばだというのだろう。占領軍の文化干渉も言葉にまでは踏み込まなかった。女ことばは敗戦直後の黒塗りの教科書でも生き残ったし、検定教科書でもちゃんと生きている。占領軍、日本政府、学会などの経緯を知るのもいいが、私は自然発生という以上は、外国言語では我らの女ことばと同じ目標は、いかにして達成されているのかを知りたいと思った。例えば欧米は、今は男女同権でも、我らのような不平等時代が長かったはずである。
- 私の書棚に「女優〜早田雄二コレクションより〜」、サンデー毎日別冊、'91が残っている。原節子から梶芽衣子までの70名ほどの主演級、準主演級の女優写真集だ。出版は映画産業が頂点に達したころだった。彼女たちが出演した多くの日本映画を見た。最近でもときおりTVで放映される。当時は男は男っぽく、女は女っぽく演じるのが当たり前だった。「若い人」の修学旅行団を見送る波止場のシーンであったか、裕ちゃんに着物の浅丘ルリ子が「女が着物を着ると男は淑やかさと優しさを連想する」と云った意味の言葉を口にするが、その着物のような役を女ことばもまた背負っていた。ルリ子が女ことばを取り上げなかったのは、女ことばを女が使うのは常識だったからであろう。
- 今では、タレントと称する人種の中に、言葉だけでなく仕草や服装にまで半男半女の人間が出現するようになった。生理的嫌悪感を感じることさえある。だからか、私は余計に女ことばは耳に快いものだと感じる。これは理屈抜きである。彼らの影響力は、過日の小説家とかメディアほどのものは無かろう。男言葉との距離は、今後はすこしずつは短縮されて行こうが、男が快いと思う限り、女ことばは持続する。快いと感じる感覚はしかしかなりが後天的なものだろう。本書に、聞く方の心理学的調査が欠けているのは残念だ。
('12/10/13)
