社会主義の誤解
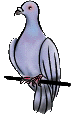
- 薬師院仁志:「社会主義の誤解を解く」、光文社新書、'11を読む。帯に「欧州では社会主義政党が健在。トンチンカンな和製左翼とは無関係」とある。なかなか刺激的な言葉だ。私らの年配者は若い頃一度は左翼思想にかぶれた。理系であっても「資本論」を読みこなそうと努力した時代であった。世界第2位のGDPに躍進した頃には社会主義など時代遅れだった。やがて1億総中産階級時代から格差階級時代に入った。老齢化少子化が進行し成長が止まる。何か社会主義から今後の参考に出来る種を拾えるのではないか。全く新しい思想からつかむより、一度はひもといた思想からの方がより効率的なのではないか。
- マルクス主義や毛沢東主義が社会主義に入るとしても驚かない。イギリス労働党は「労働主義」という社会主義だそうだ。ナポレオンⅢ世の「皇帝社会主義」、チェンバレンの「社会帝国主義」は初めて聞く言葉であった。さらにヒットラーは「国民社会主義」でムッソリーニも社会主義運動の闘士であったと聞くと、社会主義の輪郭が急に不透明になる。極右から極左までを含む社会主義であるが、どれも自由主義に対峙する思想であることに共通点がある。資本主義に対する対抗軸として、ほかに有力な思想は現れていないのも事実だ。社会主義の源流は生産手段の私有に対する異議申し立てである。知識階級のサロン活動から現実の力となるために労働運動の思想的背景となり、それが社会主義の骨格を変えていった。第1章は歴史解説序説で、昔懐かしいマルクス、エンゲルスも登場してくる。
- 川北稔:「イギリス近代史講義」、講談社現代新書、'10(本HP「イギリス近代史」)は、本書のレビューする時代とほぼ一致する。ただしイギリスに力点がある。社会情勢を活写しているからいい参考になるが、本書ほどには階級対立的図式では描いていない。1840年代にマンチェスターの労働者の平均死亡年齢はわずか17歳だった。フランスでは全人口の6人に1人が何らかの救済を必要とする貧困状態であった。持たざるものは「搾取される」自由だけを享受?出来た。支配層からの自由獲得は、保護からの離脱でもある。旧支配層の中世来の救貧の義務は、新興ブルジョワジーに貧民の労役場収容として引き継がれた。そこでは劣等処遇の原則に基づき懲罰的待遇が行われた。その結果富裕層の救貧税負担は劇的に減少した。裏にある思想は労働力の商品扱い、労働者と資本の自由契約である。新支配層は自由にこだわり、貧困自己責任論を通す。産業革命先進国は世界の富を吸収しながら、自国の社会底辺の残酷な荒廃をもたらした。慈善運動はその裏返しである。
- そこでいよいよ労働運動が台頭し、社会主義がそれに粘り着く。紆余曲折の背景に熟練労働者と一般労働者の違いがある。フランス革命の理念に、共和国内における部分的社会の排除がある。労働組合の原型は徒弟型手工業の同業組合や同職団体だが、これらは革命の理念と対立するものとして排除された。しかしこれらの熟練労働者の労働運動が嚆矢であった。彼らはブルジョワジー同様の参政権の獲得を目指し、機械化により低下しそうになる熟練工の地位確保に尽力する。一般労働者との関係はむしろ冷たかった。我が国では近年マスメディアから、正社員の組合が派遣社員に冷たいと批判を浴びたことがある。組合費を支払うものの利益のために動くのが組合だ。派遣社員の言い分のために働けば、結果は分かっている。メディアの論調など浅はかなものだとそのとき感じた。古い職人層の力が弱まり、新興ブルジョワジーと産業労働者の対立という構図が整い始めて、初めて労働運動と社会主義の接点が生まれる。イギリスの団結禁止法の撤廃は、団結も自由の内という思想上の発展がある。
- チュニジアやエジプトの民衆無血革命が中東で成功したことで、タリバンなどのイスラム過激派への支持が弱まるのではないかという観測がある。革命勝利の経験は民衆の力であり自信だ。フランス革命は労働運動のあり方に多大の影響を与えた。7月革命、2月革命ではブルジョワジーが市民革命の生け贄になった。熟練労働者と一般労働者が同じ市民側に立った。指導層は知識階級でありエリート階級であったが、彼らのかざす原理は間違いなく社会主義に通じるものであった。6月の「プロレタリア闘争」の蜂起者は工場労働者ではなかったが、ブルジョワジー対労働者という対立図式を確定化したものであったという。
- 第1インターナショナルのフランス側実質プロモーターがナポレオンⅢ世であったとは目から鱗だった。ナポレオンⅢ世は、皇帝社会主義に入った時代から、組織力のあった上層熟練労働者の支持を得るべく、各様の懐柔策をとる。その一環であった。だが要綱とか宣言を纏めたのはマルクスであった。換骨奪胎とはこのことだ。彼の政治家としての俊敏な働きは以後ことにフランス史に随所で顔を出す。社会主義の浸透が始まる。フランスは19世紀に至っても国民の3/4が農漁業の1次産業を生業とし、工場労働者を選挙の地盤に据えても勝てる情勢には無かった。未熟練労働者には外国人が多く、産業労働者の6割を占めたという。彼らはフランス人賃金引き下げの元凶として一般労働者の排斥運動の対象になっていた。とても「万国のプロレタリアよ団結せよ!」ではなかった。
- 皇帝は普仏戦争に敗れて退位させられる。すでにリヨンの絹撚糸工ストライキに代表される労働争議などで、社会主義者の指導は一定の成果を上げていた。パリを包囲したプロイセン軍を見た市民は、ブルジョワジー時代からの民兵組織を拡大した国民軍を立ち上げる。民衆の愛国の情熱は国民軍を38万に膨らませ、その他武装市民を入れると50万になったという。パリ人口は当時180万だった。新共和国政府(国防政府)に武器引き渡しを拒否したパリ国民軍の自治政権はコミューンを名乗る。だが国防政府がプロイセンとの講和を進めると、民衆の情熱はたちまちにして萎んだ。兵士の数は3万に減り、進軍してきた13万の国防軍に敗れた。まさに「明智の三日天下」であった。社会主義者の呼びかけはフランス全土に及んだが、コミューンが成立したのはパリだけだった。初等教育さえ受けていない民衆が、高等な論理だけで命がけの行動に駆り立てられることはなかった。
- 植民地の収益で、私人の慈善でない公共の福祉を目指す。イギリスのチェンバレンの労働者層への権利拡大はそんな性質のものだった。植民地化にあった国々、その脅威を受けた国々にとっては、まことに忌々しい社会主義である。労働組合運動を直接担う人々が既存の議会制度の中で活動できた理由の一つは、敗戦による八方ふさがりの憂き目を見なかったことであろう。ドイツにも革命的労働運動は根付かなかった。第2インターナショナルは、革命派非革命派が同床異夢ながら社会主義の大儀・資本主義への異議申し立てを旗印に、大同団結できた楽観的雰囲気の時代であった。普仏戦争以来大きな戦いはなく、科学の進歩が未来をバラ色にしたのである。先進国では労働者が議会に無視できぬ勢力を得ていたし、民主化の進行は踏みにじられてはならぬ労働者に地位を獲得していた。1次大戦では各国の社会主義者や労働者組織は、インターナショナル的団結よりも愛国の強調に傾いた。イタリアだけは戦いに非協力だったがこれとて消極的姿勢という程度だった。政治に相応の足場を持たなかったレーニン派のボルシェビキだけが、1次大戦中のドサクサを利用してロマノフ王朝打倒に走った。
- 1次大戦の犠牲と負担の増加、寒波による食料飢饉などが大衆の不満を暴発させたのがロシア2月革命で、足腰の弱い臨時政府を、敵国ドイツの謀略戦術で、スイスから帰国させてもらったレーニンが、ボルシェビキを先頭に大衆を組織化しつつ打倒したのが10月革命である。政権奪取後の共産党最大の難敵は、モスクワの支配を望まぬ少数民族であった。第3インターナショナル(コミンテルン)には参加要件にソビエト革命路線の認証とソ連主導が含まれ、先進国の社会主義勢力を2分することになった。ドイツでもイタリアでも合わせれば「その他」の社会主義政党が多数派であったのに、ヒットラーとムッソリーニの民族主義傾向を強く打ち出す「社会・労働」的政党が合法的に政権を奪うことになる。日本共産党は第3インターナショナルに代表を送っていた。日本共産党は革命政党なのだ。でももし第3インターナショナルが非革命的社会主義党が支配的な会議であったら、非革命政党になったろうと書いてある。思想的にも社会運動的にも後進国であった日本が、易々と社会主義の神髄を汲み取れるはずがないから、所詮は西洋を後追いすることとなったろうと云う。
- 現在でもヨーロッパの社会主義政党は、民衆の中に大きく根を張るメジャーな政党であり続けている。それに反して日本での凋落ぶりは目も当てられぬ。ソシアルはリベラルに相対する言葉だ。'96年に社会党は社会民主党に改組した。社会主義革命の看板を下ろして、西欧型の社会主義政党へ脱皮を試みた。スローガンを「社民リベラル」とした。なんとトンチンカンなことかと書いてある。共産党は共産主義を社会主義の添字にしか使わなくなったが、党名は革命主張のソ連派そのままだ。日本には真にリベラル(自由主義的)な勢力が存在しなかったためでもあるが、社会主義政党は抵抗勢力でありこそすれ、ソシアル(社会主義的)な勢力ではなかったと著者は締めくくる。
('11/05/27)
