感覚器の進化Ⅱ
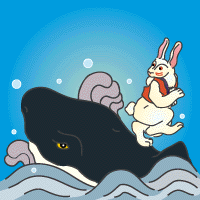
- 以下は、岩堀修明:「図解・感覚器の進化〜原始動物からヒトへ、水中から陸上へ〜」、講談社Blue Backs、'11の読後感:「感覚器の進化」の続編である。
- 水棲動物に側線器という感覚器があるとは初めて知った。古い物理刺激受容器官の一つだ。水の流れを感じ取る器官だ。側「線」だから、脊椎に対し平行にあるいは角度をもって線状に配置されている。お魚では鱗の間に隙間を作り、その中の水流を感じ取る感覚細胞を並べている。体の平衡感覚も、餌となる小魚の微妙な動きも、あるいは大型の敵の運動もこの感覚細胞を分化させることによって、感じるようになろう。分化は水流の大まかなベクトルの感知から、その中の微細な振動をまずは低周波から、ついで追々と高周波の方向に進化していくだろう。側線器が閉じて膜迷路が出来る。平衡感覚を司る半規管が先だった。
- 聴覚器官は、発生学上はあちこちの不要材料の寄せ集めで、既存の部屋に間借りさせられていると読んだことがある。とにかく感覚器としては末っ子の立場だったから、お兄様方お姉様方の使い古しで我慢せねばならなかった。家の部屋ももう満杯状態で新しい居間はなく、膜迷路に同居させてもらう。陸棲となっても水棲時代の基本構造は変えられぬ。だから聴覚器はリンパ液に浸してある。音波は密度の相違により空気からリンパ液にほとんど伝わらない。30デシベルを失うという。
- それを補うのが外耳、中耳の構造だ。レーダーがまだ開発されていなかった時代の敵機探知に、聴音機が使われていた。複数の大型ラッパ管で爆音を集音して、方向距離を測るのである。ヒトの外耳はそれに似た働きを持つなかなかの優れものらしい。中耳は鼓膜の振動をテコの原理で拡大し、内耳との隔壁である小さい前庭窓に連絡する。なんとこの機構によって、失うはずの30デシベルを回復するのだという。中耳の機能に重要な小骨のもともとは、なんと不要となったひれだそうだ。
- 陸棲になって不要になった側線器は退化して消える。再び水に戻ったクジラなどに側線器は再生しなかった。ヒトの蝸牛官は大きい。お魚も聞くことは出来るようだが、ヒトに比べればごく未発達な器官のままである。音が骨伝達で反射が大きいのも理由になっているという。ただ「来い来い出てこい池の鯉」で手をたたくと鯉が顔を出すのは事実である。彼らは例外で、なんとなれば、うきぶくろを持ち空気振動を聴覚器に伝えるからである。この空気振動は、おなかの反射の少ない部分を通してやってくるのだろう。
- ウサギを始め多くの動物の耳が左右独立で集音することは誰でも知っているが、フクロウ、ミミズクの両耳が形も位置も違い、羽毛の生える方向も異なっていて、上下方向の探知が出来るとは知らなかった。二次大戦終わりの頃にもなると我が戦艦大和にもレーダーが積載されていた。しかしアメリカの艦船のそれとは異なり、高度解析が出来なかった。フクロウらはアメリカ軍艦相当で、その他の哺乳類は日本軍艦相当なのである。フクロウらは音源を発射できないから単なる受信機としての比較だが、超音波発射で本当にソナー的探知が出来るのがコウモリである。ただそれが出来るのは小コウモリ類だ。寝るときは耳介(耳たぶ)を折りたたんで騒音侵入を防ぐ。耳栓の能力があるとは知らなかった。
- 私が科学を目指すようになったきっかけは、中学生の時生物班々員になって、生き物の科学と接触したことだ。中学生の接し方は残虐であった。蝶を捕集して標本を作る。捕集したあとバタバタ騒がれては、鱗粉が落ちていい標本にならない。蝶をセロファンの三角紙に手早くたたみ込み、胸部を親指と人差し指に挟み込んで強く押さえる。圧殺するのだ。麻酔薬や殺虫剤は使わない。今でも飛んでいる蝶を見ると、死ぬまでの蝶の循環系の鼓動が指先に、罪悪感と共に、蘇る。心臓の勉強に蛙を材料にした。蛙を解剖台に載せてピン留めにし、生きたままメスとハサミで切ってゆく。麻酔など使わない。心臓は強いもので、蛙が“脳死”してもドキドキと鼓動を打つ。我が身がそんな目にあったならどんなに痛いだろうと、脊椎動物はよりヒトに近いだけに、心の中で念仏を唱えていた。
- でも蝶も蛙も、もがきもせず突っ張りもせず声を上げるでもなく、まさに「心頭滅却すれば火もまた涼し」といった風情で死んでいった。彼らは痛くないのかなという素朴な疑問が胸を去来し今日に至った。主婦は生魚を料理するときは常に生死の現場にあるわけだし、「男子厨房に入らず」と躾けられて育った我ら男子も、踊り食いなどと称して生き魚の生死を支配する機会は結構ある。フィッシングをスポーツと心得るヒトがあるが、魚の痛みは気にならないのだろうか。本書のあとがきに、感覚器の研究の「壁」は、動物たちがその刺激を、どのような感覚で受け取るのか、分からないことだとある。それが逆に救いである。
- 昆虫にも皮膚感覚器があって、外部からの機械的刺激に対応していることは分かっているようだ。いわゆる痛覚に通じるのかどうかはその身になれぬから分からない。脊椎動物には皮膚感覚器に4種類あり、そのもっとも原始的な自由神経終末が、すでに痛覚をも受け持つとある。でも原始感覚は、他の3つの識別感覚と違い、触れているものの形や表面の状態までは分からない。お魚は自由神経終末だけらしいが、両棲類になると識別感覚終末の2つまでを所持している。お魚はなんだか料理されているぞとは分かるが、蛙は解剖の場所をかなり自覚しているはずということだろう。新聞に、研究室が実験動物の命を粗末に扱わない認識を持とうという運動とかが紹介されたり、動物の霊を慰める供養があったりするのは、死の苦痛をヒトも共有しているからに他ならない。「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」。
- 皮膚感覚の一つに温感冷感がある。そのもっとも特殊な例がヘビの赤外線受容だ。ヘビは聴覚も視覚もダメだが、この赤外線受容器が代わりを務める。孔器というのだそうだ。顔に一対付いている。ヘビは恐竜時代にいったん地下に待避し、恐竜が去ってから地上に戻ったが、もう聴覚も視覚も元通りにはならなかった。四肢も退化したままだった。その彼らが生き延びれたのは孔器のお陰なのである。でも温血動物例えばネズミの認識には赤外線受容器でいいが、冷血の蛙や昆虫はどうして感知するのだろう。冷血といっても多少は環境より温度が高いのかな、それとも不自由な目で獲物を探すのだろうか。面白い話だけ疑問もいろいろわいてくる。
- 最後は進化の途上に、いったんは陸に上がりながら、また海に戻っていったクジラの話だ。進化は後戻りできない。その代表が嗅覚で、陸棲するとき、呼吸系統の一部に居候することで見事に適応したのが逆に仇となり、退化の一途を辿った。クジラは一度呼吸をすると、15分ほどは水中で過ごせる。えら呼吸に戻れれば、浮上して捕鯨船の餌食になる歴史など無かったが、それは成らなかった。でもヒトなら1分も息を止めると苦しくてたまらないのに15分である。1回の呼吸で交換する量が、陸棲動物では10〜20%なのに、クジラでは80〜90%だという。赤血球のヘモグロビン、骨格筋のミオグロビンと結合した酸素ももちろん使われる。でもやっぱりお魚に比べれば進化不充分だ。
- TVで見た知識であるが、アフリカの喜望峰あたりは、ある時期、イワシの大群が集まる場所で、それを狙ってクジラも寄ってくる。オキアミなどを餌とするヒゲクジラではなくハクジラだ。彼らはクリック音による反響定位をやる。指向性の鋭い音波で、使う周波数帯は遠距離用近距離用で違っている。超音波探索はコウモリの専売特許ではない。ザトウクジラの歌声は200‾1800kmも遠方に伝わる。何とも信じがたいが本当らしい。海中のクジラにとっては肺の空気は貴重だ。気嚢があって肺との間で空気を往復させ、その中間に声帯に相当する弁を持つ。噴気孔から排出するようなことはしない。陸棲時代の声帯は退化してしまった。聴覚器も大改造された。耳たぶはなくなり外耳孔は申し訳ほどとなった。換わって音を導くのが下顎だ。下顎骨の先端にオトガイ孔があり、下顎官を経て下顎孔に達する。下顎孔が中耳に接している。機能は知らないが、同じ器官がヒトにもあるそうだ。
- 海中は光が弱い。クジラの目は、夜行性のネコなどと同様に、反射器を備えて、微少な光をなんとしても捕らえようとしている。海中で出会うとクジラの目は青く光るそうだ。反射器がコラーゲンだからだそうだ。偶蹄類には青く光る目を持つものがいる。クジラがウシやヒツジと同類である証拠という。
- 知識欲を満たせてくれる良書であった。
('11/04/16)
