感覚器の進化
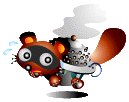
- 岩堀修明:「図解・感覚器の進化〜原始動物からヒトへ、水中から陸上へ〜」、講談社Blue Backs、'11を読む。昨年読んだ本の中で、森憲作:「脳のなかの匂い地図」、PHPサイエンス・ワールド新書、'10は、私にとって「おどろき、もものき、さんしょのき」だったとこのHP(においの科学)で告白した。爾来、その他の感覚器についての関心が高まった。著者は医学系の教授である。索引、参考文献もついている。
- ヒトの瞳孔はいつも円形である。ネコのそれは正午を境にして針状から柿の種状になり朝夕晩には円形に開いている。昼間に林やブッシュの隙間から獲物を狙うのに適している。明るい間は光の量を絞らねばならぬが、この形だときっと必要部分だけ焦点深度がより深まるのだ。ほかのネコ科動物、ライオン、トラやヒョウでもそうなのか、一度動物園でとくと拝見しよう。脊椎動物が無背椎動物とお別れしたのがカンブリア紀だったら、われわれはもう10−11億年も別の道を歩いて来たこととなる。ところがヒトとイカやタコの視覚器の構造は互いに似ている。進化の収斂性というのだそうだ。眼瞼があって、虹彩があって、角膜があって水晶体、ガラス体を経て網膜に至る。断面図を注釈なしに見せられたら、解剖学の知識のない我々には、それはヒトの目あるいは哺乳類動物の目だと云ってしまうだろう。
- 細かく見ると、眼球神経膜はヒトでは網膜の外に色素上皮膜があるのに、イカやタコでは前者だけでしかも薄い。視細胞の光受容部が一番奥にある反転眼構造を我々は持っているのに、彼らのそれは逆で、光に近い方に受容部を持っている。ヒトの網膜は複雑な情報処理機能を内在させるが、イカと同じ構造では、視細胞に栄養を補給し受容部の新陳代謝をさせるのに困難だからだ。イカでは発生の途上表皮から目が作られ、ヒトでは神経管の先端が脳に分化するときに目になる。つまり脳の一部である。でもこの差にはあまり驚かない。発生学を昔囓ったことがあった。脊椎は発生途上に表皮がへこんで作られるから、胚葉から見れば両者は同じ出自なのだ。
- 昆虫の複眼は我々の目とはたいそう違った外観をしているが、その構成要素の個眼は水晶体眼と同じとは知らなかった。ここにも進化の収斂性という言葉が出てくる。動きをとらえるのに最適の構造だとしている。理由は書いてないが、私は画素数の少ないカメラ写真の連続2枚を想定して、差し引きして残る映像が動く物体のものであるとすれば、複眼では画素数が少ないだけに判断が素早いからだと思う。複眼の画素数はせいぜい万個のオーダーだろう(本HP「昆虫−驚異の微小脳」)が、我らの水晶体眼には億単位の視細胞がひしめいているのである。
- ツバメには視神経密度の高い中心窩が2ヶ所あって、1つは我々と同じく前方用だが、もう一つは側方用だという。これは敵に備えているためだろう。アザラシやオットセイは水陸どちらでもピント合わせが出来る優れものの目を持つが、ヒトは水中ではだめだ。ペンギンは逆に陸上ではだめだそうだ。魚眼のピント合わせは、水晶体曲率を変化させるヒトと違って、水晶体の前後移動によって行う。三つ目小僧は怪談話にしか出てこないが、動物にはザラだ。そもそも発生途上に外側眼と同じ位置から出てくるのだ。面白い話がいっぱいだ。
- NHKの昔の朝ドラに、京都の漬けもの屋の、初老期に入った主人が、自分自身のあじの判別能の衰えを自覚するシーンがあった。私も、余興ではあったが、利き酒で全部を当てた時代があった。でも今はもう自信がない。ヒトの味蕾の数は老年期に入ると著しく減少するそうだ。動物の感覚器官の中でもっとも古い歴史を誇るのは味覚である。ジャコウアゲハは麝香で有名だ。私はとうとう1羽も採取できなかった蝶である。京都では亀岡あたりに生息していた。ウマノスズクサにだけ産卵する。この蝶は、この草だけが我が子にとって無毒で安全な食料になると判断する。産卵刺激物質も京大の先生によって解明されているという。
- 味覚は食物の毒性検査器として出発した。その機能を発達させた代表が草食動物だ。植物は自己防衛のためにあの手この手を繰り出す。その一つが有毒物質の分泌だ。それを逆手にとって、自分の捕食防御に利用する幼虫がいる。アセビは馬酔木と書き、馬は食うとフラフラとなってしまう。今馬酔木の花が盛りである。でも都会ではその幼虫(ヒョウモンエダシャク)を見つけることは出来ないのが残念である。
- ナマズは泥の中に住む。目では食料の小魚を追えない。彼は、全身に分布した味蕾によって、小魚の垂れ流す化学物質を感じ取り、正確に捕食する。その味蕾はアミノ酸に反応するそうだ。ヒトの5番目の味感覚・うま味は、味の素の池田菊苗氏の発見だが、ナマズは太古の昔から生きるための道具としていたのだ。鵜呑みの動物:ヘビや鳥には味蕾の数はごく少ないそうだ。
- ファーブル昆虫記は少年の頃から馴染んだ本だ。実験科学者のバイブルだと思っている。フェロモンを見いだしたのはそのファーブルで、19世紀中頃だったという。それからの時代の進歩を、日本化学会編:「一億人の化学3. 新ファーブル昆虫記」、大日本図書、'91で読んだ。20年前すでに相当数のフェロモン物質が同定されていた事が分かる。今はもっと徹底して分かっているのだろう。本書は生物学的背景を重点的に説明しているので、相補的で楽しく読める。フェロモン感覚は嗅覚から分化したと誰しも思う。性フェロモン、警戒フェロモン、道標フェロモンなどは抵抗なく理解できるが、社会性昆虫において体制維持のため女王が分泌する「階級分化フェロモン」は神秘的だ。それを嗅ぐと卵巣の発育が抑制されて、メスとして孵化しながら終生を働きバチで終わる。ヒトにも発生初期にはフェロモンの器官が発現するが、すぐに消えてしてしまう。だが、退化器官はときおり、退化が忘れられたように残留している成人個体が現れることがある。フェロモン感覚器の残存したヒトが出現したら、どんな猟奇事件が起こるであろうか。
- 哺乳類の性フェロモン効果で、ブルース効果と称されるものの内容は衝撃的だ。妊娠しているマウスのケージに交尾相手でないオスを入れると流産するというのだ。オスが自分の遺伝子を遺すために(と意識しているはずはないが)、連れ子を殺す話は、トラやライオンの夫婦関係の説明でよく聞く。ヒトでも連れ子虐待死の話題がしょっちゅうメディアを賑わすようになった。腹の子にまで同じ原理が支配しているとは知らなかった。
- 固有感覚器の話は日頃あまり意識していないから面白かった。動物はなんだかロボットと同じ構造だ。事実はロボットが動物を学んで、そっくりに創り上げたということだ。水の入ったバケツを腕で持ち上げる場合に必要なセンサー相当感覚器があげられている。腕の角度位置、バケツの重さ、関節の曲がり具合などが検知できるように旨く作られていて、それを固有感覚器と総称するのだ。腱受容器という聴力検出器が腱と筋肉の間に挟まっていて、筋繊維が収縮しても伸張してもそれに応じて変形し、活動電位を脳に報告する。仕組みを細かく知れば知るほど感心してしまう。脊椎動物だけではない。昆虫だって負けず劣らず精密なのである。
- 少々長くなった。あとは「感覚器の進化Ⅱ」に記す。
('11/04/16)
